Part4/医療費控除の明細書作成(手書き)編2 ■還付申告には医療費控除の明細書が必要です
医療費控除の明細書をダウンロードし領収書内容の転記と医療費合計額の計算
丹念に領収書の家族名・病院名・支払った金額・医療費控除額などを転記

■記入箇所は領収書の明細欄と控除額の計算
 「医療費控除の明細書」を、“手書き”で書く方法について説明します。繰り返しますが手書きのメリットは、①領収書の枚数が多い方 ②初めて申告される方(間違い防止のため)に分かりやすいからです。逆に領収書の枚数が少ない方は、国税庁のHPに直接入力されたほうが簡単かもしれません。ただ初歩の段階では、“手書き”によって基本的なことを学ばれたほうがよいと考えます。それでは国税庁のHPから、あるいは下記の国税庁のHPにリンクしているので、そこからダウンロードしましょう。
「医療費控除の明細書」を、“手書き”で書く方法について説明します。繰り返しますが手書きのメリットは、①領収書の枚数が多い方 ②初めて申告される方(間違い防止のため)に分かりやすいからです。逆に領収書の枚数が少ない方は、国税庁のHPに直接入力されたほうが簡単かもしれません。ただ初歩の段階では、“手書き”によって基本的なことを学ばれたほうがよいと考えます。それでは国税庁のHPから、あるいは下記の国税庁のHPにリンクしているので、そこからダウンロードしましょう。 「源泉票」、医療費の領収書の現物、「補てん金」が出ていればその資料か金額メモを、全てお手許に置きましょう。ダウンロードされた「医療費控除の明細書」の上部半分が、申告者の氏名や領収書の内容を転記する箇所です。下部が、「控除額の計算」の部分です。ご家族・病院・病気ごとの集計額表示でも認められますので、枚数が多い方はそうしたまとめ方をして下さい。従って領収書の準備段階で、小計を出しておくことをお勧めします。
「源泉票」、医療費の領収書の現物、「補てん金」が出ていればその資料か金額メモを、全てお手許に置きましょう。ダウンロードされた「医療費控除の明細書」の上部半分が、申告者の氏名や領収書の内容を転記する箇所です。下部が、「控除額の計算」の部分です。ご家族・病院・病気ごとの集計額表示でも認められますので、枚数が多い方はそうしたまとめ方をして下さい。従って領収書の準備段階で、小計を出しておくことをお勧めします。▽医療費控除の明細書
(サンプル)・既出 ▽医療費控除の明細書(山田太郎さん一家の記入例)


↑ クリックすると画面が拡大します ↑
医療費控除の明細書のダウンロードはこちらの国税庁HPから
 [そっとアドバイス] 記入方法の注意
[そっとアドバイス] 記入方法の注意①一般的には、黒色または濃紺のボールペン、万年筆等で記入して下さい。
②たった10数件の領収書項目の転記でも、大変なこととお分かり頂けるでしょう。まあ慣れるしかありませんが、後号でもっと簡単な方法をお伝え致します。
■対象年・氏名・住所を記入
 まずは上記のサンプルの山田太郎さん一家の例を見ながら、皆様も記入をお進め下さい。
まずは上記のサンプルの山田太郎さん一家の例を見ながら、皆様も記入をお進め下さい。(1)令和△年分 → 収入があった年(例えば「源泉票」の年度)・医療費を支払った年です。実際には、「医療費控除(還付申告)」する前年の年を入れます。
(2)氏名(申告者名) *押印は不要 (3)住所
*医療費通知に関する事項の説明は、省略します。
■1件ずつの医療費の領収書内容の転記
 ここから、手間が掛かる領収書の内容を1つ1つ転記していきます。
ここから、手間が掛かる領収書の内容を1つ1つ転記していきます。項目2 医療費の明細
(1)医療を受けた方の氏名 → 家族名をフルネームで記入
(2)病院・薬局などの支払先の名称
(3)医療費の区分 4つの項目のいずれかに「レ」(チェック)を入れます。
□診療・治療 □医薬品購入 □介護保険サービス □その他の医療費
(4)支払った医療費の額 → 領収書の金額(または合計額)を記入します。
領収書には数々の金額が載っているので、転記の際に間違えないで下さい。
(5)生命保険や社会保険などで補填(てん)される金額
 全て書き終わったら、「2の合計」へ (ウ)支払った医療費の額の合計 (エ)補てん金の合計(なければ0円)を記入します。続けて「医療費の合計」[A欄](ア)+(ウ)、[B欄](イ)+(エ)を記入します。
全て書き終わったら、「2の合計」へ (ウ)支払った医療費の額の合計 (エ)補てん金の合計(なければ0円)を記入します。続けて「医療費の合計」[A欄](ア)+(ウ)、[B欄](イ)+(エ)を記入します。■医療費控除の明細書・指定用紙のA~Gの記入項目
 「項目3 控除後の計算」は、やや頭を使います。用紙下段の、A~G項目に転記していきます。今1つ自信がない方は、下書きの心境で軽く鉛筆で書いておきましょう。
「項目3 控除後の計算」は、やや頭を使います。用紙下段の、A~G項目に転記していきます。今1つ自信がない方は、下書きの心境で軽く鉛筆で書いておきましょう。▽医療費控除の明細書(控除額の計算)

 [A]「支払った医療費」 350,000(円) → [A欄](ア)+(ウ)の合計額を転記。
[A]「支払った医療費」 350,000(円) → [A欄](ア)+(ウ)の合計額を転記。 [B]「保険金などで補てんされる金額」 120,000(円)
[B]「保険金などで補てんされる金額」 120,000(円)→ 上記と同様に、[B欄](イ)+(エ)の合計額を転記。
 [C]「差引金額(A-B)」 → 230,000(円)を記入。
[C]「差引金額(A-B)」 → 230,000(円)を記入。 [D]「所得金額の合計額」 → 「源泉票」の「給与所得控除後の金額」項目の金額
[D]「所得金額の合計額」 → 「源泉票」の「給与所得控除後の金額」項目の金額3,460,000(円)を記入。
 [E]「D×0.05」 → 173,000(円)を記入。
[E]「D×0.05」 → 173,000(円)を記入。 [F]「Eと10万円のいずれか少ない方(ほう)の金額」→100,000(円)を記入。 (注:下記)
[F]「Eと10万円のいずれか少ない方(ほう)の金額」→100,000(円)を記入。 (注:下記) [G]「医療費控除(C-F)」 → [C]230,000 - [F]100,000 = 130,000(円)を記入。
[G]「医療費控除(C-F)」 → [C]230,000 - [F]100,000 = 130,000(円)を記入。(注) [F]この計算例では、少ない方(ほう)の金額(100,000円)を選択します。但し収入が少ない方(かた)は、[E]のほうが少なくなり、その場合は[E]の金額を選びます。下記リンク参照
 [そっとアドバイス] ここでやっと、「医療費控除額」が導き出されました。この130,000円に対して、既号のように所得税5%(6,500円)が還付、住民税の約10%分(13,000円弱)が安くなるのです。
[そっとアドバイス] ここでやっと、「医療費控除額」が導き出されました。この130,000円に対して、既号のように所得税5%(6,500円)が還付、住民税の約10%分(13,000円弱)が安くなるのです。クリック願います。そして、冒頭ページのリンクインデックスからお移り下さい。











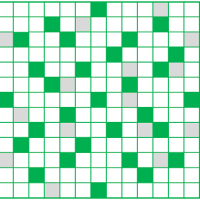



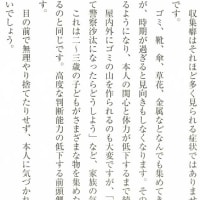







 2月 ベスト10
2月 ベスト10 

























