

 夕刻
夕刻 8/3℃
8/3℃
『雲に雲に聳ゆる 高千穂の。高根おろしに 草も木も。 なびきふしけん 大御世(おほみよ)を。 あふぐ今日こそ たのしけれ。』の歌は後期高齢者であれば大抵戦前の小学校で2月11日の紀元節の式典で歌った経験があろうと思う。 昨日は「建国記念の日」の祭日で神戸生田神社へ行ってみた。 今年は神武天皇皇が日向の国、高天原から東征を重ねながら橿原(奈良県)に進出大和の国、樫原神宮で大和朝廷の天皇に即位したのが記紀伝承上の天皇で日本国の始まり皇紀元年(BC660年)から紀紀2673年とされている。 神戸生田神社は官幣中社で皇室と関わりのある神社で2月11日の建国記念の日には紀元祭が中祭として行われている。

君が代で国旗京葉が終わり神官および氏子代表や参列者が祭りの神事で社殿に向かった。 拝殿に入った神官らが座席に着くと太鼓が打ち鳴らされ雅楽で紀元節の曲が筝じられ神事が始まった。

神官がご神体の扉を鍵で開ける。ご神体は水害による土砂崩れを防ぐものらしいが全く不明である。

ご神体の扉が開かれ、神殿には次々と山海の産物やお神酒などをお供えされ国や国民の安全と子孫繁栄を祈願する祓詞(はらえことば)・祝詞(のりと)奏上された。

神官が参列者へ厄祓いを終わって全員起立で紀元節の歌を歌い1時間ほど終了したが「雲に聳(そび)ゆる高千穂の 高根おろしに草も木も・・・・・」我輩も68年前の小学4年生(10歳)以来に口ぐさんでいた。

おそらくこの日は官幣社や靖国神社・各道府県の護国神社でも同様の紀元祭が行われたようである。 「〔前略〕恐(かしこ)み恐(かしこ)みも白(もう)す」しての生田神社の一時を過ごしたのである。
生田神社から散歩がてら神戸南京町まで歩いたが着いてみると三連休最終日とあってか、春節祭は日本の正月の初詣、同様の混雑で下画像のように、警察官の誘導で高齢者は流れで歩くのがヤットで途中で元町に出て、日を改めて来ることとした。

2013年南京町春節祭は2月17日(日)まで開催



















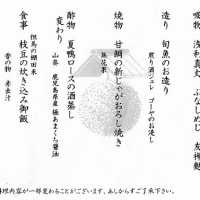
現役時代、業界の2月例会で何時も歌っていました。懐かしい思い出。
大阪の建設会社の17年勤務し、神戸方面にも良く行きました。
生田神社は何度かお参りもし、地鎮祭をお願いしたことも有ります。
でもそのころ南京町という中華街は記憶にありません。
コメント
官幣神社での紀元祭の神事は初めてみました。
日本の建設会社は神社と昔から深い関係があると思っております。
また、神戸南京町の春節祭は1987年が最初ですからdojyou38さんの大阪時代はあまり知られていなかったように思われます。
春節祭も観光客が沢山訪れるようになったのは5年前くらいで 長女家族もまだ行った事が無いそうです。