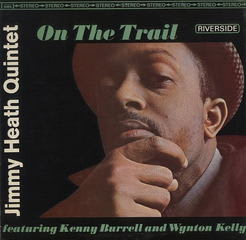今日は天気も良く、じつに爽やかな一日でしたが・・・・・
退散したはずの風邪が、じつは私をだましていたことが発覚しました。昨夜帰宅するとどうも体が重く、途中まで更新をしたブログもそこでストップ、早々に床についたものの、今朝から関節が痛み出し、咳は出るは熱っぽいはでもう大変。こんな日に限って休めないのが仕事っちゅうもんでありまして、マスクをして行ってまいりましたよぉ・・・あは、もう体ボロボロ、今晩あたりが山かもしれません。(笑)
ということで、ここからは昨晩更新しようとしていた内容です。1月13日の記事としてご覧下さい。
★
仕事中にほんのちょっと時間があったので、初詣・・・いや遅詣ですかね、に行ってきました。もちろんちっぽけな神社にはすでに詣る人もなく、境内はひっそりとしておりましたけど、とりあえずはお賽銭もあげ家内安全を祈願してまいりました。
厄年にすらそこそこお詣りもしなかった私が、いまさら神頼みしたところでそうそう御利益があるとも思えませんが、そこはそれ「行かないよりいいだろう」てなもんですね。
ところで、今日1月13日は『タバコの日・ピース記念日』なんだそうでありまして、1946年の今日、現在も販売を続ける「ピース」が自由販売たばこ第1号として発売された日なんだそうです。
当時、既存のタバコが10本入り20~60銭だったのが、「ピース」は10本入りで7円で、日曜・祝日に1人1箱だけに限られた販売だったそうですから、超高級タバコであったのですねぇ
絵柄は・・・・
おっと、これは昔「ピーカン」のくだりで話しましたので今日は止めておきましょう。
「ピース」の発売日はともかく、日本に最初にタバコを持ち込んだのは誰か?となると、大きく分けて「ポルトガル人説」と「スペイン人説」の二つに分かれるんだそうで、誰もが知っている鉄砲伝来とともに種子島にポルトガル人が持ってきたとか、あの面影を忘れようにも忘れられない宣教師ザビエルの従者が吸っていたとか、記録として間違いないのはフランシスコ会修道士三人が、1601年に徳川家康に謁見、その際たまたま病の床にあった家康のために治療薬としてタバコを献上したんだそうで、これが最初という説もあるのだそうです。(これは「スペイン人説」ですね)
もし、この1601年以前にタバコが日本に上陸していなかったとすれば、「ひょっとしたら日本人で始めてタバコを吸ったのは徳川家康」ということになるのですが、残念ながらその記録までは残っていないそうであります。
タバコ税の値上げはひとまず先送りされ、我々喫煙者はホッとしていますが、今後益々肩身が狭くなるのは必定。
「いっそのこと、タバコも麻薬扱いにしてくれ!法律で全面禁止になれば禁煙を考えるから」
なんて、思ってもいないことを口走る私でありましたとさ
さて、今日の一枚は、タッド・ダメロンです。
正直言いまして、私は「ダメロンだぁ、やったぁ聴こう!」という人種ではありません。(笑)
ですから、所有アルバムもマイルス、コルトレーン、デクスター・ゴードンといった共演者に重きを置いたものばかりです。
もちろん、コンポーザーとしての彼の手腕は高く評価していますし、「SOULTRANE」や「HOT HOUSE」といった彼の曲を忘れるわけもありません。
そんな所有枚数の少ないダメロンのアルバムの中で、もっとも彼らしさを感じられるのが今日のアルバムかもしれません。
バップの色は出しつつ、それでいて整然としたアンサンブル、これぞダメロンらしさというものでしょう。(好みは別として)
ただ、いかんせん私には「過去の人」的感覚が抜けないのも確かで、本来ならもう少し注目すべきなのでしょうね。
ダメロンが5管をどうまとめ上げているか、注目してお聴きください。
FONTAINEBLEAU / TADD DAMERON
1956年3月9日録音
KENNY DORHAM(tp) HENRY COKER(tb) SAHIB SHIHAB(as) JOE ALEXANDER(ts) CECIL PAYNE(bs) TADD DAMERON(p) JOHN SIMMONS(b) SHADOW WILSON(ds)
1.FONTAINEBLEAU
2.DELIRIUM
3.THE SCENE IS CLEAN
4.FLOSSIE LOU
5.BULA-BEIGE
★
ということで、昨日更新しようとした内容で本日は失礼いたします。
風邪のぶり返しは初詣が遅れたバチかもしれませんが、なんとか今晩でお暇していただかねばなりませんから、一杯ひっかけたらササッと布団に入り、ヌックヌクで就寝するようにいたしま~~す。