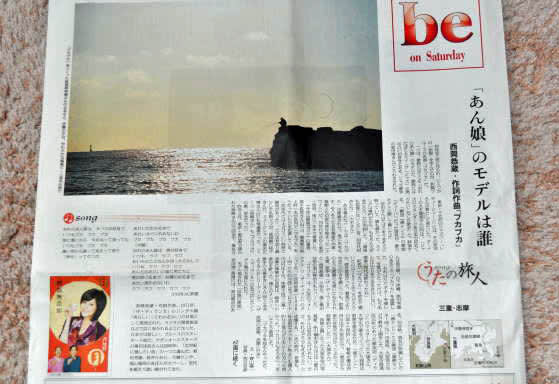「昨日の暖かさはなんじゃったんだい」おもわずツッコミを入れたくなるような、今日はそんな寒い一日でした。
仙台の予備校生に触発されたわけではないんですが、今日は朝方ちょっと暇があったのでgooの『教えて!』とYahooの『知恵袋』を覗いてみました。
『知恵袋』にはジャズというカテゴリーまであって、けっこう多くの質問が寄せられていることにビックリ、さらにビックリするのは、質問に対する反応の早さですよねぇ、いや、言い方は悪いですが、どう考えても緊急性は感じない質問にもじつに反応良く回答されておりました。
「なるほどこのレスポンスの良さなら予備校生が目を付けるのもわかるような・・・」
しかしそれはまた、彼には信頼できる友人がいなかったという証でもあるんでしょうけど。
そんな質問の中に「ジャズ(鑑賞)の中級~上級の方にお聞きします。」てな題目で、「プレイのニュアンスが聴き分けられなくて、ジャズ本や村上春樹が表現している内容が理解できない。そればかりかソロの個人差も聴き分けられない、これはまだまだ聴き足りないということかそれとも生まれ持った耳の悪さか。」といった質問が寄せられておりました。
この質問に対し一時間もしない間に回答が寄せられ、今朝私が見たときにはすでに6件もの回答が投稿されておりました。(スゴイ!)
おっと、話がまた元に戻っちゃいました、そうじゃなくて、この質問と回答を読んでいて、思い出したんですねぇ昔必至でジャズに詳しくなろうとしていた頃を
私の場合、ジャズ喫茶でアルバイトをしていた手前、じゃっかんその必要性はあったんでありますが、それでもよくよく考えれば「詳しくなったからなんなんじゃい」って話ですよ。
評論家になるわけでもなく、村上春樹のような大小説家になるわけでもなく・・・・・
回答者の一人がおっしゃってましたが、「そもそもジャズ・リスニングの初級、中級、上級っちゃ何なんだ」まったくその通りなんであります。
でもねぇ、思い返せば、私も必至で聴き分けやら読みあさりやらしましたもん。あれって自己満足だったり、たまに同類項に打ち勝ったときの優越感だったり・・・・それって、誰もが後になって「バカみたい」って思うことも、その時は「そうは思えない」ってことなんですよね。
あはは、私なんかあの頃の方が間違いなく今より聴き分けが出来てましたよ。
みなさんの中にもいらっしゃるんじゃないでしょうか。ジャズ喫茶で新譜や始めて耳にするアルバムがかかると、ジャケに伸びそうになる手を押さえ「独りブラインド・リスニング」みたいな、そんでもって当たると小さなガッツポーズしたりして(笑)
あれって何の意味があったんでしょうねぇ
でも、どうでしょう(長嶋っぽくね)「そんなん無意味だよ」って言っても、年寄りが若者に説教するようなもんで、あまり良いアドバイスじゃありませんよね。逆に「とことん分かるまで聴けば」と言っておいて、後々「ほぉら、無意味だっでしょ」ってぇのが正解でしょうか。
いずれにしてもジャズ・リスニングだけでなくどんな趣味においても「誰しもが一度はハマル道」なのかも知れませんし「それでイイのかもしんない」
ゆえに、この質問に対する無駄に期間だけが長いリスナー、私の回答は、
朝から晩までジャズを聴いて、メンバー、年代、構成と照らし合わせてりゃ、耳の善し悪しなんか関係無しに、そのうちあなたの言う「上級者」になれますよ。
ですかね。もちろん『知恵袋』には投稿しませんけど(笑)

少なくとも、ジャズに限らず音楽は、
読むものじゃなくて、聴くか奏るもんですから
さて、今日の一枚は、ドン・エリスです。
回答しておいてなんですが、何度聴いても「分からんもんは分からん」という代物はあるもので、エリスのアルバムは私にとってまさにその代物であります。
これが心底の「アンチ」であれば、好きの裏腹で聴き逃せないという存在(私にとってのビートルズみたいなもんですかねぇ)になるんですけど、それとは確実に違いますねぇ、私にとってのエリスは。
この方、頭もいいんでしょうし、理論にもたける方なんでしょうが、どうにも虫が好かんのです。
そもそも今日のアルバムにしても、ジャケット下に書かれた「Third Stream Jazz」ってぇのが、私にはどうしても合いません。(ジョン・ルイスしかり)
それに加えてなんとも身体を動かしにくい変拍子、「早くなったり遅くなったり、いいかげんにしろ!」みたいな。(笑)
最後の「IMPROVISATIONAL SUITE #1」なんざぁアンタ、全部聴くのは拷問にも思えたりします。
以前とある方に「「ASCENSION」だってじゅうぶんに拷問だ」って言われたことがありましたが、その時に「根本が違うんだ!根本が!」てなことをほざいた私はどうかとは思いますけどね。
いずれにしても、エリスに会えたら(そんなことは有り得ませんが)
「アンタはどれほどのブリッコだい?」
と、私は言おうと心に決めています。(笑)
いやぁ、久しぶりに貶しましたねぇ・・・でもこれはあくまで私の個人的嗜好であって、他人様に押しつけるものではありません。
『知恵袋』に投稿された若者には、そういった外野の意見など無視して、自分の耳で聴き込んで好き嫌いを判断していただきたいと思います。
HOW TIME PASSES / DON ELLIS
1960年10月4,5日録音
DON ELLIS(tp) JAKI BYARD(p,as) RON CARTER(b) CHARLIE PERSIP(ds)
1....HOW TIME PASSES...
2.SALLIE
3.A SIMPLEX ONE
4.WASTE
5.IMPROVISATIONAL SUITE #1