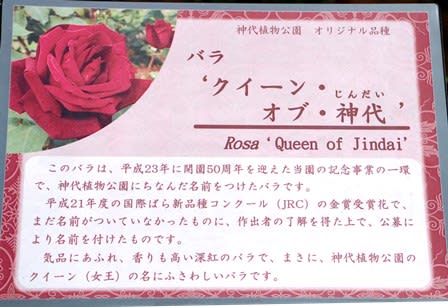水生植物園にも行ってきましたが、
欲張って歩いたので体調が悪くなり入り口付近で引き上げてきました。
初めて見たサワオグルマ等を撮り、
他にもいろいろ咲いていましたが、またの機会にといたしました。
リュウキンカ(立金花)キンポーゲ科
名前の由来:立ち上がった花茎の先に咲く、
金色の花の意味から。

サワオグルマ(沢小車)キク科
名前の由来:水辺に生えて、オグルマに似ているため。

アヤメ(菖蒲) アヤメ科
葉のつき方が文目模様とか、
花の模様から綾目と呼ぶようになったなど。

カキツバタ(杜若)アヤメ科
名前の由来:花を布にこすり付けて、
花の汁で染める古い行事「書き附け」に由来。

カモがゆったりと1羽遊んでいました

欲張って歩いたので体調が悪くなり入り口付近で引き上げてきました。
初めて見たサワオグルマ等を撮り、
他にもいろいろ咲いていましたが、またの機会にといたしました。
リュウキンカ(立金花)キンポーゲ科
名前の由来:立ち上がった花茎の先に咲く、
金色の花の意味から。

サワオグルマ(沢小車)キク科
名前の由来:水辺に生えて、オグルマに似ているため。

アヤメ(菖蒲) アヤメ科
葉のつき方が文目模様とか、
花の模様から綾目と呼ぶようになったなど。

カキツバタ(杜若)アヤメ科
名前の由来:花を布にこすり付けて、
花の汁で染める古い行事「書き附け」に由来。

カモがゆったりと1羽遊んでいました