パソコンとインターネットの普及で紙の情報は電子化され、一時は環境に優しいペーパーレス時代の訪れが喧伝された。しかし紙に打ち出したデータは、一覧性や保管場所の特定などに優れるため、紙が無くなることはなかった。プリンターメーカーも繁盛している。
プリンターのインクカートリッジは、「里帰りプロジェクト」というリサイクル運動が有名だが、果たして見えない所はどうなのか、という経験をした。
使用しているプリンターに、ある日「廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しました。修理窓口に交換をご依頼下さい」という表示が出た。修理を問い合わせた所、「修理部品の保管期限の、製造終了後5年間を過ぎているので、修理できない」と言う。いろいろ高級な機能が付いている機種なに、一つの部品がないという理由で、大きな機械を捨てなければならない。これは明らかに、SDGsの方向と合っていない。
企業の論理は、どんどん新しいプリンターに買い換えてもらう努力にあるかもしれない。頻繁にモデルチェンジをし、信じたくはないが、消耗部品の標準化をしないで、新旧の機種でわざと寸法を変えるというようにしているのではないか。
プリンターのインクカートリッジは、「里帰りプロジェクト」というリサイクル運動が有名だが、果たして見えない所はどうなのか、という経験をした。
使用しているプリンターに、ある日「廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しました。修理窓口に交換をご依頼下さい」という表示が出た。修理を問い合わせた所、「修理部品の保管期限の、製造終了後5年間を過ぎているので、修理できない」と言う。いろいろ高級な機能が付いている機種なに、一つの部品がないという理由で、大きな機械を捨てなければならない。これは明らかに、SDGsの方向と合っていない。
企業の論理は、どんどん新しいプリンターに買い換えてもらう努力にあるかもしれない。頻繁にモデルチェンジをし、信じたくはないが、消耗部品の標準化をしないで、新旧の機種でわざと寸法を変えるというようにしているのではないか。














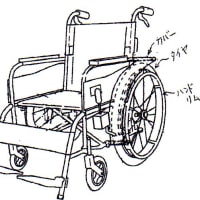
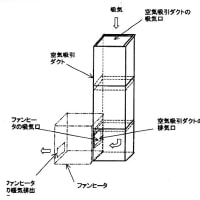
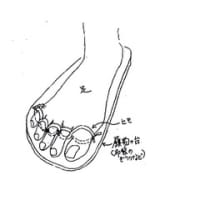





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます