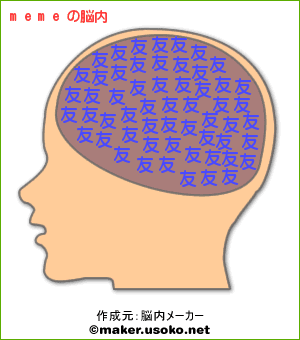最近さっぱり書きませんでしたが
息子はちゃんと(?)定期的に「ことばの教室」に通っています。
以前の「幼児言語教室」とは指導内容が
小学生むけに変わっていて
国語の教科書を読んだり
相手の話し方の速さに惑わされないように
自分のペースで話す訓練したり、
いろんな単語をインプットするみたく覚えたり。
まだ低学年なせいか、うまーく遊びをとりいれて
「勉強」「訓練」という感じを子供に抱かせないようなかんじでやっています。
ちょっと話は逸れますが、
ウチの息子(小学校1年生)は
「を」を、はっきりと「wo」で発音します。
最初のうちは そのまんま「うお」っていってたんですが
最近は「うお」と 早く発音するので「wo」の発音になっています。
自分ちでそういうふうに教えてたことはなく
気付いたら娘達がそう発音していて、
息子が幼稚園のときに
「を」は、「ぅお」って読むの!
とスパルタ教育してました…( ̄ω ̄;)
幼稚園とかで
ちいさな子に「お」と「を」の使い方と区別の仕方を教えるために
発音をわざと分けて教えてたのかな? と何気に思っていたのですが。
このあいだ、言葉の教室で
ひらがなの書かれたカードを、先生が ぱっぱっと取り出し
それを子供が即座に答えてゆく・というものをやりまして。
うちの息子がやはり「wo」の発音をしていたので
帰る時に思わず
「おねえちゃんたちがそうやって教えてるんですよ( ̄m ̄〃)」
と先生に言ったら
「静岡って そうなんですってね~」と、先生。
わたし:「『静岡だから』、なんですか?!」
先生 :「『を』の発音は、「o」でかまわないのに
静岡は「wo」なんですよね~。なんででしょうね?」
そういえば 私は
「ごはんを食べる」の「を」は 「o 」で発音しています。
小学校のときに、そういう風に区別しろ・って教わったこともない・・・。
ただ、「を」のことは「くっつきの『を』」というふうに教えられました。
(助詞の「を」としての説明の意味あい?)
そんで、その日の夜にさっそく静岡生まれ静岡育ちの旦那さんに確認。
「ねーねー、『を』って言ってみて」
「・・・wo」
「テレビを見る って言ってみて?」
「・・・テレビwo見る」
おおー、ちゃんと「wo」だ!
聞こうと思って意識して聞いてみると
「o」じゃなくて「wo」になってます!
旦那さんとはカナリ長く一緒に過ごしてますが
初めて知った!!
で、子供の頃そういうふうに指導されたのか、とか
自分で区別していってるのか としつこく詰め寄ったら(するなって)
「何で?って言ったって、『wo』で当たり前だろ~?」
・・・そうなんだ・・・・('◇')
次の日、やはり静岡生まれ静岡そだちの
ママさん友達に聞いてみました。
「『を』って言ってみて?」
「wo」
で、子供の頃そういうふうに指導されたのか、とか(以下同文)
聞いたら
「ええ~?そんなの、
『あいうえお は あいうえお って発音する』
のと同じくらいに 当たり前のことだもん。
考えた事もないよ~?」
とのこと・・・。
ちなみに旦那さんも友人も
「『くっつきのを』なんてきいたことないよ」
って言ってたよ( ̄▽ ̄;)!!
それにしても、言葉の地域での違いに 久しぶりにびっくりした・・・。
もしかして 方言の範疇に入るのかと思ったけど
それほど 特徴的でもないし・・・
ついでなので書いちゃいます。
高校のときの音楽の先生がいっていたんですが
私が生まれ育った群馬って
濁音をはっきり発音しすぎるため
普通にしゃべっていても
怒っているように受け止められちゃうことがあるんだそうです。
だから、濁音を発音する時は 小さな「ん」をいれて話すようにしたほうがいい
って。
(が=んが って風に。)
たしかに・・・一回だけですが
学生の時に、長野出身の友人としゃべっていたら
「どしたの?なんか怒ってるみたい・・・」
て言われたことがあった・・・。(もちろん、怒ってなどいませんでした)
口は災いのもと
とはちょっとニュアンスが違うような気がしますが
誤解は受けたくないので
それ以来 濁音には気をつけているのでした(;^_^A