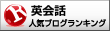『秋』
10.体調管理に努める。
⇒ 英作技法の一つである『抽象と具体思考』を使い、具体的に考える。
『要するにどういうことか』
具体的な生活上のアドバイスとなるだろう。
1. よく寝る
2. 正しい食生活
3. 適度な運動
など。
英語はどうなるか?
1. よく寝る
sleep well.
2. 正しい食生活
正しい食生活とは何だ?
バランスのとれた食生活である。では通常陥りがちなことを考える。
肉や菓子ばかり食べること。それがアンバランスで『正しくない』食事。その結果ビタミンなどの栄養素をとれなくなる。
ということは『野菜を食べよ』ということになる。
・Eat vegetables.
もしくは、先の英作問題でもやった通り『暴飲暴食を慎む』ということにもなるので、
・Don't eat too much. Don't drink too much. も可。
3. 適度な運動
適度な運動とは過剰ではないこと。ということは激しいスポーツではなくやはり『歩くこと』。
・Walk!
・Walk everyday! everyday で『適度』な感じや『規則正しさ』が出るだろう。
『適度な運動』の代表格は『歩く』や『走る』ことなので、両方合わせて、
・Walk or run!
・Walk or run everyday!
尚、通常の『適度な運動』は moderate exercise である。Moderate exercise is good for your health.
なんで『体調管理に努める』が (上記)1~3やねん、と思われる向きもあるだろう。字面だけ見る人はわからない。しかし言葉の内奥を観る人は、上記のように具体的な事柄が心に浮かぶだろう。
例えば医者が患者に『体調管理に気を付けて』と言うとする。しかしその一言を言う医師の念頭には諸々の具体的なアドバイスが浮かんでいる。
その一言にどれほどの意味を見出すか。
『ありがとう』
例えばこの一言。
万感の思いを込めての『ありがとう』。そこに込められた想いとはどんなものだろうか。機械は言葉を訳してくれても『想い』は決して訳してくれない。
本来我々は、状況に応じて言葉の意味を鋭敏に読み取る能力を有する。当たり前の感性を皆もっていた。しかしその当たり前の『察する』能力を、辞書に、権威ある先生に、ネイティブに、または機械翻訳に頼ることで、その人間最大の能力をドブに捨てている。
英語学習におけるリスニング。耳で聞くことも大切だが、何より『心で聴く』ことを忘れてはならない。意外とリスニング・リーディングの伸び悩みは、発音、リエゾン(音の連続)、語彙よりも、何か大事な事を軽んじていることから来ているのかもしれない。
自家(じか)の無尽蔵(むじんぞう)を
抛却(ほうきゃく)して、門に沿(そ)い鉢(はち)を持ちて
貧児(ひんじ)に効(なら)う。
これは、菜根譚(さいこんたん)という中国の古典にある言葉である。
『自分の中にある無尽蔵の宝を捨てて、物乞いをする(子供)のようだ』
古典の叡智を英語学習に当てはめるとどういう意味となるのか。
人として当たり前の事。それを大事にすることが英語上達にも不可欠である。
以上。
10.体調管理に努める。
⇒ 英作技法の一つである『抽象と具体思考』を使い、具体的に考える。
『要するにどういうことか』
具体的な生活上のアドバイスとなるだろう。
1. よく寝る
2. 正しい食生活
3. 適度な運動
など。
英語はどうなるか?
1. よく寝る
sleep well.
2. 正しい食生活
正しい食生活とは何だ?
バランスのとれた食生活である。では通常陥りがちなことを考える。
肉や菓子ばかり食べること。それがアンバランスで『正しくない』食事。その結果ビタミンなどの栄養素をとれなくなる。
ということは『野菜を食べよ』ということになる。
・Eat vegetables.
もしくは、先の英作問題でもやった通り『暴飲暴食を慎む』ということにもなるので、
・Don't eat too much. Don't drink too much. も可。
3. 適度な運動
適度な運動とは過剰ではないこと。ということは激しいスポーツではなくやはり『歩くこと』。
・Walk!
・Walk everyday! everyday で『適度』な感じや『規則正しさ』が出るだろう。
『適度な運動』の代表格は『歩く』や『走る』ことなので、両方合わせて、
・Walk or run!
・Walk or run everyday!
尚、通常の『適度な運動』は moderate exercise である。Moderate exercise is good for your health.
なんで『体調管理に努める』が (上記)1~3やねん、と思われる向きもあるだろう。字面だけ見る人はわからない。しかし言葉の内奥を観る人は、上記のように具体的な事柄が心に浮かぶだろう。
例えば医者が患者に『体調管理に気を付けて』と言うとする。しかしその一言を言う医師の念頭には諸々の具体的なアドバイスが浮かんでいる。
その一言にどれほどの意味を見出すか。
『ありがとう』
例えばこの一言。
万感の思いを込めての『ありがとう』。そこに込められた想いとはどんなものだろうか。機械は言葉を訳してくれても『想い』は決して訳してくれない。
本来我々は、状況に応じて言葉の意味を鋭敏に読み取る能力を有する。当たり前の感性を皆もっていた。しかしその当たり前の『察する』能力を、辞書に、権威ある先生に、ネイティブに、または機械翻訳に頼ることで、その人間最大の能力をドブに捨てている。
英語学習におけるリスニング。耳で聞くことも大切だが、何より『心で聴く』ことを忘れてはならない。意外とリスニング・リーディングの伸び悩みは、発音、リエゾン(音の連続)、語彙よりも、何か大事な事を軽んじていることから来ているのかもしれない。
自家(じか)の無尽蔵(むじんぞう)を
抛却(ほうきゃく)して、門に沿(そ)い鉢(はち)を持ちて
貧児(ひんじ)に効(なら)う。
これは、菜根譚(さいこんたん)という中国の古典にある言葉である。
『自分の中にある無尽蔵の宝を捨てて、物乞いをする(子供)のようだ』
古典の叡智を英語学習に当てはめるとどういう意味となるのか。
人として当たり前の事。それを大事にすることが英語上達にも不可欠である。
以上。