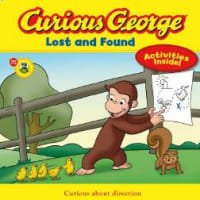久しぶりに海外の作家の翻訳推理小説を読んだ。この本のことは bookook さんのブログ記事で知った。ブログを書き始める前は、J・グリシャムの小説をはじめかなり翻訳推理小説を読んでいた。特に法廷物に関心を抱いていた。その分野の翻訳小説がその後書棚に数多く眠ったままになっている。
この本、そのタイトルから法廷物の推理小説かと勝手に思いこんでいた。読み始めて気づいた。元刑事の探偵がいわば警察の下請け的に殺人事件の捜査を行い、事件を解決に導くという探偵推理小説である。元刑事でも探偵なので捜査という用語が適切でないのかもしれないが、ここでは捜査という語で語ろう。
主人公はダニエル・ホーソーン。「もともとはロンドン警視庁に勤務していたのだが、児童ポルノ売買の容疑者がコンクリート製の階段から転落するという事故の後、職を辞することになった。事故のとき、容疑者のすぐ後ろに立っていたから」(p26)ということで、失職した元刑事の探偵。だが、泥沼事件のたぐいには警察がホーソーンに協力を要請するという関係が維持されている。
この小説の特徴は、ここに「わたし」が加わることにある。「わたし」とは本書の著者アンソニー・ホロヴィッツ自身。この点がおもしろい。ストーリーの中では、テレビドラマの脚本家としての仕事も手がけている。ホーソーンの捜査に「わたし」が同行し、その「わたし」の視点からホーソーン自身についてと事件捜査の経緯を叙述していくというスタイルになっている。
なぜ同行するのか。この小説、実は第2作で、『メインテーマは殺人』というのが第1作。その中に二人の関わった経緯が具体的に記されているという。いずれ第1作も読んでみようと思っている。
ホーソーンが捜査して解決する事件を本にまとめるということに合意し、出版元と三冊まとめての契約をしてしまったことに、同行する理由がある。
この小説のおもしろいところは、殺人事件の捜査とその解決についての本を出版するためにホーソーンに同行するプロセス自体を叙述している点にある。いわば、事件を本にまとめるための最終原稿を書く前段階、事件の捜査状況そのものを記録していくことがストーリーになっている。私にはそのように読めた。つまり、その叙述自体がこの『その裁きは死』という作品に仕上がっているという構造なのだ。なんとも奇妙でかつおもしろい構成である。こういうスタイルの推理小説は初めて読む気がする。
さて、このストーリーについて語ろう。
北ロンドンのハムステッドで殺人事件が発生した。被害者はリチャード・プライス。離婚裁判の分野では著名な離婚弁護士。殺人現場は<サギの泳跡>と称されるリチャードの自宅の書斎。犯人は、1982年ものワインの未開栓ボトルでリチャードの前頭部から額にかけて殴打し、砕けたボトルの首で被害者の喉を刺突して殺害した。本棚にはさまれた壁には、182という三つの数字が緑煙色のペンキで乱暴に描かれていた。だが、リチャードは禁酒主義者だった。
現場を検分したホーソーンの捜査はここから始まっていく。わたしはホーソーンに同行し、自らも犯人について推理をしつつ、ホーソーンの捜査プロセスの記録者となっていく。
事件現場には、この事件を担当するカーラ・グランショー警部が居た。グランショー警部はこの事件を解決するのは自分自身だと宣言し、ホーソーンの動きを逐一報告するようにわたしに圧力をかける行動に出る。このストーリーの中では、ちょっと三枚目的な役割で花を咲かせる役回りである。
リチャード・プライスは同性婚しており、連れ合いのスティーヴン・スペンサーは殺人事件の起こった夜は、別荘に居たという。
リチャードはエイドリアン・ロックウッドの依頼で離婚訴訟の代理人として離婚訴訟に臨み、エイドリアンの妻アキラ・アンノには厳しい裁定を勝ち取っていた。凶器に使われたワイン・ボトルはロックウッドからの贈り物だった。
アキラ・アンノがある場所で、リチャードをワインのボトルで殴ると脅しているという話が事件発生前に伝わっていた。
もう一つこのストーりーの特徴がある。ホーソーンがわたしを同行させるが、その捜査過程で、ホーソーンは自分自身の捜査の推理を一切わたしには明かさないという展開になる点だ。わたしは同行時のホーソーンの捜査行動について、捜査場所、聞き込み相手への質問と会話、ホーソーンとわたしとの間の会話などを語っていく。それらの情報集積から、わたしはわたしとしての推理を展開していく。
たとえば、ホーソーンはリチャード・プライスの人間関係や過去暦を捜査する。リチャードは洞窟探検を趣味としていて、<長路洞>と称される洞窟探検を3人のパーティで行い、一人が死亡するという経験をしていた。その未亡人、ダヴィーナ・リチャードソンに聞き込みに行く。夫の死後、リチャードソンがダヴィーナと息子コリンの面倒を見てくれてきた事実を知る。また、もう一人が、長路洞のあるヨークシャーに住むグレゴリー・テイラーだとわかる。後に、そのグレゴリー・テイラーは、リチャードの殺害される前日、キングス・クロス駅で轢死していたことが報道されていた事実もわかる。
わたしとホーソーンがダヴィーナの自宅を再訪した時、ダヴィーナがアキラ・アンノの労作の俳句本を読んでいた。わたしは、伏せられた本のページをついめくり、その先頭に「君が息 耳にぞ告ぐる 裁きは死」という句に目を留める。その句は第182句だった。(p233)
ホーソーンの捜査活動から、様々な断片的情報が次々に累積されていく。そこからリチャードソンの過去が明らかになっていくにつれ、人間関係の複雑な交錯が一層事件の謎解きを混迷させていく。
わたしの視点と推理から眺めると、一見、事実が解明されたように見える。だが、そうではなかった。二転三転する推理の組み直し・・・・・そこにこの作品の巧みさが現れている。一つの事実にどのような意味づけができ、解釈ができるか。それが推論を誤らせることにもなる。
ホーソーンは最後の最後まで、己の推理内容を明らかにしない。一方、わたしはどんでん返しの矢面に直面することになる。この二人の組み合わせが実に楽しめる。
本書のタイトルは、第182句「君が息 耳にぞ告ぐる 裁きは死」の下五に由来するのだろう。「182」という三つの数字が何を意味するか。読んでお楽しみ、というところに突き進んで行く。
ホーソーンとわたし、という二人三脚は、シャーロック・ホームズとワトソン博士の組み合わせを連想させる。「読書会」という章で、コナン・ドイルの『緋色の研究』を題材に扱った場面を組み込んでいるところもおもしろい。
ホーソーンという人物像をわたしがつかみきれていないということをあちらこちらで触れていること自体がストーリーの一部になっているというなんとも奇妙なところがなんともおもしろい。第3作が書かれるとしたら、ホーソーンの人物像がクリアになるのだろうか。著者はどのように描き出していくのか。別の意味での楽しみができた。
ご一読ありがとうございます。
この本、そのタイトルから法廷物の推理小説かと勝手に思いこんでいた。読み始めて気づいた。元刑事の探偵がいわば警察の下請け的に殺人事件の捜査を行い、事件を解決に導くという探偵推理小説である。元刑事でも探偵なので捜査という用語が適切でないのかもしれないが、ここでは捜査という語で語ろう。
主人公はダニエル・ホーソーン。「もともとはロンドン警視庁に勤務していたのだが、児童ポルノ売買の容疑者がコンクリート製の階段から転落するという事故の後、職を辞することになった。事故のとき、容疑者のすぐ後ろに立っていたから」(p26)ということで、失職した元刑事の探偵。だが、泥沼事件のたぐいには警察がホーソーンに協力を要請するという関係が維持されている。
この小説の特徴は、ここに「わたし」が加わることにある。「わたし」とは本書の著者アンソニー・ホロヴィッツ自身。この点がおもしろい。ストーリーの中では、テレビドラマの脚本家としての仕事も手がけている。ホーソーンの捜査に「わたし」が同行し、その「わたし」の視点からホーソーン自身についてと事件捜査の経緯を叙述していくというスタイルになっている。
なぜ同行するのか。この小説、実は第2作で、『メインテーマは殺人』というのが第1作。その中に二人の関わった経緯が具体的に記されているという。いずれ第1作も読んでみようと思っている。
ホーソーンが捜査して解決する事件を本にまとめるということに合意し、出版元と三冊まとめての契約をしてしまったことに、同行する理由がある。
この小説のおもしろいところは、殺人事件の捜査とその解決についての本を出版するためにホーソーンに同行するプロセス自体を叙述している点にある。いわば、事件を本にまとめるための最終原稿を書く前段階、事件の捜査状況そのものを記録していくことがストーリーになっている。私にはそのように読めた。つまり、その叙述自体がこの『その裁きは死』という作品に仕上がっているという構造なのだ。なんとも奇妙でかつおもしろい構成である。こういうスタイルの推理小説は初めて読む気がする。
さて、このストーリーについて語ろう。
北ロンドンのハムステッドで殺人事件が発生した。被害者はリチャード・プライス。離婚裁判の分野では著名な離婚弁護士。殺人現場は<サギの泳跡>と称されるリチャードの自宅の書斎。犯人は、1982年ものワインの未開栓ボトルでリチャードの前頭部から額にかけて殴打し、砕けたボトルの首で被害者の喉を刺突して殺害した。本棚にはさまれた壁には、182という三つの数字が緑煙色のペンキで乱暴に描かれていた。だが、リチャードは禁酒主義者だった。
現場を検分したホーソーンの捜査はここから始まっていく。わたしはホーソーンに同行し、自らも犯人について推理をしつつ、ホーソーンの捜査プロセスの記録者となっていく。
事件現場には、この事件を担当するカーラ・グランショー警部が居た。グランショー警部はこの事件を解決するのは自分自身だと宣言し、ホーソーンの動きを逐一報告するようにわたしに圧力をかける行動に出る。このストーリーの中では、ちょっと三枚目的な役割で花を咲かせる役回りである。
リチャード・プライスは同性婚しており、連れ合いのスティーヴン・スペンサーは殺人事件の起こった夜は、別荘に居たという。
リチャードはエイドリアン・ロックウッドの依頼で離婚訴訟の代理人として離婚訴訟に臨み、エイドリアンの妻アキラ・アンノには厳しい裁定を勝ち取っていた。凶器に使われたワイン・ボトルはロックウッドからの贈り物だった。
アキラ・アンノがある場所で、リチャードをワインのボトルで殴ると脅しているという話が事件発生前に伝わっていた。
もう一つこのストーりーの特徴がある。ホーソーンがわたしを同行させるが、その捜査過程で、ホーソーンは自分自身の捜査の推理を一切わたしには明かさないという展開になる点だ。わたしは同行時のホーソーンの捜査行動について、捜査場所、聞き込み相手への質問と会話、ホーソーンとわたしとの間の会話などを語っていく。それらの情報集積から、わたしはわたしとしての推理を展開していく。
たとえば、ホーソーンはリチャード・プライスの人間関係や過去暦を捜査する。リチャードは洞窟探検を趣味としていて、<長路洞>と称される洞窟探検を3人のパーティで行い、一人が死亡するという経験をしていた。その未亡人、ダヴィーナ・リチャードソンに聞き込みに行く。夫の死後、リチャードソンがダヴィーナと息子コリンの面倒を見てくれてきた事実を知る。また、もう一人が、長路洞のあるヨークシャーに住むグレゴリー・テイラーだとわかる。後に、そのグレゴリー・テイラーは、リチャードの殺害される前日、キングス・クロス駅で轢死していたことが報道されていた事実もわかる。
わたしとホーソーンがダヴィーナの自宅を再訪した時、ダヴィーナがアキラ・アンノの労作の俳句本を読んでいた。わたしは、伏せられた本のページをついめくり、その先頭に「君が息 耳にぞ告ぐる 裁きは死」という句に目を留める。その句は第182句だった。(p233)
ホーソーンの捜査活動から、様々な断片的情報が次々に累積されていく。そこからリチャードソンの過去が明らかになっていくにつれ、人間関係の複雑な交錯が一層事件の謎解きを混迷させていく。
わたしの視点と推理から眺めると、一見、事実が解明されたように見える。だが、そうではなかった。二転三転する推理の組み直し・・・・・そこにこの作品の巧みさが現れている。一つの事実にどのような意味づけができ、解釈ができるか。それが推論を誤らせることにもなる。
ホーソーンは最後の最後まで、己の推理内容を明らかにしない。一方、わたしはどんでん返しの矢面に直面することになる。この二人の組み合わせが実に楽しめる。
本書のタイトルは、第182句「君が息 耳にぞ告ぐる 裁きは死」の下五に由来するのだろう。「182」という三つの数字が何を意味するか。読んでお楽しみ、というところに突き進んで行く。
ホーソーンとわたし、という二人三脚は、シャーロック・ホームズとワトソン博士の組み合わせを連想させる。「読書会」という章で、コナン・ドイルの『緋色の研究』を題材に扱った場面を組み込んでいるところもおもしろい。
ホーソーンという人物像をわたしがつかみきれていないということをあちらこちらで触れていること自体がストーリーの一部になっているというなんとも奇妙なところがなんともおもしろい。第3作が書かれるとしたら、ホーソーンの人物像がクリアになるのだろうか。著者はどのように描き出していくのか。別の意味での楽しみができた。
ご一読ありがとうございます。