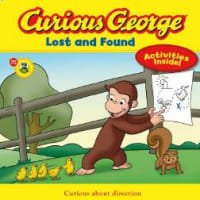著者の作品を読むのはこれが初めて。かなり前に、本書の新聞広告で「矛」と「楯」、つまり「矛盾」という語に触れていたことが読んでみようと思う動機だったのではなかったかと思う。私にとっては初作家なので、地元の図書館で予約、長らく順番待ち待ちして、今読了した。著者は本作品で直木賞を受賞。それが長らく待っことになった理由の一つなのだろう。本書は、「小説すばる」(2019年8月号~2020年12月号、2021年3月号~8月号)に連載された後、2021年10月に単行本が刊行された。借り出したのは、2022年2月の第9刷である。多分、現在は刷版の数字が大きくアップしていることと推察する。
ストーリーに引きこまれ、つい感涙する箇所が複数あった。おもしろい時代小説だ。
「矛盾」とは、「ほことたて」。「盾・たて」は、本書のタイトル中の「楯」も同義である。中国の古典『韓非子』に載る故事に由来する。「(中国の楚の国に矛と盾を売る者があって、この矛はどんな盾をも貫くといい、この盾はどんな矛でも防ぐと言ったが、その矛でその楯を突いたらどうなるかと反問されて、答えられなかったという)前後のつじつまが合わないこと」(『日本語大辞典』講談社)
そこで矛と楯がこの作品とリンクしてくる。読了してこの発想の取り込みが秀逸だと感じた。
近江国(滋賀県)には、穴太(あのう)と国友という地名がある。前者の地域には石積みに秀でた「穴太衆」と呼ばれる人々、プロフェッショナルが居た。穴太衆は道祖神「塞の神」を信奉していて、石積みの技術・技能に最も秀でた人を「塞王」と称したという。穴太衆は「野面積み」という技法を最も得意とする石積み技術のプロ集団。ここでは、まず飛田屋を名乗る飛田源斎が塞王として登場する。塞王が頭となり作った石積みが「楯」である。攻城戦において城を守るのは石垣であり、「楯」の役割を果たす。一方、近江の湖北には国友村があり、そこでは鉄砲の製造が盛んであった。国友三落が国友衆の頭としてその頂点に居た。彼は「砲仙」と称されていた。鉄砲がここでは「矛」となる。
奇しくも、近江国に、全国の大名達が求める「楯」と「矛」を生業とするプロフェッショナルの両雄が存在した。源斎は、飛田屋集団を率い戦国時代に大名の注文を受け各地で石垣積みを行った。このストーリーでは近江の安土城、大津城、京の伏見城が登場する。 三落は勿論国友鉄砲の製造・販売である。秀吉に攻められて鉄砲の巨大産地だった根来が壊滅した後は、国友が鉄砲生産量でトップとなっていた。
「互いに命に纏わる物作り」を行い、「三落はこれまで次々と新作の鉄砲を生みだし、源斎はそれに対抗する石垣を造ってきた。この二人で国友、穴太の技は百年進んだと言われるほど。世間では好敵手のように言われている」(p128)存在である。城の攻防戦では塞王源斎と砲仙三落はほぼ互角の状況だった。
このストーリー、「序」は、織田信長が朝倉の一乗谷に侵攻し、焼き払い、浅倉氏を滅亡させる時点から始まる。石積みの仕事でこの地に来ていた源斎が、この戦乱で孤児となる男の子・匡介を、一乗谷から脱出して穴太に連れて帰る。このとき匡介は気づいていなかったが、源斎は匡介が持つ石の声を聞き、姿を感じ取る天賦の才を発見していた。
第一章は、源斎が、匡介を己の後継ぎに指名した時点以降、つまり匡介が副頭となっている時点から始まっていく。飛田屋には源斎の親類に玲次がいて、飛田屋を継ぐ候補者でもあったのだが、彼は石の運搬をする荷方の小組頭になる。匡介と玲次の人間関係がこのストーリーの一つの要素となっていく。
一方、国友三落の許には、彦九郎という匡介より一つ年上の職人が早くも後継者となっていた。彦九郎もまた次々に鉄砲に工夫を加え新作を製造していた。
このストーリー、源斎と三落の好敵手関係を礎にして、世代が匡介と彦九郎へとバトンタッチされ、匡介と彦九郎がライバル関係となっていく。その移行期と移行後を描き出す。
移行期におけるストーリーの山場がまず描かれる。本能寺の変の直後において、蒲生親子の籠もる日野城における石積みを飛田屋源斎が請け負う。「懸(かかり)」と称する仕事を戦の直前から戦の最中に行うことになる。源斎と匡介が飛田屋集団を率いて行う石積みである。
そして、源斎が秀吉の要請を受け、伏見城の縄張りをすることになる。この時、匡介は源斎から大津城を任される。蛍大名と陰口される京極高次が治める湖上の城である。この外堀は空堀だったが、匡介が差配して水堀にするプロセスが描かれる。
この「懸」と「水堀化」がこのストーリー構成に読者を引きこんでいく導入的な山場となる。
関ヶ原の戦い、このエポック・メーキングとなる戦いはその関連事象としてさまざまな戦を多発している。ここでは、伏見城と大津城での戦に焦点が絞られていく。結果的には伏見城は落城し、大津城はからくもぎりぎりまで持ちこたえた後、高次が開城を決意した。だがこの二城での戦の経緯と期間が、間接的に関ヶ原での結果に重要な影響を及ぼしていたことになる。
伏見城で「懸」を請け負う源斎の視点からの伏見城の攻防戦が一つの山場として描かれる。ここには国友彦九郎が西軍に加担して攻める側となる。彦九郎の矛(鉄砲)と源斎の築く楯(石垣)との攻防戦である。
その先に、メインの山場が描き出されて行く。舞台は大津城。蛍大名京極高次の兵力は3000人規模である。一方、西軍は総大将毛利元康のもとに4万人軍勢となる。その中には、西国無双と称される立花宗茂と3000人の兵力が加わっていた。この大津城の攻防戦では、国友彦九郎は立花宗茂の許に加わる。
この大津城の攻防戦は、実質的に塞王とみなされる立場になった飛田屋匡介と国友彦九郎との攻防戦の側面が描き込まれていく。大津城に入り、「懸」として石積みを行う飛田屋集団がさまざまな工夫をする。そのプロセスがストーリーを盛り上げていく。そして、ファイナルステージは、立花宗茂の攻略戦とそれに対する防戦、そして大津城の天守を護る為に匡介が築く石積み(楯)と、国友彦九郎の製造した大筒「電破」(矛)との間での攻防戦が中心となっていく。
読者がこれらの攻防戦に自然と引きこまれていくことになり、感情移入していくことになるだろう。少なくとも私は感情移入しつつ読むことになった。
「序」と「終」の間は,9章立てに構成されている。単行本の総ページは552ページ。
「第七章 蛍と無双」が大津城での攻防戦の始まりとなる。それは p325 からである。216ページが第七章~第九章に当てられている。このストーリーは、匡介と彦九郎の戦いがメインの山場になっていくことがこの構成からでもわかる。
基礎的史実を踏まえた上でのフィクション化だ思うが、どのあたりからがフィクションなのだろうか。その点が私にはわからないが、時代小説としては大いに楽しめる。
穴太衆、国友衆と称される職人群は存在した。この小説で描かれる人々のモデルはいるだろうけれど、登場人物はたぶんフィクションだろう。京極高次と初は実在した人物だが、ここで描かれたキャラクターはどこからがフィクションだろうか。おもしろい設定になっている。その点、興味深い。立花宗茂のキャラクター設定も同様に私には興味深い。
最後に、この小説で印象深い箇所を引用しご紹介して終りたい。
*城の縄張りは重要な機密であるため、穴太衆は紙に一切の記録を残さず、全て頭の中に図面を引いて行う。そしてそれは同じ穴太衆であっても決して外に漏らさない。
積み方の技術も同様である。一子相伝、しかも全て口伝である。こうして穴太衆は技術の漏洩を防ぎ、依頼主の信用を勝ち取ってきた。 p52
*片やどんな城でも打ち破る至高の矛。片やどんな攻めも撥ね返す最高の楯。矛盾という言葉がこれほどしっくり当て嵌まることも少なかろう。
だがこの世に矛盾は存在しない。必ずどちらかに軍配が上がるのである。 p133
*それが時として自らの命を縮めることになろうとも、人は研鑽の道を歩むことを止めない。そう考えれば人が技を生み出しているのではなく、技という得体の知れぬものが、自らが世に出るために人に憑依して操っているかのように思える。 p141
*世に矛があるから戦が起こるのか、それを防ぐ楯があるから戦が起こるのか。いや、そのどちらも正しくなく、人が人である限り争いは絶えないのかもしれない。
だが、それを是とすれば人は人でなくなる。ならば矛と楯は何のために存在するのか。人の愚かさを示し、同じ過ちを起こさせぬためではないか。 p538
ご一読ありがとうございます。
補遺
穴太衆 :ウィキペディア
穴太衆積みの石垣 :「比叡山・びわ湖」
「穴太衆」伝説の石積み技を継ぐ末裔に立ちはだかる壁とは:「中川政七商店の読みもの」
第48回【歴史】「穴太衆(あのうしゅう)」ってよく聞くけど何をした人たちなの?
:「城びと」
国友 :ウィキペディア
国友鉄砲ミュージアム ホームページ
国友(歴史を陰で支えた隠れたる名工の里):「須賀谷温泉Blog」
京極高次 :ウィキペディア
京極高次 :「コトバンク」
初 ⇒ 常常院 :ウィキペディア
「意地」と「計算」から家康の東軍に味方したホタル大名「京極高次」(東軍)
江宮隆之 :「歴史人」
立花宗茂 :ウィキペディア
1.種子島銃(ポルトガル初伝銃) :「種子島 西之表市」
火縄銃(鉄砲)の種類 :「刀剣ワールド」
12. 林流抱大筒 :「シニアネット久留米」
一宮藩の大筒 千葉県教育委員会 :「千葉県」
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
ストーリーに引きこまれ、つい感涙する箇所が複数あった。おもしろい時代小説だ。
「矛盾」とは、「ほことたて」。「盾・たて」は、本書のタイトル中の「楯」も同義である。中国の古典『韓非子』に載る故事に由来する。「(中国の楚の国に矛と盾を売る者があって、この矛はどんな盾をも貫くといい、この盾はどんな矛でも防ぐと言ったが、その矛でその楯を突いたらどうなるかと反問されて、答えられなかったという)前後のつじつまが合わないこと」(『日本語大辞典』講談社)
そこで矛と楯がこの作品とリンクしてくる。読了してこの発想の取り込みが秀逸だと感じた。
近江国(滋賀県)には、穴太(あのう)と国友という地名がある。前者の地域には石積みに秀でた「穴太衆」と呼ばれる人々、プロフェッショナルが居た。穴太衆は道祖神「塞の神」を信奉していて、石積みの技術・技能に最も秀でた人を「塞王」と称したという。穴太衆は「野面積み」という技法を最も得意とする石積み技術のプロ集団。ここでは、まず飛田屋を名乗る飛田源斎が塞王として登場する。塞王が頭となり作った石積みが「楯」である。攻城戦において城を守るのは石垣であり、「楯」の役割を果たす。一方、近江の湖北には国友村があり、そこでは鉄砲の製造が盛んであった。国友三落が国友衆の頭としてその頂点に居た。彼は「砲仙」と称されていた。鉄砲がここでは「矛」となる。
奇しくも、近江国に、全国の大名達が求める「楯」と「矛」を生業とするプロフェッショナルの両雄が存在した。源斎は、飛田屋集団を率い戦国時代に大名の注文を受け各地で石垣積みを行った。このストーリーでは近江の安土城、大津城、京の伏見城が登場する。 三落は勿論国友鉄砲の製造・販売である。秀吉に攻められて鉄砲の巨大産地だった根来が壊滅した後は、国友が鉄砲生産量でトップとなっていた。
「互いに命に纏わる物作り」を行い、「三落はこれまで次々と新作の鉄砲を生みだし、源斎はそれに対抗する石垣を造ってきた。この二人で国友、穴太の技は百年進んだと言われるほど。世間では好敵手のように言われている」(p128)存在である。城の攻防戦では塞王源斎と砲仙三落はほぼ互角の状況だった。
このストーリー、「序」は、織田信長が朝倉の一乗谷に侵攻し、焼き払い、浅倉氏を滅亡させる時点から始まる。石積みの仕事でこの地に来ていた源斎が、この戦乱で孤児となる男の子・匡介を、一乗谷から脱出して穴太に連れて帰る。このとき匡介は気づいていなかったが、源斎は匡介が持つ石の声を聞き、姿を感じ取る天賦の才を発見していた。
第一章は、源斎が、匡介を己の後継ぎに指名した時点以降、つまり匡介が副頭となっている時点から始まっていく。飛田屋には源斎の親類に玲次がいて、飛田屋を継ぐ候補者でもあったのだが、彼は石の運搬をする荷方の小組頭になる。匡介と玲次の人間関係がこのストーリーの一つの要素となっていく。
一方、国友三落の許には、彦九郎という匡介より一つ年上の職人が早くも後継者となっていた。彦九郎もまた次々に鉄砲に工夫を加え新作を製造していた。
このストーリー、源斎と三落の好敵手関係を礎にして、世代が匡介と彦九郎へとバトンタッチされ、匡介と彦九郎がライバル関係となっていく。その移行期と移行後を描き出す。
移行期におけるストーリーの山場がまず描かれる。本能寺の変の直後において、蒲生親子の籠もる日野城における石積みを飛田屋源斎が請け負う。「懸(かかり)」と称する仕事を戦の直前から戦の最中に行うことになる。源斎と匡介が飛田屋集団を率いて行う石積みである。
そして、源斎が秀吉の要請を受け、伏見城の縄張りをすることになる。この時、匡介は源斎から大津城を任される。蛍大名と陰口される京極高次が治める湖上の城である。この外堀は空堀だったが、匡介が差配して水堀にするプロセスが描かれる。
この「懸」と「水堀化」がこのストーリー構成に読者を引きこんでいく導入的な山場となる。
関ヶ原の戦い、このエポック・メーキングとなる戦いはその関連事象としてさまざまな戦を多発している。ここでは、伏見城と大津城での戦に焦点が絞られていく。結果的には伏見城は落城し、大津城はからくもぎりぎりまで持ちこたえた後、高次が開城を決意した。だがこの二城での戦の経緯と期間が、間接的に関ヶ原での結果に重要な影響を及ぼしていたことになる。
伏見城で「懸」を請け負う源斎の視点からの伏見城の攻防戦が一つの山場として描かれる。ここには国友彦九郎が西軍に加担して攻める側となる。彦九郎の矛(鉄砲)と源斎の築く楯(石垣)との攻防戦である。
その先に、メインの山場が描き出されて行く。舞台は大津城。蛍大名京極高次の兵力は3000人規模である。一方、西軍は総大将毛利元康のもとに4万人軍勢となる。その中には、西国無双と称される立花宗茂と3000人の兵力が加わっていた。この大津城の攻防戦では、国友彦九郎は立花宗茂の許に加わる。
この大津城の攻防戦は、実質的に塞王とみなされる立場になった飛田屋匡介と国友彦九郎との攻防戦の側面が描き込まれていく。大津城に入り、「懸」として石積みを行う飛田屋集団がさまざまな工夫をする。そのプロセスがストーリーを盛り上げていく。そして、ファイナルステージは、立花宗茂の攻略戦とそれに対する防戦、そして大津城の天守を護る為に匡介が築く石積み(楯)と、国友彦九郎の製造した大筒「電破」(矛)との間での攻防戦が中心となっていく。
読者がこれらの攻防戦に自然と引きこまれていくことになり、感情移入していくことになるだろう。少なくとも私は感情移入しつつ読むことになった。
「序」と「終」の間は,9章立てに構成されている。単行本の総ページは552ページ。
「第七章 蛍と無双」が大津城での攻防戦の始まりとなる。それは p325 からである。216ページが第七章~第九章に当てられている。このストーリーは、匡介と彦九郎の戦いがメインの山場になっていくことがこの構成からでもわかる。
基礎的史実を踏まえた上でのフィクション化だ思うが、どのあたりからがフィクションなのだろうか。その点が私にはわからないが、時代小説としては大いに楽しめる。
穴太衆、国友衆と称される職人群は存在した。この小説で描かれる人々のモデルはいるだろうけれど、登場人物はたぶんフィクションだろう。京極高次と初は実在した人物だが、ここで描かれたキャラクターはどこからがフィクションだろうか。おもしろい設定になっている。その点、興味深い。立花宗茂のキャラクター設定も同様に私には興味深い。
最後に、この小説で印象深い箇所を引用しご紹介して終りたい。
*城の縄張りは重要な機密であるため、穴太衆は紙に一切の記録を残さず、全て頭の中に図面を引いて行う。そしてそれは同じ穴太衆であっても決して外に漏らさない。
積み方の技術も同様である。一子相伝、しかも全て口伝である。こうして穴太衆は技術の漏洩を防ぎ、依頼主の信用を勝ち取ってきた。 p52
*片やどんな城でも打ち破る至高の矛。片やどんな攻めも撥ね返す最高の楯。矛盾という言葉がこれほどしっくり当て嵌まることも少なかろう。
だがこの世に矛盾は存在しない。必ずどちらかに軍配が上がるのである。 p133
*それが時として自らの命を縮めることになろうとも、人は研鑽の道を歩むことを止めない。そう考えれば人が技を生み出しているのではなく、技という得体の知れぬものが、自らが世に出るために人に憑依して操っているかのように思える。 p141
*世に矛があるから戦が起こるのか、それを防ぐ楯があるから戦が起こるのか。いや、そのどちらも正しくなく、人が人である限り争いは絶えないのかもしれない。
だが、それを是とすれば人は人でなくなる。ならば矛と楯は何のために存在するのか。人の愚かさを示し、同じ過ちを起こさせぬためではないか。 p538
ご一読ありがとうございます。
補遺
穴太衆 :ウィキペディア
穴太衆積みの石垣 :「比叡山・びわ湖」
「穴太衆」伝説の石積み技を継ぐ末裔に立ちはだかる壁とは:「中川政七商店の読みもの」
第48回【歴史】「穴太衆(あのうしゅう)」ってよく聞くけど何をした人たちなの?
:「城びと」
国友 :ウィキペディア
国友鉄砲ミュージアム ホームページ
国友(歴史を陰で支えた隠れたる名工の里):「須賀谷温泉Blog」
京極高次 :ウィキペディア
京極高次 :「コトバンク」
初 ⇒ 常常院 :ウィキペディア
「意地」と「計算」から家康の東軍に味方したホタル大名「京極高次」(東軍)
江宮隆之 :「歴史人」
立花宗茂 :ウィキペディア
1.種子島銃(ポルトガル初伝銃) :「種子島 西之表市」
火縄銃(鉄砲)の種類 :「刀剣ワールド」
12. 林流抱大筒 :「シニアネット久留米」
一宮藩の大筒 千葉県教育委員会 :「千葉県」
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)