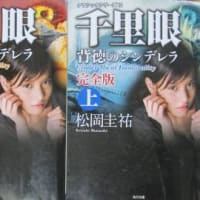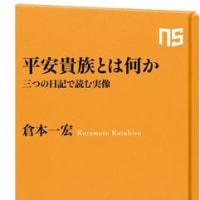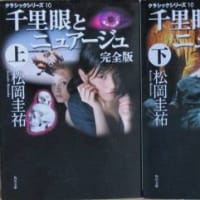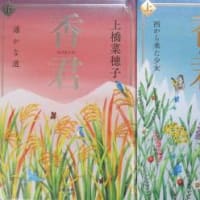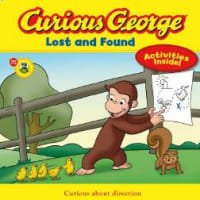新聞広告によれば、本書がこのシリーズの完結編となる。シリーズ第4弾。
本署は「小説すばる」(2024年3月号~2024年8月号)に連載された後、2024年11月に単行本が刊行された。
第1作の『破暁』は明治20年代半ばという時点から始まった。弔堂で「高遠の旦那さん」と呼ばれ、東京の外れで無為に過ごしていた高遠彬は、時が移り現在は、印刷造本改良會という団体の代表になっていた。巌谷小波が肝煎となり、博文館などの協力で創られた団体である。信州の山村から東京に出て来て、この印刷造本改良會に勤める甲野昇がこの完結編では主人公となる。甲野は高遠から鋳造活字の元になる字を書くという仕事を与えられた。
本書には、甲野を主人公とする形で、書楼弔堂終焉までの6短編が収録されている。
短編の構成形式はこれまでのスタイルを引き継いでいる。甲野に関わる様々な側面の話題から始まり、甲野が坂の上の茶店に立ち寄った後、書楼弔堂を訪れる。弔堂で主人や居合わせた客を交えた会話がストーリーの最終ステージになって行く。この時の客のほとんどが、その時代の著名人たちだった。その人物たちのプロフィールの一側面が鮮やかに点描されている。
この完結編の主な登場人物は、書楼弔堂の主人龍典と店員・撓の他には:
鶴田夫妻 現在、坂の上の茶店を営む。茶店に立ち寄る甲野との会話相手になる。
弥蔵 茶店の地所の所有者。この茶店に鶴田夫妻と家族同様に住む。第3作まで
は、この茶店の主人として登場していた人。
尾形 甲野の下宿先の向かいの部屋に住む下宿人。仏蘭西語の翻訳が生業。
石見の出身。甲野の部屋を訪れ、話し相手にし自説を論じ、助言する。
この完結編は、写本、木版印刷本、希少な輸入本が中心の時代から、鋳造活字の使用と活版印刷が始まり、大型輪転機が導入され、大量の書籍発行が可能となり、出版業界の体制が整いはじめてきた時代、つまり出版業界確立までの過渡期が終焉を迎える時代を背景としている。
弔堂の主人は、本の弔いを旨として、客にとっての一冊の本を紹介するという方針を貫いてきた。時代の先を読み、弔堂を閉じる選択をするに至る。その決断に至る経緯が、ここに収録された6つの短編連作である。
また、この6編は、東京に出てきた甲野の過去の人生を明らかにしていく連作にもなっている。尾形は己を語り、一方で甲野に彼の信州での人生を語らせる役回りを担っていく。
この完結編の構成は、本に絡むタイトル仕立てをベースにし、そこに甲野の人生の歩みを織り込んでもいると受け止めた。短編の最終段階に当時の著名人が弔堂の客として登場するのは凡そ従来通り。全体構成と登場する著名人をまずご紹介しよう。
探書拾玖 活字 夏目漱石
探書廿 複製 岡倉覚三(天心)
探書廿壱 蒐集 田中稲城
探書廿弐 永世 牧野富太郎
探書廿参 黎明 金田一京助
探書廿肆 誕生 天馬塔子
天馬塔子は『書楼弔堂 炎昼』で狂言回しの役割を担った才媛として登場していた人。
短編の末尾に著名人を登場させる一方で、著名人を描き込んだ最後に、短編の最後を「それもまたーーーーーーー本の中に記されていることでしょう」の一文で締めくくるところがおもしろい。
各編を、読後印象を含め簡単にご紹介しておきたい。
< 探書拾玖 活字 >
甲野は己に与えられた仕事である活字を起こすための字を書くのに役立つヒントあるいは資料が手に入ると高遠に言われて、書楼弔堂探しをするという顛末譚。
活字の意義と種類・働きなどが明らかにされる。
夏目漱石が教職を辞し、朝日新聞社に入社して再出発する日、将にその日に甲野は書楼弔堂で先客の漱石に遭った設定になっている。ここから、この完結編の始まりは明治40年(1907)とわかる。
< 探書廿 複製 >
尾形が甲野の部屋を訪れる。尾形は、大叔父が亡くなり大叔父が残した浮世絵の一部をもらった。尾形には関心もなくその価値もわからない。売りさばけないかと甲野に相談。甲野は弔堂の主人を思い浮かべる。
弔堂には先客として岡倉覚三が居た。浮世絵談義が始まるとともに、本物・複製・贋作論議へと発展する。浮世絵に関心を持つ読者には興味深く読めるた短編。
岡倉天心が『浮世絵概説』を構想しながら、完成に至らなかったということを、本書で知った。
「複製されたからこそ、・・・ 出会う機会が増える」 甲野の仕事との接点が浮かびあがる。
< 探書廿壱 蒐集 >
下宿の親爺は元浪花節語り。甲野と親爺の会話は、浪花節から浄瑠璃・落語・講談へと広がり、レコードの蒐集話に及んでいく。これが下敷きとなり、坂の上の茶店では鶴田の処分された雑誌への嘆き話につながる。弔堂に着くと、先客と主人との間に口論が起こっていた。後で、二人の客は競取(セド)り業者だという主人の推測を聞く。そこには古書の蒐集という問題が絡んでいた。そこにはもう一人の先客がいた。その客と協力して、本の片づけを手伝うことになる。その先客は、岩国の出身だと名乗る田中稲城だった。
田中稲城は、甲野の仕事を聞き、活字の大事さを語る。
< 探書廿弐 永世 >
甲野が描いた文字が活字に起こされ、それを順不同に組んだ文字の羅列を各種の紙に印刷した試し刷り。甲野の勤務先の事務所で、紙問屋の社長大木と同僚の田川が試し刷りされた紙の状態を確認しながら、論議をしていた。その中に甲野が巻き込まれていく。紙の種類、質の違いが生む印刷仕上がりの差異。本にとっての重要な要素が俎上にあがる。
高遠の注文していた本を甲野が受け取りに弔堂に行くことに。先客として、牧野富太郎が居た。そこで話題になるのが、本はいつまで保つかということだった。ここでも紙の質に戻っていく。甲野にとって、本そのものについて学ぶ場面になる。読者にとっても、本というもののベーシックな要素が論議の俎上にのぼっいるので、普段ほとんど意識しない側面を考える機会になる。
< 探書廿参 黎明 >
気分が優れない甲野の部屋に尾形が訪れる。甲野が抱く劣等感の無意味さを話題にした後で、甲野の郷里の向かいの住人が訪れた時の言伝を甲野に伝えた。だが、それは甲野の気持を一層滅入らせる。
翌朝早く、事務所に出た甲野は、高遠から弔堂が火災に遭ったらしいという噂を聞かされる。勿論甲野は弔堂に向かう。坂の上の茶店でまず鶴田から様子を聞く。このとき弔堂から戻って来た様子の男に話を聞く。彼はなぜか自分の決意も甲野に話した。その男は後に金田一京助と弔堂の主人から聞かされる。
火つけ行為は、気づいたのが早くて、軽度なものにとどめることができた。だが、それは弔堂の龍典に一つの決断をさせる契機となる。
この短編のタイトルは、金田一と龍典の二人の決意を象徴しているのだろうと思う。
< 探書廿肆 誕生 >
言伝を聞いても甲野は帰省をしなかった。心配する尾形は、甲野の部屋を訪れ、その真意を問い詰める、甲野は遂に信州での己の過去を語る。尾形は最後に言った。「貴君が思っているよりも、貴君のことを気にしている者は多いのだ。それは心得ておいた方がいいと思うぞ」と (p433)
甲野が事務所に出ると、高遠の来客を巌谷小波先生と紹介され、甲野は話に加わる。火災後の弔堂のことが話題となる。それを契機に、甲野はいつもの茶店に立ち寄った後、弔堂を訪れる。弔堂の状況の変化を知ることに。
さらにその後、思わぬ事態が重なっていく。
この短編のタイトルにはいくつかの事象の意味が重ねられていると感じる。
お読みいただき、その意味合いを感じていただきたいと思う。
末尾近くに記された次の箇所だけは触れておきたい。「僕・・・・・甲野昇は、相変わらず字を描いている」「・・・・遣り甲斐のある仕事だと思えるようにはなっている。僕の作った字が、組まれて活きて、読んだ人の中に何かを立ち上げることが出来たなら、それで満足だ」(p512)
最後に、読書について、有意義な指摘が各所に織り込まれている。いくつか引用しておこう。
*読まなくたって好いんだ。積んでおこうが並べておこうが、読めるようになっているならそれで好いのさ。読みたい時に読みたいものが読める・・・・それが何より大事なことだ。 p233
*現実を忘れて書を読み耽るのは無上の悦びですが、それは現実の代替えになるものではないのですわ。 p470
*読書は、人や、世の中を変えるものではないし、書物も人や世の中を変えるためにあるものではないんだ・・・・・・そうした変化は凡そこちら側で起きること・・・。 p475
*この世に無駄な本はない、本を無駄にする者がいるだけだ・・・・・。 p475
*本の中に時間なんてないんです。・・・・・好きに読めばいいんです。 p478
*何が書かれているかではなくて、読み方次第、ということだと思いますわ。 p477
ご一読ありがとうございます。
補遺
夏目漱石年譜 夏目漱石ライブラリ :「東北大学附属図書館」
大極宮 京極夏彦 公式ホームページ
京極夏彦作品人名辞典 ホームページ
田中稲城 :ウィキペディア
田中稲城 :「山口県の先人たち」
田中稲城文書 :「同志社大学図書館」
牧野富太郎 :「高知県立牧野植物園」
飯沼慾斎著「新訂草木図説」草部 :「文化遺産オンライン」
飯沼慾斎著「草木図説」草之部稿本附写生本 :「岐阜県」
牧野富太郎 :ウィキペディア
金田一京助 :ウィキペディア
金田一京助 :「盛岡市先人記念館」
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
こちらもお読みいただけるとうれしいです。
『姑獲鳥の夏』 講談社文庫
『書楼弔堂 炎昼』 集英社文庫
『書楼弔堂 破暁』 集英社文庫
『書楼弔堂 待宵』 集英社
[遊心逍遙記]に掲載 : 『ヒトごろし』 新潮社
本署は「小説すばる」(2024年3月号~2024年8月号)に連載された後、2024年11月に単行本が刊行された。
第1作の『破暁』は明治20年代半ばという時点から始まった。弔堂で「高遠の旦那さん」と呼ばれ、東京の外れで無為に過ごしていた高遠彬は、時が移り現在は、印刷造本改良會という団体の代表になっていた。巌谷小波が肝煎となり、博文館などの協力で創られた団体である。信州の山村から東京に出て来て、この印刷造本改良會に勤める甲野昇がこの完結編では主人公となる。甲野は高遠から鋳造活字の元になる字を書くという仕事を与えられた。
本書には、甲野を主人公とする形で、書楼弔堂終焉までの6短編が収録されている。
短編の構成形式はこれまでのスタイルを引き継いでいる。甲野に関わる様々な側面の話題から始まり、甲野が坂の上の茶店に立ち寄った後、書楼弔堂を訪れる。弔堂で主人や居合わせた客を交えた会話がストーリーの最終ステージになって行く。この時の客のほとんどが、その時代の著名人たちだった。その人物たちのプロフィールの一側面が鮮やかに点描されている。
この完結編の主な登場人物は、書楼弔堂の主人龍典と店員・撓の他には:
鶴田夫妻 現在、坂の上の茶店を営む。茶店に立ち寄る甲野との会話相手になる。
弥蔵 茶店の地所の所有者。この茶店に鶴田夫妻と家族同様に住む。第3作まで
は、この茶店の主人として登場していた人。
尾形 甲野の下宿先の向かいの部屋に住む下宿人。仏蘭西語の翻訳が生業。
石見の出身。甲野の部屋を訪れ、話し相手にし自説を論じ、助言する。
この完結編は、写本、木版印刷本、希少な輸入本が中心の時代から、鋳造活字の使用と活版印刷が始まり、大型輪転機が導入され、大量の書籍発行が可能となり、出版業界の体制が整いはじめてきた時代、つまり出版業界確立までの過渡期が終焉を迎える時代を背景としている。
弔堂の主人は、本の弔いを旨として、客にとっての一冊の本を紹介するという方針を貫いてきた。時代の先を読み、弔堂を閉じる選択をするに至る。その決断に至る経緯が、ここに収録された6つの短編連作である。
また、この6編は、東京に出てきた甲野の過去の人生を明らかにしていく連作にもなっている。尾形は己を語り、一方で甲野に彼の信州での人生を語らせる役回りを担っていく。
この完結編の構成は、本に絡むタイトル仕立てをベースにし、そこに甲野の人生の歩みを織り込んでもいると受け止めた。短編の最終段階に当時の著名人が弔堂の客として登場するのは凡そ従来通り。全体構成と登場する著名人をまずご紹介しよう。
探書拾玖 活字 夏目漱石
探書廿 複製 岡倉覚三(天心)
探書廿壱 蒐集 田中稲城
探書廿弐 永世 牧野富太郎
探書廿参 黎明 金田一京助
探書廿肆 誕生 天馬塔子
天馬塔子は『書楼弔堂 炎昼』で狂言回しの役割を担った才媛として登場していた人。
短編の末尾に著名人を登場させる一方で、著名人を描き込んだ最後に、短編の最後を「それもまたーーーーーーー本の中に記されていることでしょう」の一文で締めくくるところがおもしろい。
各編を、読後印象を含め簡単にご紹介しておきたい。
< 探書拾玖 活字 >
甲野は己に与えられた仕事である活字を起こすための字を書くのに役立つヒントあるいは資料が手に入ると高遠に言われて、書楼弔堂探しをするという顛末譚。
活字の意義と種類・働きなどが明らかにされる。
夏目漱石が教職を辞し、朝日新聞社に入社して再出発する日、将にその日に甲野は書楼弔堂で先客の漱石に遭った設定になっている。ここから、この完結編の始まりは明治40年(1907)とわかる。
< 探書廿 複製 >
尾形が甲野の部屋を訪れる。尾形は、大叔父が亡くなり大叔父が残した浮世絵の一部をもらった。尾形には関心もなくその価値もわからない。売りさばけないかと甲野に相談。甲野は弔堂の主人を思い浮かべる。
弔堂には先客として岡倉覚三が居た。浮世絵談義が始まるとともに、本物・複製・贋作論議へと発展する。浮世絵に関心を持つ読者には興味深く読めるた短編。
岡倉天心が『浮世絵概説』を構想しながら、完成に至らなかったということを、本書で知った。
「複製されたからこそ、・・・ 出会う機会が増える」 甲野の仕事との接点が浮かびあがる。
< 探書廿壱 蒐集 >
下宿の親爺は元浪花節語り。甲野と親爺の会話は、浪花節から浄瑠璃・落語・講談へと広がり、レコードの蒐集話に及んでいく。これが下敷きとなり、坂の上の茶店では鶴田の処分された雑誌への嘆き話につながる。弔堂に着くと、先客と主人との間に口論が起こっていた。後で、二人の客は競取(セド)り業者だという主人の推測を聞く。そこには古書の蒐集という問題が絡んでいた。そこにはもう一人の先客がいた。その客と協力して、本の片づけを手伝うことになる。その先客は、岩国の出身だと名乗る田中稲城だった。
田中稲城は、甲野の仕事を聞き、活字の大事さを語る。
< 探書廿弐 永世 >
甲野が描いた文字が活字に起こされ、それを順不同に組んだ文字の羅列を各種の紙に印刷した試し刷り。甲野の勤務先の事務所で、紙問屋の社長大木と同僚の田川が試し刷りされた紙の状態を確認しながら、論議をしていた。その中に甲野が巻き込まれていく。紙の種類、質の違いが生む印刷仕上がりの差異。本にとっての重要な要素が俎上にあがる。
高遠の注文していた本を甲野が受け取りに弔堂に行くことに。先客として、牧野富太郎が居た。そこで話題になるのが、本はいつまで保つかということだった。ここでも紙の質に戻っていく。甲野にとって、本そのものについて学ぶ場面になる。読者にとっても、本というもののベーシックな要素が論議の俎上にのぼっいるので、普段ほとんど意識しない側面を考える機会になる。
< 探書廿参 黎明 >
気分が優れない甲野の部屋に尾形が訪れる。甲野が抱く劣等感の無意味さを話題にした後で、甲野の郷里の向かいの住人が訪れた時の言伝を甲野に伝えた。だが、それは甲野の気持を一層滅入らせる。
翌朝早く、事務所に出た甲野は、高遠から弔堂が火災に遭ったらしいという噂を聞かされる。勿論甲野は弔堂に向かう。坂の上の茶店でまず鶴田から様子を聞く。このとき弔堂から戻って来た様子の男に話を聞く。彼はなぜか自分の決意も甲野に話した。その男は後に金田一京助と弔堂の主人から聞かされる。
火つけ行為は、気づいたのが早くて、軽度なものにとどめることができた。だが、それは弔堂の龍典に一つの決断をさせる契機となる。
この短編のタイトルは、金田一と龍典の二人の決意を象徴しているのだろうと思う。
< 探書廿肆 誕生 >
言伝を聞いても甲野は帰省をしなかった。心配する尾形は、甲野の部屋を訪れ、その真意を問い詰める、甲野は遂に信州での己の過去を語る。尾形は最後に言った。「貴君が思っているよりも、貴君のことを気にしている者は多いのだ。それは心得ておいた方がいいと思うぞ」と (p433)
甲野が事務所に出ると、高遠の来客を巌谷小波先生と紹介され、甲野は話に加わる。火災後の弔堂のことが話題となる。それを契機に、甲野はいつもの茶店に立ち寄った後、弔堂を訪れる。弔堂の状況の変化を知ることに。
さらにその後、思わぬ事態が重なっていく。
この短編のタイトルにはいくつかの事象の意味が重ねられていると感じる。
お読みいただき、その意味合いを感じていただきたいと思う。
末尾近くに記された次の箇所だけは触れておきたい。「僕・・・・・甲野昇は、相変わらず字を描いている」「・・・・遣り甲斐のある仕事だと思えるようにはなっている。僕の作った字が、組まれて活きて、読んだ人の中に何かを立ち上げることが出来たなら、それで満足だ」(p512)
最後に、読書について、有意義な指摘が各所に織り込まれている。いくつか引用しておこう。
*読まなくたって好いんだ。積んでおこうが並べておこうが、読めるようになっているならそれで好いのさ。読みたい時に読みたいものが読める・・・・それが何より大事なことだ。 p233
*現実を忘れて書を読み耽るのは無上の悦びですが、それは現実の代替えになるものではないのですわ。 p470
*読書は、人や、世の中を変えるものではないし、書物も人や世の中を変えるためにあるものではないんだ・・・・・・そうした変化は凡そこちら側で起きること・・・。 p475
*この世に無駄な本はない、本を無駄にする者がいるだけだ・・・・・。 p475
*本の中に時間なんてないんです。・・・・・好きに読めばいいんです。 p478
*何が書かれているかではなくて、読み方次第、ということだと思いますわ。 p477
ご一読ありがとうございます。
補遺
夏目漱石年譜 夏目漱石ライブラリ :「東北大学附属図書館」
大極宮 京極夏彦 公式ホームページ
京極夏彦作品人名辞典 ホームページ
田中稲城 :ウィキペディア
田中稲城 :「山口県の先人たち」
田中稲城文書 :「同志社大学図書館」
牧野富太郎 :「高知県立牧野植物園」
飯沼慾斎著「新訂草木図説」草部 :「文化遺産オンライン」
飯沼慾斎著「草木図説」草之部稿本附写生本 :「岐阜県」
牧野富太郎 :ウィキペディア
金田一京助 :ウィキペディア
金田一京助 :「盛岡市先人記念館」
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
こちらもお読みいただけるとうれしいです。
『姑獲鳥の夏』 講談社文庫
『書楼弔堂 炎昼』 集英社文庫
『書楼弔堂 破暁』 集英社文庫
『書楼弔堂 待宵』 集英社
[遊心逍遙記]に掲載 : 『ヒトごろし』 新潮社