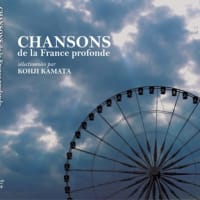晴れ渡った初夏の一日、三宅坂の国立劇場へ。恒例の前進座5月公演であります。この公演、1年おきに古典と新作をやるのだが、今年は新作の番で『裏長屋騒動記』という落語ネタのコメディ。堅苦しいドラマじゃなくて助かった。
実をいうと、新作歌舞伎がオレは苦手である。特に明治大正期に盛んに作られたヤツは、西洋心理劇の手法を採り入れて、脱論理的な古典のおおらかなエンタメ性を窒息させてしまっている。一昨年上演された真山青果の『元禄忠臣蔵』なんか、そう言っちゃナンだが、退屈がカミシモつけて歩いてるみたいだった。
作者の山田洋次監督は、第2次大戦前に前進座の出演で制作された山中貞雄の『人情紙風船』が念頭にあったんじゃないかと思う。お通夜の名目で因業大家から酒肴をせしめるエピソードは、多分あの名作からの引用だ。
主演の嵐芳三郎は、ふだん白塗りの二枚目役者だが、貧しく気のいい中年の屑拾いをまずは無難に演じていた。武士と浪人の、カネを受け取れ受け取れぬの板挟みに遭い、大金を持って両者のあいだを往ったり来たりする役。ついには耐えきれなくなって役目を降りる。
お武家様は意地を張ってればいいが、貧しい我々は50両もの大金を持たされれば、このまま持ち逃げしようかと悪い心を起こす。しかしそうすれば、いずれ捕まって晒し首。どうかもう巻き添えにはしないでおくんなさい、云々。
庶民の精一杯のタンカを芳三郎が力みなく、持ち前の爽やかな声でサラリと演じたのがよかった。メンツに生きる武士とその日暮らしの町民との対比に、庶民派・山田監督の心意気を見た。ドラマの勘所だ。
中盤、店子が大家を脅そうと屋敷に押しかけて死人にかんかんのうを踊らせる。派手な見せ場だが、ドラマの文脈では、大家がそれほど因業には見えないのが少々困った点。
死人というのが長屋じゅうの鼻つまみだったヤクザで、長屋に来て以来、店賃を一度も払ったことがない乱暴者である。道で出会った大家から力ずくで下駄を巻き上げたりもする。大家はむしろ、被害者だ。
大詰め、名女形の国太郎扮するバカ殿がデウス・エクス・マキナ然と登場して、もつれた筋にあっさりケリをつけるが、マンガ的な誇張が過ぎて、やや浮いていた。
このように突っ込みどころがないわけじゃないのだが、国立劇場に笑いが渦巻いたのは初めて経験した。
ところで、トシ寄りの観客マナーって年々悪くなるね。柝が入り、幕が開き、下座音楽が鳴り出しても、遠い海鳴りのような私語の騒音がダラダラ消えない。女性陣ばかりではなく白髪のジイさんまでがペチャクチャしゃべり散らしている。年齢層の若い四季の客席が、開幕と同時にピタッと鎮まるのと対照的だ。
オレ自身トシ寄りだから遠慮なく言わせてもらうが、老人は保育園の設置計画が持ち上がったりすると、幼児の声がうるさいといって真っ先に反対する。そのクセ、自分が人に掛ける迷惑には一向に頓着しない。多分、想像力が衰えているせいだろうが、いい加減にして欲しいよ。