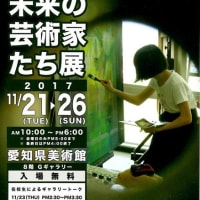名古屋市南東部の街で見つけたヤマユリやアケビといった里山の名残を紹介する記事を先日(9月17日)掲載しましたが、実はもう一つ、正体が分からずに記述しなかった植物がありました。
ここに掲載した写真の植物についてです。
細い道端の雑木の間から顔を覗かせる大きな熊手状の葉。枝はなく茶色のボロ布みたいな網で覆われた幹が真っすぐ伸びています。樹高6~7㍍、中には10㍍もあろうかと思われるのも。ツタが幾重にも絡みついて野生化しているようです。
歩きながら柵で囲まれた竹林や雑木の奥を覗くと、10本や20本ではありません。種子から生えたのか2~3㍍の若木もあります。
「ヤシ?まさか・・・」。こんなところに熱帯のヤシが自然にあったとは思えません。過去にヤシの庭樹で屋敷を囲むような庄屋でも住んでいたのだろうか。結局、分からないまま宿題にしておいたのです。
その謎が、1週間後の9月24日朝、NHKテレビBSⅢの「ニッポンの里山」を見ていて解けました。正体はヤシ科の「シュロ」のようです。熱帯のヤシのような大きな実は付けまませんが、外見は当然ながら似ています。
テレビでは和歌山県有田川町の山村の暮らしを紹介。ここでは古くからシュロを家の周りに植え、シュロの葉柄の下部を包んでいるような網状の繊維質の樹皮をはぎ取り、生活用品を作ってきました。
たわし、ほうき、敷物、シュロ縄・・・。今では輸入に押されているようですが、有田川町では現在も受け継がれているようです。
シュロは有田川町だけでなく国内のあちこちで植えられ、今も人気の「亀の子たわし」も作られていたのでしょう。
改めて現地に行ってみると、回りには養蚕用の桑の古木や、かつては嫁ぐ娘に持たせるタンスやゲタの素材として家ごとに1本はあった桐らしい古木も見えます。
雑木林の多くが消え、マンションが建ち並ぶ名古屋市南東部ですが、蚕を育て、シュロを植える農家の暮らしがたくさんあったのですね。
そうそう、先日は1個しか見つけられなかったアケビを、今回の再探検でも1本の蔓を発見、3個の実を確認できました。でも、1本の蔓にいくつもの実をつけた風景は昔話になってしまったようです。