松永史談会1月例会は休会。その代わりに松永西町を取り上げた「入江屋石井家の人々の近代」を配布します。

2頁(差し替え版)



石井得雄の弟石井賚三(1886-1932)は朝日新聞記者(名古屋支局長)を辞して実業家へと転身を計るが、大成はしなかった。福山学生会雑誌は石井賚三の追悼記事を掲載していた。この中に賚三(通称”らい”ちゃん)の手記も掲載。

2頁(差し替え版)



石井得雄の弟石井賚三(1886-1932)は朝日新聞記者(名古屋支局長)を辞して実業家へと転身を計るが、大成はしなかった。福山学生会雑誌は石井賚三の追悼記事を掲載していた。この中に賚三(通称”らい”ちゃん)の手記も掲載。
天保5年備後国国絵図の中の「つるぎの宮」
沼隈郡内では九州往還沿いの「つるぎの宮」・伊勢山、明王院、そして瀬戸内航路(山陽沿岸を通る地乗り航路)に沿った阿伏兎観音、鞆の番所・古城跡・鞆の観音堂そして鞆町あたりの無人の島々など。街道沿いの河川については船渡・歩行渡など渡河事情が詳細に注記されている。今津一里塚と鞆街道の表現はやや地図的なディフォルメが著しい。
鞆町及び後地一帯は大きく誇張されている。
鞆の番所は記載されても芸藩と福山藩との藩領境にあった防地の番所は無記載。わたしが注記した「川尻」(藤井川河岸)辺りに図示されている一里塚は今津一里塚同様、場所がかなりずれている高須のそれ。
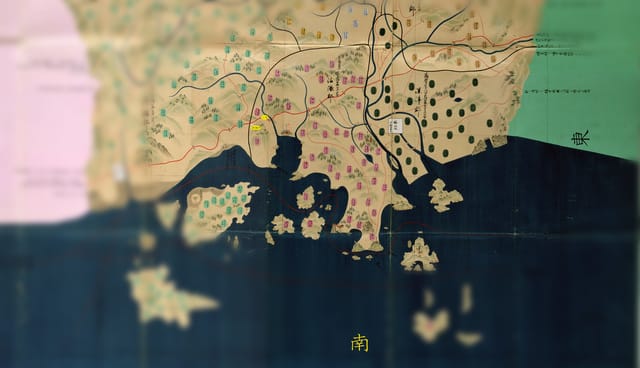
国立公文書館デジタルアーカイブ
公開されている内容:
元禄国絵図
元禄郷帳
天保国絵図
天保郷帳
正保城絵図
jpeg2000でDLすると2.8Gバイトくらいの巨大なファイルになる。高精細だが、高性能のPCでないと扱いにくいかもしれない。
備後国郷帳

備後国国絵図は天保図のみ公開。馬屋原重帯『西備名区』を編纂した馬屋原が書き写した国絵図はこの元禄国絵図だったようだ(簡易チェック済)。

寛永の備後国絵図では神村は「賀村」(かむら)と表記している、発音は「かむら」だろう。
九州往還は吉和―尾道―高須ーそのまま山手方面に。今津は記載なし。
沼隈郡内では九州往還沿いの「つるぎの宮」・伊勢山、明王院、そして瀬戸内航路(山陽沿岸を通る地乗り航路)に沿った阿伏兎観音、鞆の番所・古城跡・鞆の観音堂そして鞆町あたりの無人の島々など。街道沿いの河川については船渡・歩行渡など渡河事情が詳細に注記されている。今津一里塚と鞆街道の表現はやや地図的なディフォルメが著しい。
鞆町及び後地一帯は大きく誇張されている。
鞆の番所は記載されても芸藩と福山藩との藩領境にあった防地の番所は無記載。わたしが注記した「川尻」(藤井川河岸)辺りに図示されている一里塚は今津一里塚同様、場所がかなりずれている高須のそれ。
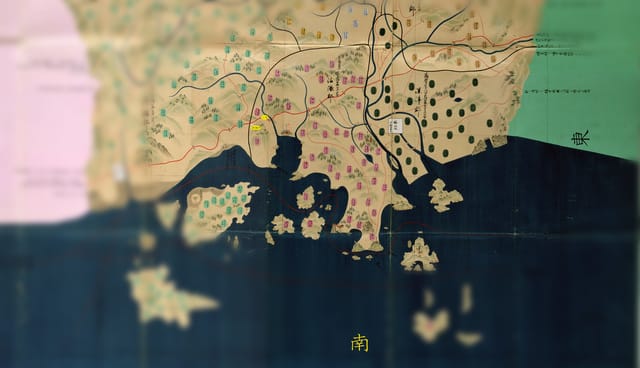
国立公文書館デジタルアーカイブ
公開されている内容:
元禄国絵図
元禄郷帳
天保国絵図
天保郷帳
正保城絵図
jpeg2000でDLすると2.8Gバイトくらいの巨大なファイルになる。高精細だが、高性能のPCでないと扱いにくいかもしれない。
備後国郷帳

備後国国絵図は天保図のみ公開。馬屋原重帯『西備名区』を編纂した馬屋原が書き写した国絵図はこの元禄国絵図だったようだ(簡易チェック済)。

寛永の備後国絵図では神村は「賀村」(かむら)と表記している、発音は「かむら」だろう。
九州往還は吉和―尾道―高須ーそのまま山手方面に。今津は記載なし。

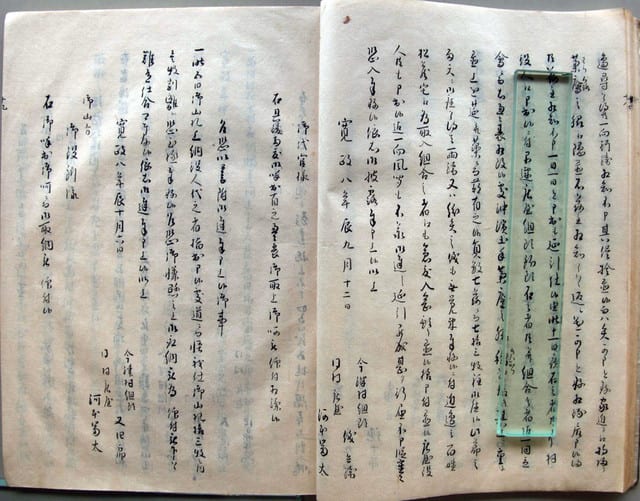
寛政8年8月6日夜、夜間魚取りのため本郷川(土手)を下っていたところ松永方面から川を渡ってくる不審者たちと遭遇。忠右衛門・留八が𠮟責したところ、かれらは前新涯角土手に備後表7荷を残したまま逃走したという話だ。
備後表の抜け荷は絶えなかったようだが、おそらく舟でやってくる尾道の商人に密売するために備後表をひそかに前新涯角土手に置いていたのだろう。
前新涯角の地先には幕末・明治期にかけて通称「三角」(末広新涯)が造成され寛政期の景観は一変したがこのあたりは備後表7荷積み出す舟の着舟可能な場所であった訳だ。
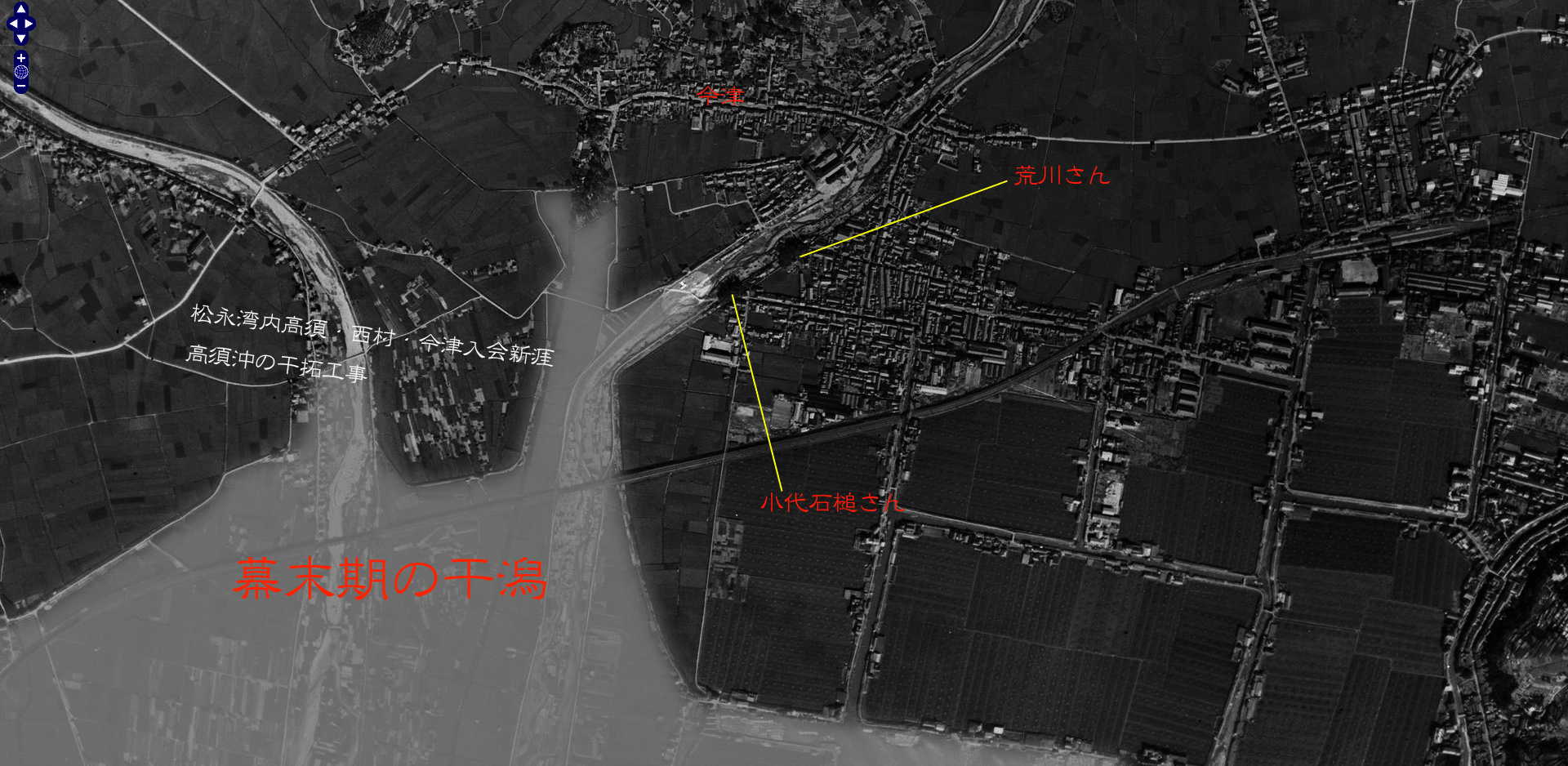
頼山陽が辿った尾道―今津間の航路。矢印アニメは舟の動き。

寛政9年当時でも九州往還の川尻(藤井川デルタ地帯)付近で通行不能になることがったらしく、その場合は険しい迂回路を避け、尾道ー今津間を舟で行き来することがあったらしいことがわかる。


































