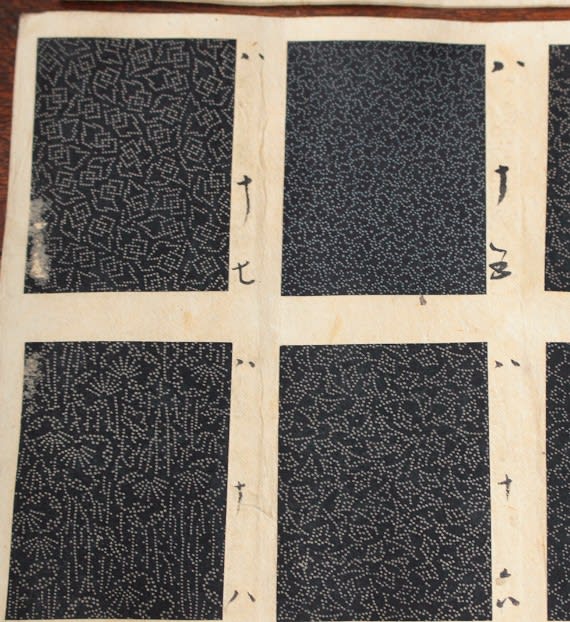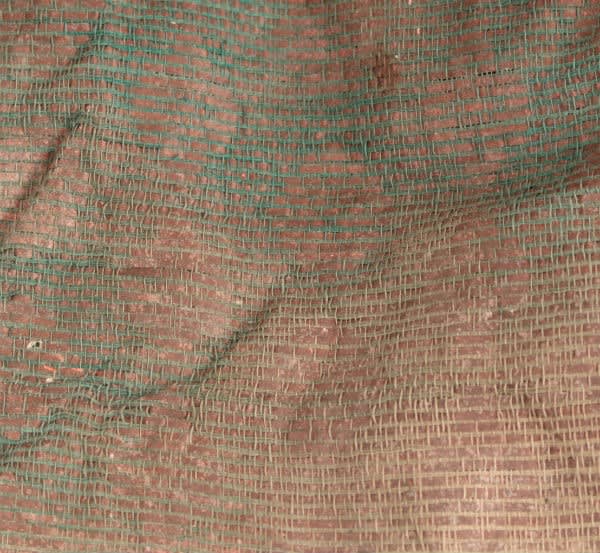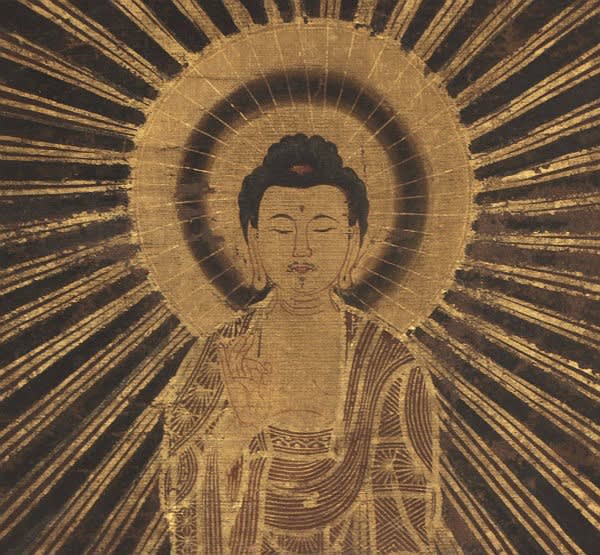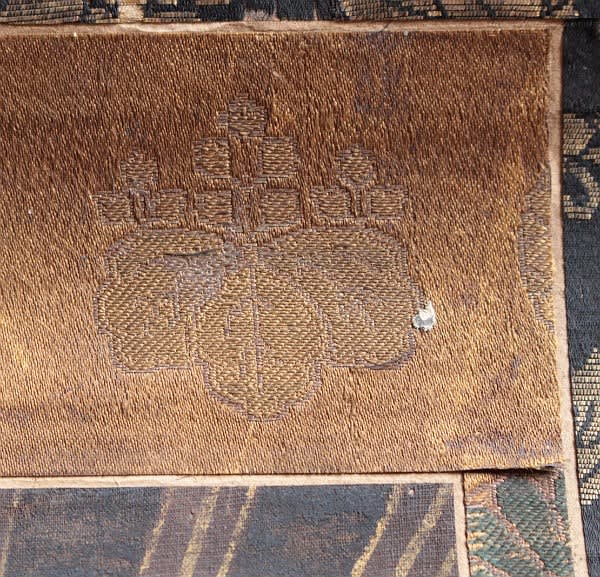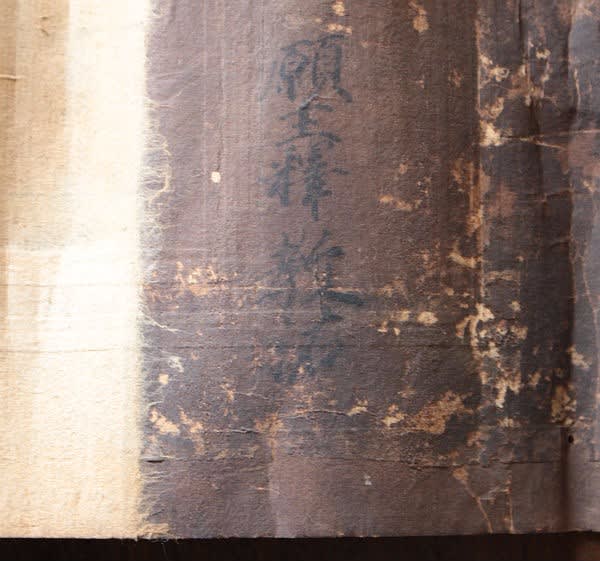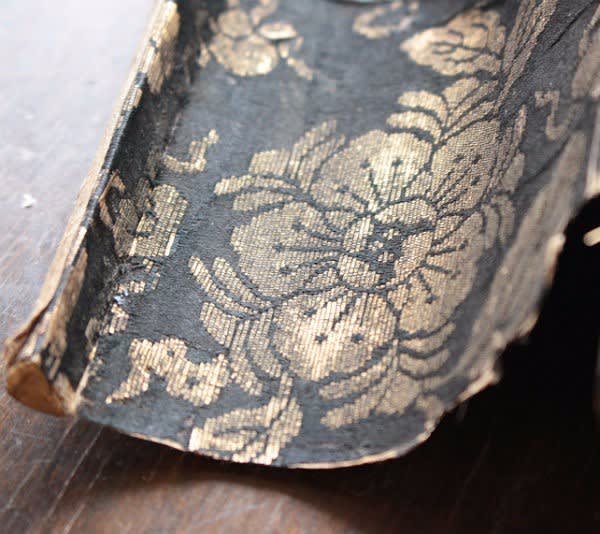インド更紗 南蛮短刀鞘
19世紀ころのインド更紗です。
おそらく南蛮の短刀用のものだと思いますが、
鞘に仕立てられたものです。
古いものですので、裂自体にリキはなく、
分解して再利用することはおそらく不可能ですので、
ご承知置きください。
長さ 約26.5センチ前後
幅 約4.5センチ前後(真ん中付近)
厚み 約1.5センチ前後
画像の通り、破れ等あります。
実物と画像とでは多少色合いが異なる場合があります。
古いものですので、画像と説明文にない傷等ある場合があります。
サイズは前後と記載の通り、誤差を含みます。
時代産地は当方見解です。