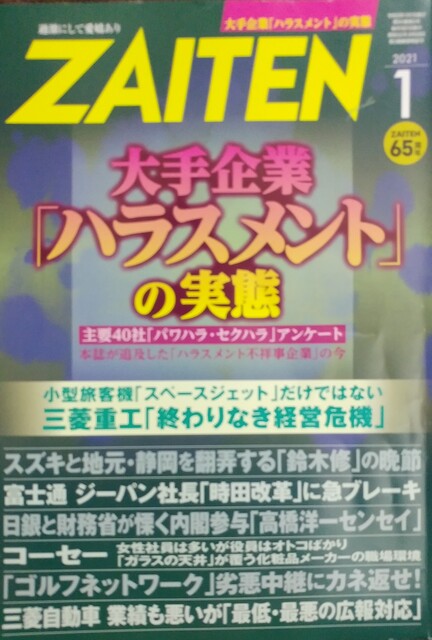近年、美術業界でセクハラや性被害を訴える声が上がっている。美術作家にはフリーランスで活動する人が多く、地位や権力が上の人による嫌がらせから守られにくい。また、作家の卵である美大生が受ける被害も深⇒続きはコチラ・・・・
実際に、著者が勤務していた大学では、正規社員はまったく仕事をせず(事務室で、1人で歌を唱いながらダンスをしていた)、もっぱら正規社員よりもはるかに低い賃金の非正規社員が仕事をこなしていた。
ところがある日、急にその非正規社員が雇用契約を一方的に破棄された。労働法を知らない著者はこの解雇の理由が分からず、びっくりした。
当時はまだ、パート、アルバイト、派遣、契約社員などの有期労働契約で働く人が、同じ会社で雇用契約を繰り返して契約期間が5年を超えると、契約期間中に次の契約時に無期労働契約への転換を求めることができるという「無期転換ルール」(2013年4月の「労働契約法」の改正に基づき18年4月から適用開始)は存在しなかった。
しかし、労働法の専門家によると、事実上、パート契約を更新し続けると契約解除が難しくなるという話であった。おそらく、そうした事実上の契約解除の困難さが、そのときの解雇の理由ではなかったかと⇒続きはコチラ・・・・FLASH
ところがある日、急にその非正規社員が雇用契約を一方的に破棄された。労働法を知らない著者はこの解雇の理由が分からず、びっくりした。
当時はまだ、パート、アルバイト、派遣、契約社員などの有期労働契約で働く人が、同じ会社で雇用契約を繰り返して契約期間が5年を超えると、契約期間中に次の契約時に無期労働契約への転換を求めることができるという「無期転換ルール」(2013年4月の「労働契約法」の改正に基づき18年4月から適用開始)は存在しなかった。
しかし、労働法の専門家によると、事実上、パート契約を更新し続けると契約解除が難しくなるという話であった。おそらく、そうした事実上の契約解除の困難さが、そのときの解雇の理由ではなかったかと⇒続きはコチラ・・・・FLASH
長崎造船所が創業した明治期からの前史にはじまり、終戦直後の組合結成や65年の組合分裂を経て、労働者の命と権利を守る闘いを全7部に分けて執筆。職場新聞などを収めた資料編も充実させた。
編さん委員の藤原春光さん(82)は▽臨時工廃止と常時雇用制度の実現▽じん肺救済訴訟と補償制度の獲得▽組合分裂後の賃金差別や労働環境の改善要求▽過労問題の支援-を長船分会の功績に挙げ、「職場の要求をどう実現するか、という思いで続けてきた」と振り返る。
分裂前、約1万2300人だった組合員は65年、約3千人が長船分会に残ったが、労使協調路線を目指した組合員は別の組合を設立⇒続きはコチラ・・・・
**********************************
闘わない労働組合は存在価値が無いですね。
組合費を吸い上げるだけの、何かの懇親会です。
収めてきたカネは何処へ消えているのやら。
編さん委員の藤原春光さん(82)は▽臨時工廃止と常時雇用制度の実現▽じん肺救済訴訟と補償制度の獲得▽組合分裂後の賃金差別や労働環境の改善要求▽過労問題の支援-を長船分会の功績に挙げ、「職場の要求をどう実現するか、という思いで続けてきた」と振り返る。
分裂前、約1万2300人だった組合員は65年、約3千人が長船分会に残ったが、労使協調路線を目指した組合員は別の組合を設立⇒続きはコチラ・・・・
**********************************
闘わない労働組合は存在価値が無いですね。
組合費を吸い上げるだけの、何かの懇親会です。
収めてきたカネは何処へ消えているのやら。
国家公務員とは
公務員と一口にいっても職種は様々ですが、大きく2つに分けられます。
「国家公務員」と「地方公務員」です。
現在日本の公務員の数は国家公務員が58.5万人、地方公務員が274.2万人となっています。
国家公務員は国の業務に従事する職員のこととなっており、特別職と一般職に分かれます。この中で、給与法が適用される一般職の国家公務員は27.7万人となっています。
ではこの一般職の国家公務員が支給される退職金について詳しく⇒続きはコチラ・・・・
公務員と一口にいっても職種は様々ですが、大きく2つに分けられます。
「国家公務員」と「地方公務員」です。
現在日本の公務員の数は国家公務員が58.5万人、地方公務員が274.2万人となっています。
国家公務員は国の業務に従事する職員のこととなっており、特別職と一般職に分かれます。この中で、給与法が適用される一般職の国家公務員は27.7万人となっています。
ではこの一般職の国家公務員が支給される退職金について詳しく⇒続きはコチラ・・・・
Aさんは今の職場で定年後も継続雇用してもらえそうですが、今のところ妻は継続雇用を希望しておらず、定年後をどう過ごすか検討中なのだそう。定年後、いかに長く収入を得るかが老後のやりくりに与える影響は大きいので、ここは慎重に検討したほうがよさそうです。⇒続きはコチラ・・・・