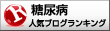進むIoT研究…生活習慣病は激減へ?
少子高齢化で医療費はますます増大する。そうした中、経済産業省は、民間投資の活性化により、IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)などの技術革新を最大限に取り入れ、医療の質を高めるイノベーションを実現しようと取り組んでいる。
たとえば、2型糖尿病患者が、体重計や歩数計などでデータをスマートフォンのアプリにアップし、セルフモニタリングで健康管理に役立てる。自己流の食生活の改善ではなく、医師や保健師などからのアドバイスを受け、生活習慣の正しい行動変容へと導くのが狙いだ。その個人データを血液検査などの臨床研究データと統合し、さらに、健康情報を収集してデータを蓄積することで、新たなヘルスケア産業の創出などにもつなげていきたいようだ。
「米国では、服薬情報もスマートフォンでわかるようになっています。患者さんの個人データと医療機関の電子カルテなど、今はバラバラなデータを統合できるようにすると、患者さんの健康管理に役立ち、医療の質の向上につながると思います」
こう話すのは、国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センターの植木浩二郎センター長。IoTの大規模臨床試験や、診療録直結型全国糖尿病データベース事業(J-DREAMS)の研究代表を務める。
すでに日本でも、処方された薬の情報(お薬手帳)が、スマホのアプリに入るシステムを導入しているドラッグストアもある。ただし、患者が毎日きちんと薬を服用したかどうかは現状ではわからない。
植木医師によれば、米国では薬の容器とスマホのアプリを連動させ、患者が薬を飲むために容器を開けた情報が自動的にアプリに入力されるようになっているものも存在する。患者自身もアプリ情報を確認することで、薬の飲み忘れの防止や「飲んだかどうか記憶にない」といったときにも対処が可能になる。
「服用時間もアラームで知らせてくれるようになると、飲み忘れは防げると思います。もちろん、このような服用情報のアプリが役立つかどうか、事前にきちんと臨床研究で有効性は確かめなければなりませんが」
IoTは便利だが、有効性が確かめられないと医療ツールとしての使用に制限がかかり、患者データとの融合なども進まない。また、有効性がわかっても、データを共有するためのアプリの開発、個人情報に関する新たなセキュリティーシステムの構築も必要になるだろう。今もスマホの中には、たくさんのアプリがあるが、医療用としての進展にはまだもう少し時間がかかりそうだ。
「2008年に始まった特定健診・特定保健指導で、国民の健康意識は高まり、2型糖尿病の予備群や新たに糖尿病になる人は減りました。合併症で亡くなる人も減っています。その健康意識をさらに高めるために、IoTなどのシステム活用が役立つと考えています」
間違った生活習慣などは、医師や保健師などの的確な指導で改善は可能だ。IoTのアプリが、モチベーションも上げてくれれば継続もしやすいだろう。加えて、医師も自動ガイダンスやデータベースにより、患者の状態に合わせた治療や指導を行いやすくなる。IoTやAIなどの研究が進むと、近い将来、生活習慣病を新たに発症する患者は激減するかもしれない。(安達純子)
https://www.zakzak.co.jp/lif/news/191130/hea1911300001-n1.html
そして個人情報が・・・・・・(´・ω・`) まぁ、それより病気優先で。本当に。

今朝の血糖値です。90(mg/dl)です。問題ないですね。薬物もよく効いて。(´・ω・`)
TKJ(糖尿病降下剤ジャヌビア)薄ピンクの錠剤。健常者には違法薬物。
うっへっへっへーーーーーーーーーーー。
また更新します。皆様もご自愛ください。
パソコンの売れ行きが好調だそうで(´・ω・`)スマホ疲れが原因だそうで。
ちょっと違う気がしますが。ただ単に。。。。