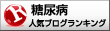◇ガイドラインから逸脱 都が医療法に基づき立ち入り検査
外科医は「透析治療を受けない権利を患者に認めるべきだ」と話している。病院側によると、女性は受診前に約5年間、近くの診療所で透析治療を受けていた。血液浄化用の針を入れる血管の分路が詰まったため、昨年8月9日、病院の腎臓病総合医療センターを訪れた。外科医は首周辺に管を挿入する治療法と併せ、「死に直結する」という説明とともに透析をやめる選択肢を提示。女性は「透析は、もういや」と中止を選んだ。外科医は夫(51)を呼んで看護師同席で念押しし、女性が意思確認書に署名。治療は中止された。
センターの腎臓内科医(55)によると、さらに女性は「透析をしない。最後は福生病院でお願いしたい」と内科医に伝え、「息が苦しい」と14日に入院。
ところが夫によると、15日になって女性が「透析中止を撤回する」と話したため、夫は治療再開を外科医に求めた。外科医によると、「こんなに苦しいのであれば、また透析をしようかな」という発言を女性から数回聞いたが、苦痛を和らげる治療を実施した。女性は16日午後5時過ぎに死亡した。
外科医は「正気な時の(治療中止という女性の)固い意思に重きを置いた」と説明。中止しなければ女性は約4年間生きられた可能性があったという。
外科医は「十分な意思確認がないまま透析治療が導入され、無益で偏った延命措置で患者が苦しんでいる。治療を受けない権利を認めるべきだ」と主張している。
日本透析医学会が2014年に発表したガイドラインは透析治療中止の基準について「患者の全身状態が極めて不良」「患者の生命を損なう」場合に限定。
専門医で作る日本透析医会の宍戸寛治・専務理事は「(患者の)自殺を誘導している。医師の倫理に反し、医療とは無関係な行為だ」と批判している。
外科医は女性について「終末期だ」と主張しているが、昨年3月改定の厚生労働省の終末期向けガイドラインは医療従事者に対し、医学的妥当性を基に医療の中止を慎重に判断し、患者の意思の変化を認めるよう求めている。
東京都医療安全課の話 生命尊重と個人の尊厳保持という医療法の理念通りに病院が適正に管理されているかを確認している。
厚労省地域医療計画課の話 一連の行為は国のガイドラインから外れ、現在の医療水準や一般社会の認識からも懸け離れている。【斎藤義彦】
◇人工透析治療
人工膜や腹膜を使い、血液中の老廃物や毒素、水を除く治療法。人工膜を使った血液透析では通常、週3回で各4時間、腕の血管を透析器につないで血液を浄化する。腎臓が機能しない腎不全に有効で、長期生存が可能になる。
1950年代に実用化され、国内では67年に健康保険の適用になった。72年からは更生医療(現・自立支援医療)により自己負担が軽減され、広く普及している。患者らでつくる全国腎臓病協議会によると、薬や機器の進歩で患者負担が軽減され、大多数は苦痛なく治療を受けている。ただ、疲れが出て腰が痛くなったり、針を刺す痛みを強く感じたりする人も一部にいるという。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190307-00000004-mai-soci
人工透析約40年。手首のシャントが詰まる。外科的手術。「首の頸動脈」からの人工透析可能。

中止しなければ女性は約4年間生きられた可能性があったという。
延命治療をすべき???中止すべき???
全国2050万人の糖尿病患者さん及びその予備群さん!

糖尿病性腎症とは、
糖尿病性腎症(Diabetic Nephropathy)
糖尿病性腎症は、糖尿病の細小血管合併症(腎症、網膜症、末梢神経障害)の1つです。
1998年以降、血液透析導入の原因疾患として増加の一途を辿っていましたが、近年ではその傾向は段々鈍ってきています。しかし、依然として血液透析導入の原因疾患の第1位(約44%)であり、毎年約1万6000人が新規に透析療法を導入されています。
治療の中心は、食事療法、血糖・血圧・脂質コントロールです。
糖尿病患者(約1000万人くらい)の急激な増加とともに、わが国における糖尿病性腎症患者数も急激に増加してきています。
糖尿病の罹患後10~15年以上経過してから発症することが多いとされています。
糖尿病患者全体の30%~40%(約400~500万人)が、本症に罹患していると考えられ、新規透析導入患者の原因疾患の第1位となっています。
病態と成因
【病態】
糖尿病性腎症は持続する高血糖により発症し、腎障害の進行とともに腎不全に至る病気です。
【成因】
糖尿病性腎症の成因としては、下記のものが考えられています。
① 遺伝素因 ②代謝異常 ③血行動態異常 ④慢性微小炎症 ⑤酸化ストレスなど
【症状】
初期には無症状である場合がほとんどです。
進行するとネフローゼ症候群となり、浮腫(むくみ)が出現します。腎不全になると慢性腎炎や高血圧等が原因の腎不全と同じように尿毒症症状(食欲不振、全身倦怠感等)が出現します。
【尿検査所見】
微量アルブミン尿が確認できれば糖尿病性腎症と診断されます。非常に多くの蛋白尿が出現しネフローゼ症候群となることがあります。ただし、糖尿病網膜症などを合併しない場合や高度な血尿を伴う場合は、他の病気が原因によることを考慮して、腎生検を行い確定診断を行う場合もあります。
【経過・予後】
アルブミン尿(蛋白尿)が多いほど、腎機能低下をきたす可能性は高くなります。また、腎機能低下は心筋梗塞などの心臓血管合併症を合併しやすい(心腎連関)とされ、生命予後に悪い影響を与えます。
【治療】
主な治療法は血糖・血圧・脂質コントロールで、食事療法が基本です。厚生省糖尿病調査研究班により作成された糖尿病性腎症病期新分類(表1)にもとづき、治療が行われます。
【血糖コントロール】
糖尿病性腎症病期分類の第4期までは、特に厳格な血糖コントロールが腎症の進展抑制に効果的です。具体的には、空腹時血糖130 mg/dL以下、食後2時間後血糖180 mg/dL以下、HbA1c 7.0 % (NGSP) 未満にコントロールすることが目標となります。血糖降下薬の種類に関しては、第3期までは、経口薬[ビグアナイド薬(糸球体濾過量 45ml/分以下では注意が必要)、DPP-IV阻害薬、グリニド系薬剤、αグルコシダーゼ阻害薬、SU剤、SGLUT2阻害薬]でコントロールします。第4期以降は、インスリン療法に切り替えることが勧められます。ただし、インスリン排泄の低下のため低血糖の出現には十分注意する必要があります。
【血圧コントロール】
厳格な血圧コントロールが糖尿病性腎症の全病期にわたり進行抑制に効果的です。 具体的には、130/80 mmHg未満が目標となります。降圧薬の種類に関しては、アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬、アンジオテンシンII(AT1)受容体阻害薬(ARB)が第1選択薬となります。また、Ca拮抗薬、α遮断薬、β遮断薬や利尿薬も血圧のコントロールが不良なときは併用されます。
【食事療法】
糖尿病性腎症における食事療法は、他の慢性糸球体腎炎の場合と同様に低蛋白食になります。日本腎臓学会から刊行された糖尿病性腎症の食事療法ガイドライン(表2)によると、病期分類の第2期までは蛋白制限よりもむしろ糖尿病食を基本とし、第3期以降は蛋白制限を中心とします。病期にかかわらず高血圧合併では塩分制限を必要とします。
【多角的強化療法】
脂質異常も腎障害を進展させることが知られていますので、脂質制限食やHMG-CoA還元酵素阻害薬を中心とした脂質コントロール薬も検討されます。その他、禁煙や抗血小板薬の服用などの多角的療法が腎障害を抑制に有用であるとの報告があります。
糖尿病性神経障害は30歳で発症(´・ω・`)って事は、糖尿病性腎症は45歳で発症するん???
45歳で人工透析。1週間に3日。5時間か・・・
約400~500万人の糖尿病性腎症の方、人工透析は辛いですか???

死ぬまでか・・・。
(´・ω・`)辛いのー。これは。
月2回の通院(糖尿病・突発性難聴)でも辛いのに・・・。
毎年約1万6000人が新規に透析療法を導入されています。だって(´・ω・`)糖尿病患者さんが。
明日は我が身。
その時には「腎臓」をくれ!誰か! (´・ω・`)買うよ!高額で!
犯罪かな???

今朝の血糖値です。108(mg/dl)です。いつも100(mg/dl)前後なら(´・ω・`)
インスリン中毒患者曰く。
また更新します。皆様もご自愛ください。
ランチ(´・ω・`)410円の宅配弁当。悪くはない。と思う。