こんにちは。堺市西区の上野芝にある個別指導の学習塾ONE-S(ワンズ)の塾長の松下です。
夏期講習も終わり通常授業にもどりましたが、まだまだ暑い日が続き生徒たちも大変です。
なんとかすべての生徒の夏休みの宿題を全部提出することができ、まずはホッとしております。
何度も書いていますが、特に中学生の夏休みの宿題を全員同じものにするという制度はなんとかならないでしょうか。問題集というのは、自分の学力にあった問題をするから効果があるもので、そうでなければ時間の無駄になってしまいます。小学生に高校の問題集を宿題としてやらせて、「わからないところは答えを全部写してくるんだぞ」なんてことはしませんよね。なぜなら、それがまったくの無駄になるということがわかっているからです。
それと同じようなことが中学校でおこなわれています。中学生になると、学力の差は小学生の低学年とは比べ物にならないくらい大きくなっています。中学3年生ならもっとです。大阪では、公立高校も私立高校もちょっと検索すれば偏差値の高い順の一覧表が出てきますよね。これだけ大きな学力の差があるのに、すべての生徒に同じ宿題をやらせるなんて、効率が悪すぎるというか、何のための宿題なのか理解に苦しみます。
平等という言葉は素晴らしいのですが、それがおかしな方向にいってしまうと大きな不平等を生む原因にもなってしまいます。
すべての子どもが平等に、教育を受ける機会を与えられるということは、当然ですが大賛成です。世界にはまだまだ学校がない国も多い中で、このように多くのことを学べる場があるのはとても素敵でありがたいですよね。小学校に入学して、みんなが読み書きできて、計算できるようになっていくというのはすごくいいことです。ですが気をつけなければならないのは、こうして全員が同じスピードで同じ授業をすることによって、なんらかの理由でそこから離れてしまった子どもや、ついていけない子どもをフォローする体制が整ってないことです。1ヵ月でも授業から離れることになった場合、もとに戻るのはとてもしんどいことなんです。
また、小学校の高学年や中学生になると大きな学力差が生まれているにもかかわらず、全員が同じ授業を受けます。真ん中の学力の子どもに合わせて授業するのが一般的でしょうが、学力の高い子どもにとっては退屈な授業でしかなく、逆に低い生徒にとってはほとんど理解できず、ただノートを写しているだけになっています。平均的な学力の子どもが多かった昔ならまだ通用したのですが、これだけ二極化が進んでいる現状では、いったいだれが得をする授業なのか、おそらく全員が損をする授業(先生にとっても)になっています。学校の授業の位置づけが「つまらないことであっても、黙って耐えて聞き続けること」という忍耐力を養う目的であるならばいいのですが、そうではなく「学力」を目的としているのであれば、今の学校の授業は完全に時代遅れになっています。学力の高い子どもは、学校の授業に期待などしていなく、塾の授業に頼りきっています。学力の低い生徒は、わからないものを、ただ聞くだけという拷問のような授業を受け続けています。
学ぶ機会を平等に与えることが目的ならば、今の制度ではそれを与えることができていません。なぜなら、「学ぶこと」ができていないからです。ただ授業を受けているだけなのです。
クラス分けもせずに、問題集も全員同じものをさせるのが平等だと考えているのなら、そんな平等はなくせばいいと思います。
どうしてクラス分けや問題集に差をつけることがいけないことなのでしょう? いじめにつながる? 自己肯定感を持てない子どもが増える? いえ、そんな価値観を植え付けているのは、私たち大人ではないでしょうか。テストで良い点数をとること、偏差値の高い高校や大学に合格すること、それがすべてのような感覚で、子どもと接していないでしょうか。子どもに勉強させるためであっても、そういう接し方をしてしまうと、子どもは影響されやすいので、学力の低い子を下に見てしまったり、自分が勉強できないことに必要以上に劣等感を抱いてしまうのです。今の学校教育では、いわゆるエリート、優秀な人材も育ちにくいはずです。それは国としては大きな損失です。また、勉強に劣等感を抱いてしまった子どもは自分の人生を明るく見れずに、消去法的な考え方の選択をするようにもなります。これも大きな損失です。
中学を卒業すると、すぐに不平等な社会になります。高校・大学は偏差値でランク分けされ、働き始めても給料も違えば、仕事の内容も異なり、平等とは無縁の世界になります。でも、それが自然なのではないでしょうか。高校や大学などの勉強に関しては、得意・不得意があります。勉強の適性が優れた子どもは、頑張ってその道を自信もって進んでいけばいいんです。そうではない子どもたちも、まったく自信を失うことなく、自分のしたいことや自分の力が生かせるものを選んでいけばいいのです。どっちが上や下なんてものはないのです。それぞれが異なった人間なのですから、できることや、やりたいこと、目指すもの、求めるもの、すべて違っていて当たり前なんです。それらをお互いが認め合う社会こそ、私たちが目指す社会だと思います。
ですから、形だけの、うわべだけの平等を学校教育に持ちこむのではなく、不平等であることをおそれずに伝えて、そのうえで多様な価値観を持てるように導いていくことこそが学校で行える真の教育ではないでしょうか。
この話については、もう少し書きたいこともありますが、長くなりましたので別の機会にしますね。
ONE-SのHP
夏期講習も終わり通常授業にもどりましたが、まだまだ暑い日が続き生徒たちも大変です。
なんとかすべての生徒の夏休みの宿題を全部提出することができ、まずはホッとしております。
何度も書いていますが、特に中学生の夏休みの宿題を全員同じものにするという制度はなんとかならないでしょうか。問題集というのは、自分の学力にあった問題をするから効果があるもので、そうでなければ時間の無駄になってしまいます。小学生に高校の問題集を宿題としてやらせて、「わからないところは答えを全部写してくるんだぞ」なんてことはしませんよね。なぜなら、それがまったくの無駄になるということがわかっているからです。
それと同じようなことが中学校でおこなわれています。中学生になると、学力の差は小学生の低学年とは比べ物にならないくらい大きくなっています。中学3年生ならもっとです。大阪では、公立高校も私立高校もちょっと検索すれば偏差値の高い順の一覧表が出てきますよね。これだけ大きな学力の差があるのに、すべての生徒に同じ宿題をやらせるなんて、効率が悪すぎるというか、何のための宿題なのか理解に苦しみます。
平等という言葉は素晴らしいのですが、それがおかしな方向にいってしまうと大きな不平等を生む原因にもなってしまいます。
すべての子どもが平等に、教育を受ける機会を与えられるということは、当然ですが大賛成です。世界にはまだまだ学校がない国も多い中で、このように多くのことを学べる場があるのはとても素敵でありがたいですよね。小学校に入学して、みんなが読み書きできて、計算できるようになっていくというのはすごくいいことです。ですが気をつけなければならないのは、こうして全員が同じスピードで同じ授業をすることによって、なんらかの理由でそこから離れてしまった子どもや、ついていけない子どもをフォローする体制が整ってないことです。1ヵ月でも授業から離れることになった場合、もとに戻るのはとてもしんどいことなんです。
また、小学校の高学年や中学生になると大きな学力差が生まれているにもかかわらず、全員が同じ授業を受けます。真ん中の学力の子どもに合わせて授業するのが一般的でしょうが、学力の高い子どもにとっては退屈な授業でしかなく、逆に低い生徒にとってはほとんど理解できず、ただノートを写しているだけになっています。平均的な学力の子どもが多かった昔ならまだ通用したのですが、これだけ二極化が進んでいる現状では、いったいだれが得をする授業なのか、おそらく全員が損をする授業(先生にとっても)になっています。学校の授業の位置づけが「つまらないことであっても、黙って耐えて聞き続けること」という忍耐力を養う目的であるならばいいのですが、そうではなく「学力」を目的としているのであれば、今の学校の授業は完全に時代遅れになっています。学力の高い子どもは、学校の授業に期待などしていなく、塾の授業に頼りきっています。学力の低い生徒は、わからないものを、ただ聞くだけという拷問のような授業を受け続けています。
学ぶ機会を平等に与えることが目的ならば、今の制度ではそれを与えることができていません。なぜなら、「学ぶこと」ができていないからです。ただ授業を受けているだけなのです。
クラス分けもせずに、問題集も全員同じものをさせるのが平等だと考えているのなら、そんな平等はなくせばいいと思います。
どうしてクラス分けや問題集に差をつけることがいけないことなのでしょう? いじめにつながる? 自己肯定感を持てない子どもが増える? いえ、そんな価値観を植え付けているのは、私たち大人ではないでしょうか。テストで良い点数をとること、偏差値の高い高校や大学に合格すること、それがすべてのような感覚で、子どもと接していないでしょうか。子どもに勉強させるためであっても、そういう接し方をしてしまうと、子どもは影響されやすいので、学力の低い子を下に見てしまったり、自分が勉強できないことに必要以上に劣等感を抱いてしまうのです。今の学校教育では、いわゆるエリート、優秀な人材も育ちにくいはずです。それは国としては大きな損失です。また、勉強に劣等感を抱いてしまった子どもは自分の人生を明るく見れずに、消去法的な考え方の選択をするようにもなります。これも大きな損失です。
中学を卒業すると、すぐに不平等な社会になります。高校・大学は偏差値でランク分けされ、働き始めても給料も違えば、仕事の内容も異なり、平等とは無縁の世界になります。でも、それが自然なのではないでしょうか。高校や大学などの勉強に関しては、得意・不得意があります。勉強の適性が優れた子どもは、頑張ってその道を自信もって進んでいけばいいんです。そうではない子どもたちも、まったく自信を失うことなく、自分のしたいことや自分の力が生かせるものを選んでいけばいいのです。どっちが上や下なんてものはないのです。それぞれが異なった人間なのですから、できることや、やりたいこと、目指すもの、求めるもの、すべて違っていて当たり前なんです。それらをお互いが認め合う社会こそ、私たちが目指す社会だと思います。
ですから、形だけの、うわべだけの平等を学校教育に持ちこむのではなく、不平等であることをおそれずに伝えて、そのうえで多様な価値観を持てるように導いていくことこそが学校で行える真の教育ではないでしょうか。
この話については、もう少し書きたいこともありますが、長くなりましたので別の機会にしますね。
ONE-SのHP













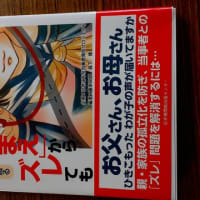
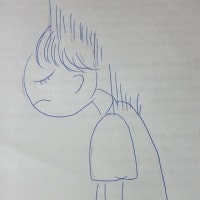
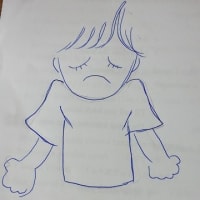
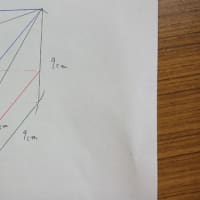
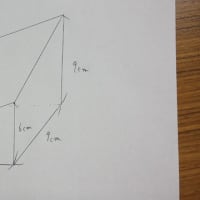
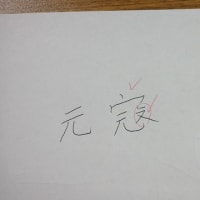
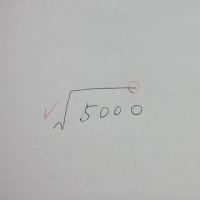
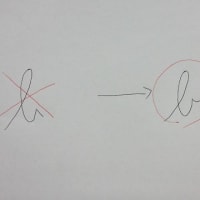






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます