軽(かろ)く、漕(こ)げや、
しづかな波に、
軽く、すべれ、
この潮(しほ)に、
寄せ來(く)る波と、吹き來(く)る風と、
共に歌へ、
この船に。
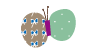
これ、なんの歌だと、思います?
日本の唱歌の出発点となった1曲、『ちょうちょう』の原曲なのです。
訳詩は、小林愛雄さん。題目は『軽く漕げ』
蝶々とは、全く関係ないのだ・・!
メロディはスペインの歌が元になっていると言われています。
またドイツほかヨーロッパ各地にも伝えられ、「ドイツ民謡」とクレジットしている楽譜もあるそうです。
蝶々の原曲
Lightly Row
スペイン民謡
Lightly row! lightly row!
O'er the glassy waves we go;
Smoothly glide! smoothly glide!
On the silent tide,
Let the winds and waters be
mingled with our melody,
Sing and float! sing and float!
In our little boat.

小林愛雄さんは、英語の歌詞から「かろく、こげや、しづかな、なみに…」と訳しましたが、
現在では野村秋足さんの「ちょうちょう、ちょうちょう、菜の葉にとまれ…」という元の舟歌とは無関係の歌詞だけが残りました。
これもまた、不思議・・!
この『ちょうちょう』の歌は、明治14年11月文部省発行の「小学唱歌集 初編」に掲載されます。
そして、昭和22年発行の「一ねんせいのおんがく」では、歌詞の「栄える御代に」を「花から花へ」に改めています。

明治14年(1881年)11月24日 「小学唱歌集 初編」
作詞 野村秋足
一、
ちょうちょう ちょうちょう。
菜の葉にとまれ。
菜の葉に飽いたら、桜にとまれ。
さくらの花の、さかゆる御代に、
とまれよ 遊べ、遊べよ とまれ。
作詞 稲垣千頴
二、
起きよ おきよ。
ねぐらのすずめ。
朝日の光の、さし来ぬさきに。
ねぐらを出でて、こずえにとまり、
遊べよ すずめ、 歌えよ すずめ。
昭和22年以降。「一ねんせいのおんがく」
作詞 野村秋足
一、
ちょうちょう ちょうちょう
なのはにとまれ
なのはにあいたら さくらにとまれ
さくらの花の 花から花へ
とまれよ あそべ あそべよ とまれ

二番以下を廃止。この改作に関しては「栄ゆる御代に」はGHQが教育現場からの排除を主張していた皇室賛美と取られるフレーズであること、二番以下の廃止は表題の「ちょうちょう」と無関係な鳥や昆虫に関する描写を排除して曲の主題を明確にしたものと解されている。
おもしろいサイトを見つけました
 『ちょうちょう』の謎
『ちょうちょう』の謎
是非~どうぞ!

蝶々の舞う春の景色。
それは、日本の原風景ですよね~。
 ≪蝶々≫
≪蝶々≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 今日はこの辺で
今日はこの辺で








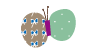



 『ちょうちょう』の謎
『ちょうちょう』の謎 蝶々の舞う春の景色。
蝶々の舞う春の景色。 ≪蝶々≫
≪蝶々≫
 今日はこの辺で
今日はこの辺で
 はなこころ
はなこころ です。
です。