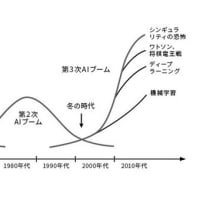IBMがメインフレーム「S/360(System/360)」を発表してから2024年で60年。「還暦」を迎えたメインフレームのモダナイズ競争が激しくなってきた。
今回は2030年度末に販売終息、2035年度末に保守終了となる富士通メインフレームからの移行をテーマに解説する。
「2035年を越えて使いたいと要請をいただいたユーザーは今のところない。ぎりぎりではあるが、(移行完了の)道筋は見えた」。
富士通の伊井哲也モダナイゼーションナレッジセンターセンター長は、富士通メインフレームからの移行に取り組んでいるユーザーの状況をこう話す。同社の調べでは2024年7月時点で320社、650台の富士通メインフレームが国内で稼働していたが「2025年3月には600台を切るだろう」(伊井センター長)。
この移行スピードが速いか遅いかは一概には言えない。600台を超えるメインフレームの中には10~20年稼働しているものもある。
1社で10台前後を保有する大型ユーザーが複数いるので、こうしたユーザーが移行を完了すれば削減台数が一気に増える。

富士通メインフレームのロードマップ(出所:富士通)
販売パートナーとの活動を本格化
移行対象のメインフレームの中身を少し掘り下げていこう。対象機種は2018年に販売開始した「GS21 3600/3400」がメインだという。
「用途は基幹系システムが多いが、オープン系システムと併用するハイブリッド型もある」(伊井センター長)。
富士通メインフレームで広く利用されている基盤ソフトが「AIM(Advanced Information Manager)」である。AIMは、オンライン処理を制御するAIM/DC(DCMS)及びデータベースを管理するAIM/DB(DBMS)の2つがある。
データベースはNDB(ネットワーク型)やSymfoWARE(リレーショナル型)が多いという。システムの移行に際しては「カスタマイズしたミドルウエアや、バッチをうまく流すためのスクリプトなどユーザー個別の仕様で手を入れている部分の移行に苦労している」(伊井センター長)。
移行対象の中では、COBOLステップで数千万といった大規模システムが注目されちだが、中小規模システムが意外な盲点になるかもしれない。
富士通メインフレームのOSは「MSP」と「XSP」の2種類がある。MSPは大手企業向けで、30数台を保有しているユーザーもあるという。
これに対してXSPは中小、中堅ユーザー向けの位置付けだ。こうしたユーザーが使うメインフレームは、富士通の販売パートナーを経由しているものがかなりの割合を占める。
パートナーの営業やエンジニアが面倒を見ているケースが多いため富士通本体から状況が見えづらく、全メインフレームの移行完遂を阻むリスクといえる。
課題解決に向けて富士通が2024年4月に立ち上げたのが「パートナーエンゲージメント室」である。販売パートナーと手を組みメインフレームを稼働させているユーザーにアプローチするための組織だ。
「正直、去年までは手薄だった」と伊井センター長が認めるように、販売パートナーとの共同活動をようやく本格化させた形だ。
-
IBMはメインフレームのハイブリッド活用推し、NEC・日立・BIPROGYもサポート継続理由(2024.12.06公開予定)
-
AWS・MS・GoogleがITモダナイズに本腰、メインフレーム巻き取る最新技(2024.12.11公開予定)
-
日新火災と損保ジャパンに見るモダナイの現実解、10年費やし段階的に(2024.12.12公開予定)
-
メインフレームは若手に任せる、IBMとアクセンチュアの真逆の発想(2024.12.13公開予定)
リライト、リホストで現行踏襲
富士通には、同社メインフレームで動いてきたシステムを別のプラットフォームへ移行し、モダナイズに導く狙いがある。
伊井センター長は「メインフレームを利用中のユーザー各社に調査を行い、モダナイズのタイミングを見計らっている」と話す。
モダナイズへの取り組みはいくつかあるが、650台が残る富士通メインフレームのうち移行方針が決まっているものは8割、残りの2割は最適解を検討している最中だ。
この8割について移行手法を見ると、リビルドが50%、リホストが25%、リライトが25%だという。
 富士通メインフレームの移行方針(出所:富士通への取材を基に日経クロステック作成)
富士通メインフレームの移行方針(出所:富士通への取材を基に日経クロステック作成)
ここからは移行手法ごとに詳しく見よう。リライトはメインフレームで稼働中のCOBOLプログラムをJavaやオープン系COBOLに書き換える。
「リライトを選ぶユーザーは運用を含めて現行踏襲がゴール」(伊井センター長)であり、自動変換ツールを使って既存プログラムを書き換えるのが基本だ。
リライトツールとしては、米Amazon Web Services(アマゾン・ウェブ・サービス、AWS)の「AWS Blu Age」、富士通の「Fujitsu PROGRESSION」、TISの「Xenlon~神龍 モダナイゼーションサービス」などが使われるという。
AWS Blu Ageはコードを読み取ってJavaへ変換する機能を提供する。「日本語対応をサービスとして富士通が提供していて、現在、高島屋がモダナイズに活用している」(伊井センター長)。
Fujitsu PROGRESSIONはCOBOLをJavaやC#に自動でリライトするツールで、Microsoft AzureやIAサーバーで動く。米国で開発したツールで、海外では50社の利用実績があり、国内では2社がPoC(概念実証)を実施中という。国内向けには2024年5月に提供を開始した。
メインフレームから別のプラットフォームへシステムを乗せ換えるリホストも、基本は現行踏襲である。ただし、移行に合わせてセキュリティーを強化するような例はあるという。
移行先はオンプレミスのオープン環境やクラウドが多いが「工場内で他システムと連係しているようなケースはプライベートクラウドに集約することもある」(伊井センター長)。
「できるだけリビルドを提案」
リビルドは現行アプリ、現行業務を全面的に見直して再構築する。一般にリライトやリホストに比べてモダナイズの効果は大きいが、難度もコストも高い。
そのため、リライトやリホストでいったんメインフレームを脱出し、その後で再構築に取り組むこともある。
富士通が手がけるリビルドは、システムを手組みでつくるほか、SAP、ServiceNow、Salesforceなどの活用も含む。「リビルドは書き換えや置き換えではなくゼロベースで立ち上げる。SAPに業務を合わせたりするので、エンドユーザーを巻き込んだ業務変革も必要だ」(伊井センター長)。
一筋縄ではいかないが「DX(デジタル変革)推進やシステムオープン化への千載一遇のチャンスではないかと、できるだけリビルドを提案する」(同)という。
リビルドのハードルの高さを考えると全体の5割という数字は小さくない。懸念されるのは、そうした高度なモダナイズを担うIT人材の確保だ。
富士通が移行のピークと見る2028年ごろに向けて、人材リソースの積み上げを急ぐ。
これから2035年まで10年余り、数百台規模で富士通メインフレームのモダナイズ事例が現れるはずだ。ユーザーもベンダーも少しずつ、モダナイズの内容や効果を検証するフェーズに入っていくだろう。差し迫った課題はメインフレームからの脱出だが、モダナイズの真価はその先にある。
日経記事2024.12.05より引用