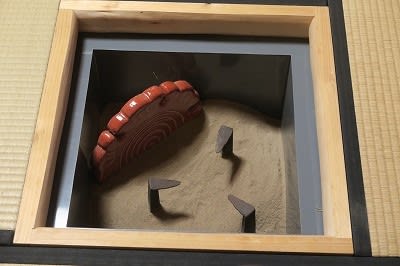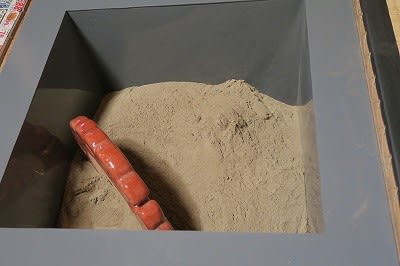2月8日(木)
大寒波は峠を越えたという報道ですが、北から西にかけての雲は穏やかな雲ではありません。
凄い北風です。
今日は、明日からの自宅のお稽古に備えて、道具の出し入れや掃除に一日を費やしてしまいました。
三時前には終わりましたので、後はのんびりとお茶を飲みながら・・・

なごみ2月号
先日届いたなごみ2月号です。
「懐石料理をおうちで」という面白いテーマを特集しておりますので、お料理好きな方は必見です。

家庭料理を
家庭料理を懐石に変えるのは心づくしのひと手間。
ほとんど同じ材料で、料理をワンランクアップさせる秘訣を紹介します。
こんな内容で頁が進んでおります。

鶏肉団子を
鶏肉団子とたっぷりの野菜から出るうま味がおいしい家庭料理で懐石のハイライトの煮物椀に、ワンランクアップさせるには・・・
レシピが事細やかに載っております。

焼物を
懐石の焼物の内、もっとも基本的な調理法が塩焼きです。
懐石は取りやすさも考慮して立体的にが基本・・・だそうです。

進肴&八寸
進肴は、亭主の心配りで加える一品ですので、あまり重くなりすぎないほうがよいでしょう。
ここでも優しい解説が、「やって見よう」の気を起こさせます。
こんな内容ですが、今月号は面白い・・・
大寒波は峠を越えたという報道ですが、北から西にかけての雲は穏やかな雲ではありません。
凄い北風です。
今日は、明日からの自宅のお稽古に備えて、道具の出し入れや掃除に一日を費やしてしまいました。
三時前には終わりましたので、後はのんびりとお茶を飲みながら・・・

なごみ2月号
先日届いたなごみ2月号です。
「懐石料理をおうちで」という面白いテーマを特集しておりますので、お料理好きな方は必見です。

家庭料理を
家庭料理を懐石に変えるのは心づくしのひと手間。
ほとんど同じ材料で、料理をワンランクアップさせる秘訣を紹介します。
こんな内容で頁が進んでおります。

鶏肉団子を
鶏肉団子とたっぷりの野菜から出るうま味がおいしい家庭料理で懐石のハイライトの煮物椀に、ワンランクアップさせるには・・・
レシピが事細やかに載っております。

焼物を
懐石の焼物の内、もっとも基本的な調理法が塩焼きです。
懐石は取りやすさも考慮して立体的にが基本・・・だそうです。

進肴&八寸
進肴は、亭主の心配りで加える一品ですので、あまり重くなりすぎないほうがよいでしょう。
ここでも優しい解説が、「やって見よう」の気を起こさせます。
こんな内容ですが、今月号は面白い・・・