漢字を深く学んで行くとある時期で必ず「杮」コケラという字に出会う。
「柿」カキに似ているけど微妙に違う事に気付き、ついつい蘊蓄を傾けてしまう。
因みに「杮」コケラは漢検対象外の漢字である。
柿 かき = 木(部首) + シ(音符)
シ(音符)
杮 こけら = 木(部首) + ハイ(音符)
ハイ(音符)
シ
 市イチの立つ場所を示す標識の形。
市イチの立つ場所を示す標識の形。
シを音符に持つ漢字は、
常用 市 シ、いち
常用 姉 シ、あね 正字=
常用 柿 シ、かき 正字=
一級 鬧 ※象形 トウ、ドウ、さわぐ、あらそう (熱鬧、喧鬧)
ハイ
 草木がしげり、花のしべが垂れる形に象る。
草木がしげり、花のしべが垂れる形に象る。
ハイを音符に持つ漢字は、
一級 旆 ハイ、はた (大旆、旆旌)
一級 霈 ハイ、おおあめ、さかん (霈然、霈艾の馬)
一級 沛 ハイ、さわ、たおれる (沛然、造次顚沛)
漢検外杮 ハイ、こけら (杮落し)
常用 肺 ハイ、こころ (肺腑)
ここにひとつだけ例外が存在する。
肺の音符は イチである。
イチである。
ただし、常用漢字では イチであるが、旧字では
イチであるが、旧字では ハイとなっている。
ハイとなっている。
字義からいって、肺の音符は「シ」ではなく「ハイ」でなくてはならない。
分かりにくいですね。金文を見たところ、
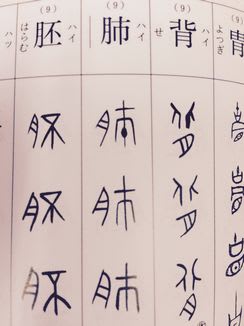
確かに、シではなく、ハイとなっている。
ということは、常用(当用)漢字に整理された時に、シになったのであろうか。
文化庁 当用漢字表(内閣告示第三十二号) 昭和21年11月16日
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/joho/kakuki/syusen/tosin02/05.html
※よく見えないですね ^^;
常用漢字でシを音符に含んでいる字は、柿と姉だけである。また、常用漢字にはハイを含んだ漢字はなかった。
想像ではあるが、常用漢字が制定された時にシに整理し、肺だけをハイにしたと考える方が自然だ。常用漢字でのシとハイの混乱を避けるためだと思う。なので、常用漢字には、ハイという字は存在しない。ある辞書では、「市シと混同して書かれた」とか「肺は古くから書道では、市シで書かれた」とか書かれているが真意のほどは定かではない。
 ハイ
ハイ
長々と書いてきましたが、わたしが言いたかったのは次のことです。
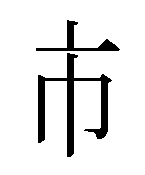 シ
シ
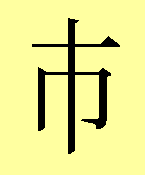 ハイ
ハイ
一級の書き取りで、沛などを書くとき、シと同じ書き方ではなく、縦に一画で下してください。
市みたく、亠 と 巾 の間に空白が出来てしまうと不正解になるかもしれないので。
なんだか、書き順辞典みたくなってきましたね(笑)
「柿」カキに似ているけど微妙に違う事に気付き、ついつい蘊蓄を傾けてしまう。
因みに「杮」コケラは漢検対象外の漢字である。
柿 かき = 木(部首) +
 シ(音符)
シ(音符)杮 こけら = 木(部首) +
 ハイ(音符)
ハイ(音符)シ
 市イチの立つ場所を示す標識の形。
市イチの立つ場所を示す標識の形。シを音符に持つ漢字は、
常用 市 シ、いち
常用 姉 シ、あね 正字=

常用 柿 シ、かき 正字=

一級 鬧 ※象形 トウ、ドウ、さわぐ、あらそう (熱鬧、喧鬧)
ハイ
 草木がしげり、花のしべが垂れる形に象る。
草木がしげり、花のしべが垂れる形に象る。ハイを音符に持つ漢字は、
一級 旆 ハイ、はた (大旆、旆旌)
一級 霈 ハイ、おおあめ、さかん (霈然、霈艾の馬)
一級 沛 ハイ、さわ、たおれる (沛然、造次顚沛)
漢検外杮 ハイ、こけら (杮落し)
常用 肺 ハイ、こころ (肺腑)
ここにひとつだけ例外が存在する。
肺の音符は
 イチである。
イチである。ただし、常用漢字では
 イチであるが、旧字では
イチであるが、旧字では ハイとなっている。
ハイとなっている。字義からいって、肺の音符は「シ」ではなく「ハイ」でなくてはならない。
分かりにくいですね。金文を見たところ、
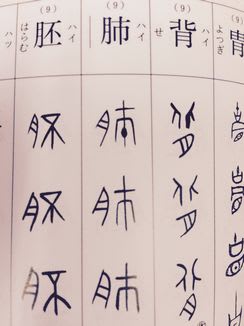
確かに、シではなく、ハイとなっている。
ということは、常用(当用)漢字に整理された時に、シになったのであろうか。
文化庁 当用漢字表(内閣告示第三十二号) 昭和21年11月16日
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/joho/kakuki/syusen/tosin02/05.html
※よく見えないですね ^^;
常用漢字でシを音符に含んでいる字は、柿と姉だけである。また、常用漢字にはハイを含んだ漢字はなかった。
想像ではあるが、常用漢字が制定された時にシに整理し、肺だけをハイにしたと考える方が自然だ。常用漢字でのシとハイの混乱を避けるためだと思う。なので、常用漢字には、ハイという字は存在しない。ある辞書では、「市シと混同して書かれた」とか「肺は古くから書道では、市シで書かれた」とか書かれているが真意のほどは定かではない。
 ハイ
ハイ長々と書いてきましたが、わたしが言いたかったのは次のことです。
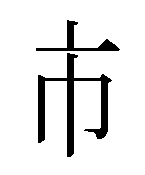 シ
シ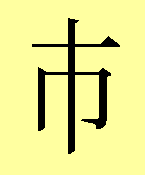 ハイ
ハイ一級の書き取りで、沛などを書くとき、シと同じ書き方ではなく、縦に一画で下してください。
市みたく、亠 と 巾 の間に空白が出来てしまうと不正解になるかもしれないので。
なんだか、書き順辞典みたくなってきましたね(笑)
















