おきゃん な娘。
キョウ
おとこだて、きゃん
俠
【解字】形声。人+夾。音符の夾は、わきの下にはさむの意味。弱者をかばい抱きかかえる力のある人、おとこだての意味を表す。
- おとこだて(をとこだて)。義に勇み、強者をくじき弱者を助ける。また、その人。「任俠」
- おとこぎ。おとこだての気性。義俠心
- はさむ(侠キョウ)。さしはさむ。
- きゃん。(キャンは唐音。「俠」を女の名のように用いたもの)
いさみ肌の女性。
はすっぱな女性。おきゃん。おてんば。
「おきゃん」
お転婆。蓮っ葉。尻軽。跳ねっ返り娘。。
あまり聞きなれない言葉でした。
実際口に出して使っている人は、今はいないでしょう。
まず最初に思ったのは、女性ファッション雑誌の ”CanCam” でした。
もしかしたら、語源はこの「おきゃん」から来ているのかなと。
しかし残念ながら、
I can campus (アイ・キャン・キャンパス)
キャンパスリーダーになれるように との意味だそうです。
「おきゃん」からの由来の方がイケてるように思うのですが・・・
「お侠」をネット検索していて面白い記事に出会いました。
杉浦日向子のおもしろ講座(2002/09/27)
http://www.geocities.co.jp/playtown/6757/020927.html
江戸では、お転婆な娘さんのことを「おきゃん」または「おちゃっぴい」と呼んでいたそうです。
「おちゃっぴい」というと現代の若者言葉のような感じを受けますが、昔からある言葉だったのですね。
そしてこの二つの言葉には年齢による微妙な使い分けがあるというから面白い。
まとめると、、
Under-16 おちゃっぴい
Under-18 おきゃん
Upper-19 艶っぽい
※註 おちゃっぴい → おしゃまさん
「ヤングなでしこ」より「おちゃっぴいジャパン」の方が個人的にはスキ。
また、今は廃刊となっていますが、「おちゃっぴい」という女性向け性雑誌があったそうです。
もちろん、お目に掛かったことはありません。
最近は、「おきゃん」はともかく「お転婆」も「蓮っ葉」も「跳ねっ返り」もほとんど聞いたことがありません。
類義語は、「利かん気」が強いというところでしょうか。
北海道では、”言うことを聞かない”から「きかない」「きかん坊」と言われています。
ただし、これは男女の区別を問いません。
--
私ごとで恐縮です。
長い間、病気療養中でしたが明日から職場復帰することが叶いました。
ちょうど一年振りに職場に顔を出すことになりますが、今はなんだか転校生のような心境です。
仕事に漢検にまた頑張りたいと思います。(ブログもまめに更新します)
いろんな方に励まされ助けられてここまで辿り着く事ができました。
本当に本当にありがとうございました。
今後とも宜しくお願いいたします。














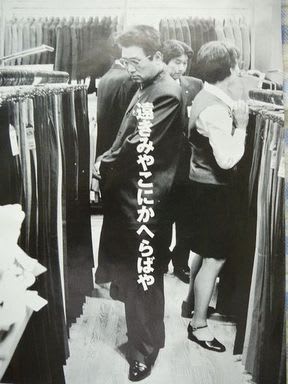

 胡 瓜
胡 瓜 茄 子
茄 子 南 瓜
南 瓜 玉 葱
玉 葱 馬鈴薯
馬鈴薯 葡 萄
葡 萄 林 檎
林 檎 蜜 柑
蜜 柑 檸 檬
檸 檬