- 祐さんから、新しい質問を頂きました。「気の利かない男性」についてです。とても興味深い内容で、せっかくですので、いくつかのレベルにわけて掘り下げて考察してみたいと思います。以下がその質問文の引用です。
- **************************************
- はじめまして。
つい最近このサイトを発見し、興味深く拝見しました。
よく女性の友人と話すことが、独身の男性は気が効かないというものです。
既婚男性は奥様に教育されているのか、女性の喜ぶツボを心得ているよねという話をしていました。
ところが私の男性を見る目が肥えてきたのか、既婚者でも気の効かない人はいるし、若くてもよく気がつく人もいます。
以前の私の上司は誰もいないのに電話をとらなかったりするなまけものでした。
「え~、ちょっとこの荷物運んでくれてもいいでしょ。」と心の中でつぶやきながらこの人奥さんとうまくいってないのかしらと思うような人がいます。
女性にも気の効かない人はいますが、そういうことって奥さんや彼女の教育ではなく、家庭環境などで培われた本人の能力の問題なのでしょうか。
今いる会社のある男性は気が効かないばかりか、仕事でもミスばっかり。建築関係の会社なので、ほんのちょっとのミスが命取りになるのですが、どうしてこんな人が一級建築士の試験に受かったのか不思議でなりません。
愚痴っぽくなってしまって申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
**************************************
まずはじめに、あくまで一般論として、「独身男性は、既婚男性に比べて、気の利かないひとが多い」かどうかについて考えてみたいと思います。このことについての実際の実験などの研究は私の知る限りありませんが、一般常識的な推測で、それから、異性間での結婚についてですが、「結婚という共同生活を経験している男性は、ひとりだけで生活している独身者と比べて、そこに自分とはまったく違う生活環境で育った性格も世界観も異なる他者とうまくやっていく過程で、それまでは気付かなかったいろいろなことを必然的に学ぶようになり、また、その生活から、女性が何を求めているのか知るようになり、その結果、独身時代よりも気が利くようになる」、という推論はすぐに思いつきました。これは実際私の観察する限り、あくまで概して、ですが、YESであると思います。しかし、この差がどれだけ大きいかは疑問です。圧倒的な違いではないし、そうでないケースも相当にあります。
たとえば、亭主関白で超ワンマンな男性が、控えめで消極的で気配りの細かい女性と結婚したら、彼がこの結婚で「気が利く」ようになる可能性は低いですし、また、もともと気の利いていた男性が、非常に独立心が強く、相手に何かをしてもらうことに強い抵抗を示す女性と結婚したら、彼は彼女とうまく生きるために、今まで気を利かせてしていたいろいろなことをしないようにしていきます。「しないこと」が、この女性とスムーズにやっていくことに繋がるからです。このような結婚生活を何年も続けているうちに、彼はしないことが自然になり、独身時代と比べて「気の利かない」男性になるかもしれません。
それから、結婚はしていないものの、事実婚など、長期的、半永久的な同棲をしている男性は、この論理でいえば、新婚の男性よりも、独身でありながら、ずっと気が利く可能性は高いです。また、先ほど、「異性間での結婚」と書きましたのは、たとえばGayのカップルは、日本では「結婚」はできないものの、その共同生活で、ものすごく気が利くようになる人が多いです(彼らのなかにはもともと女性のような気遣いをする人が多いですが)。
さらに、これもよく知られていることですが、年下のきょうだいがいたり、異性のきょうだいがいる人は、一人っ子のひとよりも、気が利くことが多いといわれています。きょうだいという、血は繋がっているものの自分とは異なる人格をもった他者とうまくやっていくなかで、いろいろなバランス感覚、気配りを学ぶからです。
ところで、電話をとらないあなたの上司は、気が利かない、というよりも、性格の問題かもしれません。ひょっとしたら気付いているものの、部下のあなたが電話に出ることが当然、または、出るべきだと思っているため、出ないのかもしれません。あなたがいなくて、ひとりだったら出ているかもしれませんし、もしそこに彼の上司でもいたら、彼はさっさと受話器を取っているかもしれません。あまり感心できない態度ですが。。。
「女性にも気の効かない人はいますが、そういうことって奥さんや彼女の教育ではなく、家庭環境などで培われた本人の能力の問題なのでしょうか」、という質問に対する回答ですが、「奥さんや彼女の教育」と、「家庭環境などで培われる」ものに、はっきりした境界線、違いはなく、どちらの状況下においても、本人が身につけたものは能力であり、それは、これまでの説明でお分かりだと思います。
さて、ここから一段レベルの高い話をします。
人間は、無意識的に、自分の関心のあるものにどんどん注意が向き、同時に興味のないものには注意が向かないことがよく知られています。これは認知心理学の実験などでも明らかなことです。つまり、あながた他者を観察するときに、ほとんど無意識的に、「気が利く、利かない」、という基準を基にしているため、そこに神経が集中し、いままで気にならなかったことまで気になるようになっている、という印象があります。
また、人間は、以前私が『確証バイアス』の記事でも書いたように、自分が見たいものを見、見たくないものは見ない、つまり、自分の考えにつじつまがあう情報に注意がいき、つじつまが合わない情報は無意識に排除される、ということです。たとえば、あなたのまわりの「気の利かない」ひとが、いつも気が利かないのではなく、何か気の利くこともしているのだけれど、確証バイアスによって、その情報が抜け落ちている、という可能性があります。
もうひとつ、これも実は大事なポイントですが、「何をもってして、気が利く」のか、「気が利く」とはどういうことなのか、自問してみると新しい発見があるかも知れません。というのも、これらは人それぞれで全然違った基準があったりするもので、その人の価値観に左右されるところが多く、ある人にとっては「気の利く」行為が、別の誰かにとってはどうでもよかったり、全然気にならない場合もあるからです。もちろん、誰がどう見ても気の利かない人はいますが、「ちょっと気が利かないなあ」、と思った人が、実は別の視野でみると案外気が利いていたりすることはよくあります。このように考えていくと、何かが気になったとき、相手に注意を向けるよりも自分のこころを観察することで、何が自分にとって大事なのか、対人関係でどのような欲求が自分にあるかなど、いろいろな発見があって面白いです。
最後にまとめますが、気が利く人、気が利かない男性の違いは、1)配偶者、長期的なパートナーの有無、2)家庭環境の違い、3)1と2の相互作用、4)本人の性格、5)1、2、4の相互作用、そして、6)あなた自身の認知によるものと、その人の言動との相互作用、という少なくとも6つの観点において考えられると言えそうです。














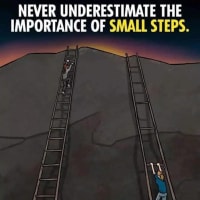
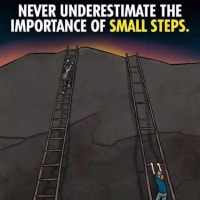




漢字が間違っていましたね。お恥ずかしいです。(・ ・;)
>「何をもってして、気が利く」のか、「気が利く」とはどういうことなのか、自問してみると新しい発見があるかも知れません。
この言葉にはっとしました。「気が利く」ってもしかしたら、自分にとって都合が良いに近い感覚かも。。。
手を怪我して包帯をしていた時に、スーパーのレジでバイトの学生さんがカゴをレジから台まで運んでくれたんです。このスーパーは誰もがやってくれました。ところが、会社の男性は知らんぷりしたので、イラっとしてしまいました。
イギリスでは女性が重い荷物を持っていると見知らぬ男性が手伝ってくれますが、これは紳士階級の人だけだということがわかりました。
欧米ではドアをホールドするのも生活習慣から来ていますよね。日本は引き戸ですから。
>自分が見たいものを見、見たくないものは見ない、
これはテレビで見たことがあります。
数人がバレーボールをやっているVTRを見て、ボールだけを見てくださいと言われると、真ん中を熊の着ぐるみを着た人が通っても全く気がつきませんでした。
今の会社ではお客様のクレームは私が最初に受けるので、誤るのも私ですから、「なんでこんなこともできないのかしら」と思う気持ちがあったのかも知れません。
もしかしたら自分でルールを作って、それにあてはめようとしていたのかもしれません。
おつきあいしていた男性には「こうだったら良いのに」とかって感じたことないんですよね。
大切な気づきをありがとうございました。
再び大変興味深い回答、ありがとうございます。
まさにそういうことだと思います。スーパーにおける経験も、大変面白いですね。
祐さんから質問をいただき、回答し、さらに回答をいただいたものを読んでいるうちに思いましたが、祐さんが仰る「気が利く」ほぼイコール「自分にとって都合が良い」という感覚はつまり、心理学的にいうと、どれだけその行為者(或いは非行為者)が、相手の言外の必要、気持ち、欲求、困っていることなどを正確に汲み取って、それに答えられる(かどうか)、つまり、行為者の共感(Empathy)能力の質といえそうです。
以前、混んだ電車内で、明らかに妊娠しているのに席を譲ってもらえなくて辛かった、という女性と、妊娠していないのに妊娠していると勘違いされてしきりに席を譲られ辛かった、という女性から聞いた話を思い出しました。
これは、席を譲るという行為そのものよりも、その人の気配りや空気を読む能力の質を表していて、まったく同じ行為(非行為)が、相手によって適切であったり不適切であったりする好例で、この例の「妊娠」を「高齢者」に置き換えたものはよくある話ですね。
譲られて「年寄り扱いされた」と思う人と、譲られずに「年寄りなのに大切にしてもらえなかった、冷たい社会だわ」、と思う人がいます。
ひとは他者に、言葉を使って伝える前に何かして欲しかったことをしてもらうと大変嬉しいもので(これは私が以前書いた『甘え』についての記事にも関係していますが)少し前はそういうことが普通だったのが、欧米などの影響で社会の変化によって人々のメンタリティも変わり、
「言葉を使わないと気持ちは伝わらない、言葉によるコミュニケーションが大切」である世のなかへと変わりつつある現われであるようにも思います。
バレーボールの例も、面白いですね。日本ではそういう面白い番組をやっているのですね。確証バイアスとはまさにそれです。人の認知のバイアスはときにありえないようなことも普通にしてしまいます。
「気が利かないなあ」と思うのは、自分のニーズが満たされていない、という大切なシグナルで、とても自然な気持ちだから、それをよく理解して受け入れて、いかに満たしてあげたり、また状況によってはうまく表現していくかを心がけてゆくと、逆説的だけれど、相手はあなたがどういう人でどういうことが大切なのか理解が深まり、共感性がでてきて、それまでよりも気が利くひとになっていったりするもので、人間って面白いなあと思います。
こうして見ると「良い病院」「良い店」というのも、自分にとって都合が良かったということなのかも知れないと思いました。
「安くておいしい店」と聞いて行った店が安くておいしいけれど、気難しいおじさんがやっていて怖くて味を感じる余裕がなければ、良い店とは思えないわけですし。
「あそこの先生は名医で命を救ってもらった」と聞いて行った病院が受付の対応が悪かったというだけで「あの病院はだめ。」となるわけですよね。
「気が利く」とか「良い」とかいうのは非常に曖昧なものなんですね。
日本には以心伝心という言葉があるので「これくらいは察してよ。」と思ってしまうのかもしれません。
以前、父の香典返しの準備で百貨店に行った時、売り場に誰もいなくて、隣のブライダルの担当者は関係ないといった顔で私語をしていました。
やっと来た店員に声をかけると、無視をして別の客のところに戻りました。
父の希望でその百貨店に行ったのですが、こんな店で父が生前買い物をしていたのかと思うと涙が出てきて、その百貨店にクレームを入れたことがありました。
しかし、百貨店にしてみれば、それが普通で、私が百貨店に自分の価値観を押し付けていたのかもしれません。
それはその人が選んだ仕事のやりかただから許そうと思えば腹も立たないのかもしれません。
心って深くて本当におもしろいですね。
仰せの通りだと思います。良い店、良い病院とはつまり、その人の物理的或いは心理的なニーズを正確に把握してきちんと満たしてくれるところだと思いました。人それぞれ、心理的、物理的ニーズは異なるから、ある人にとっては良い店、よい病院が、別のひとにとっては全然良くなかったり、ひどいところだったりします。先日、知人がある心療内科医に通っていてその医者がすごいいい、と話し出して、内心驚いたのは、彼は一般的には技術も知識もなく患者確保に必死で適当なことをしている医者として知られるからでしたが(私も実際に会ったことはないものの、彼の書く記事を読んだり、彼と会った人の話を聞いて、まずい医者だなという印象はあります)それでも人によっては良い医者、良い病院になるんですよね。私は一瞬迷ったけど、よく話を聞くとその人がその医者のところで実際に良くなっているようだったので、「良いお医者さんが見つかって良かったですね。とくに心のことは、相性が大切ですからね」、とだけ答えました。
それにしても、その百貨店での経験は悲しいと思いました。お父様との思い出があって、そこに強いSentimentがあったらなおさら、腹が立つのも自然なことだと思います(実際ひどい対応でしすね。そこの店員たちは、それぞれ事情はあるだろうけど、せめてもう少し善意的な対応ができなかったものかな、と思います。無視して他の客のところにいくのではなく、「少々お待ちください」など、一言でも全然違いますし)。
きっとお父様は生前そこで、彼にとって本当に個人的なこころの繋がり、満足感があったのかもしれませんね。
祐さんの話の中の、「病院」について、私も同じように感じたことがあります。
同じ病院について、Aさんは
「とても丁寧に診察してくださって、いいお医者さん」
と話し、Bさんは
「技術も未熟で全くよくない医師だ」
と話し、Cさんは
「イイトシしたおっさんがミッキーの時計なんかして気持ち悪い」
と話していました。
私個人としては
「丁寧に診察してくださり、こちらの要望も聞いてくださって、優しくてとてもいいお医者様」
といった印象でした。
同じ医師ですが、人によって意見が異なるものですよね。
また、店に関しても同じで、
美味しいラーメン店、といった記事に対しても
私個人は、話半分に読むことにしています。
味の好みも千差万別。
脂っこいものが好きか嫌いか
甘~~いものが好きか嫌いか
人によってそれぞれだからです。
好き嫌い、良い悪いが、実はいかに主観的で、個人的なものであるか、考えてみると面白いですね。もちろん誰がどこからどう見ても悪いもの(例えば麺が延びまくってスープが恐ろしくぬるくて味気がなく、チャーシューはゴムのように硬く、もやしやねぎは腐っているラーメンを提供するお店)など考えられますが、世の中のたいていのものは、多かれ少なかれ、意見の分かれるもので、どこかの人格障害の市長さんでさえ、良いという人は少なからずいます。私は彼のように共感性の欠落した首尾一貫性も国際感覚もない病的に強い自己愛を持ったお方が政治家であるのは非常に危険で間違ったことだと思いますが、彼には確かにリーダーシップ能力はあり、このように先の全く見えない不確かな世のなかで彼のような存在に安定感や理想を見出す人もいるわけで、世の中面白いなあと思います。
最も端的に言えば、相手が自分にとって、十分に細やかな配慮があるのかないのか、ということが頭に浮かびます。
それはまた、愛情の裏返しと言えなくもありません。
ところが、本当のところは、その人に備った、最も本質的な人格的内面の要素を凝縮していると、私は思うのです。
こんな議論は、恐らく、日本でしか話題にならないと思うのですが、そんな話題に心を寄せる、そんな細やかな配慮が、まさしく日本人の特性ではないかと、微笑ましく感じます。
実際のところ、こういう現象は文化を超えたもので、アメリカでもこういうことは非常に大切ですよ。その現れ方が日本とはだいぶ異なるわけだけれど、アメリカでも、空気の読める人、思慮深い人、配慮のある人は社会的に成功する傾向があるし、組織のリーダーである場合が多いし、また、私生活でも、人気のある人たちです。心理学においても、他の記事で触れたIntersubjective theoriesなどは、この分野に特に深く関係しています。