
つつじが咲き誇る山の中腹に先祖代々の墓地があった
ある年、祖先の墓は移転となり、菩提寺の住職や親戚たち、
地下足袋のおじさん達が墓前に揃った。
戒名の文字も消えかかり風雨に傷んだ墓石が取り外された
そこだけ色の違う地面がスコップで掘り起こされて行く
50cm~1m掘ってもまだ出ない。緊張した面持ちで見守るなか、
「グズッ」というくぐもった音が聞こえた。
腐った柩を突き崩す音は記憶に残る音
土にまみれ朽ち果てた「骨」は一塊の「土くれ」のようだった
愛する人の「白い骨」には頬ずりも辞さないが、
「土くれ」にはとうてい、できそうにないと思った。
今に思えば
「時が経つ」とはそういうことか
「土に還る」とはこういうことか
傍らに灰色が混じったもしゃもしゃの髪がある
髪の中で見知らぬ「虫」が蠢いていた
先人の不屈の意思をも、虫はすべてを喰い尽くし
清浄も不浄もない白の冥界へといざなうがごとし。
願 文(がんもん) 天台宗
悠悠(ゆうゆう)たる三界(さんがい)は 純(もっぱ)ら苦にして安きことなく
擾擾(じょうじょう)たる四生(ししょう)は 唯(た)だ患(うれい)にして楽(たのし)からざるなり
牟尼(むに)の日久(ひさし)く隠れて慈尊(じそん)の月未(いま)だ照らさず
三災の危(あやう)きに近づき五濁(ごじょく)の深きに沈む
加以(しかのみならず)
風命(ふうみょう)保ち難(がた)く露體(ろたい)消え易(やす)し
艸堂(そうどう)楽(たのし)み無しと雖(いえど)も然(しか)も老少百骨(ろうしょうびゃっこつ)
を散じ曝(さら)し
土室(どしつ)闇(くら)くせましと雖(いえど)而(しか)も貴賎魂魄(きせんこんぱく)を争い宿す
彼を瞻(み)己を省るに此(こ)の理(り)必定(ひつじょう)せり
仙丸(せんがん)未だ服せず遊魂(ゆうこん)留め難し
命通(みょうつう)未だ得ず死屍(ししん)何(いつ)とか定めん
生ける時善を作(なさずんば)死する日獄(ごく)の薪(たきぎ)と成らん
得難(えがた)くして移り易(やす)きは其(そ)れ人身(にんしん)なり
発(おこ)し難(がた)くして忘れ易きは斯(こ)れ善心(ぜんしん)なり
是(ここ)を以(もっ)て
法皇(ほうおう) 牟尼(むに)は大海(だいかい)の針(はり)妙高(みょうこう)の線(いと)
を暇(か)りて人身(にんしん)の得難きを喩況(ゆきょう)し
古賢(こけん)う王は一寸の陰(とき)半寸の暇(いとま)を惜(おし)みて一生の過ぐるを
嘆勧(たんがん)せり
因(いん)無くして果(か)を得(う)る是(こ)の処(ことわ)り有(あ)ること無く
善(ぜん)無くして苦を免(まぬが)る是(こ)の処(ことわ)り有(あ)ることなし
伏(ふ)して己(おの)が行迹(ぎょうしゃく)を尋(たず)ね思うに
無戒(むかい)にして竊(ひそか)に四事(しじ)の労(いたわり)を受け
愚癡(ぐち)にして亦(また)四生(ししょう)の怨(あだ)となる
是(こ)の故(ゆえ)に未曾有(みぞう)因縁経(いんねんきょう)に云(いわ)く
施(ほどこ)す者は天に生まれ
受くる者は獄(ごく)に入(い)ると
提韋(だいい)女人(にょにん)の四事(しじ)の供(そなえ)は末利夫人(まりぶにん)
の福(さいわい)と表われ
貪著(とんじゃく)利養(りよう)の果(はて)は石女(しゃくにょ)擔譽(かっこ)の
罪と顕(あらわ)る
明(あきらか)なる哉(かな)善悪の因果(いんが)誰か有慙(うざん)の人(にん)に
して此(こ)の典(のり)を信ぜらん
然(しか)れば則(すなわ)ち
苦因(くいん)を知りて而も苦果(くか)を畏(おそ)れざるを釈尊(しゃくそん)は
闡提(せんだい)と遮(しゃ)したまい
人身(にんしん)を得て徒(いたずら)に善業(ぜんごう)を作(な)さざるを
聖経(しょうぎょう)には空手(くうしゅ)と嘖(せ)めたまう
是(ここ)に於(おい)て
愚が中の極愚(ごくぐ) 狂(おう)が中の極狂(ごくおう) 塵禿(じんとく)の有情(うじょう)
底下(ていげ)の最澄 上は諸仏に違(い)し 中(なかごころ)皇法(こうぼう)に背(そむ)き
下(しも)は孝礼(こうれい)を闕(か)く
謹(つつしみ)て迷狂(めいおう)の心(しん)に随(したが)い三二の願を発(ほっ)す
無所得を以(もっ)て方便(ほうべん)と無し無上(むじょう)第一義(だいいちぎ)の為に
金剛(こんごう)不懷(ふえ)不退(ふたい)の心願(しんがん)を発(ほっ)す
我れ未(いま)だ六根相似(ろっこんそうじ)の位(くらい)を得(え)ざるより
以還(このかた)出假(しゅっけ)せじ
未(いま)だ理(り)を照らすの心を得(え)ざるより以還(このかた)才藝(さいげい)あらじ
未(いま)だ淨戒(じょうかい)を具足(ぐそく)し得(え)ざるより以還(このかた)
壇主(だんしゅ)の法会(ほうかい)に預(あずか)らじ
未(いま)だ般若の心を得(え)ざるより以還(このかた)世間の人事縁務(じんじえんむ)
に著(じゃく)せじ相似(そうじ)の位(くらい)を除く
三際(さんさい)の中間(ちゅうげん)に修(しゅう)する所の功徳(くどく)は己(おの)が
身に受けず普(あまね)く有識(うしき)に回施(かいせ)して悉(ことごと)く皆(みな)
無上菩提(むじょうぼだい)を得(え)しめん
伏して願わくは
解脱(げだつ)の味(あじ)独(ひと)り飲まず安楽(あんらく)の果(か) 独(ひと)り
證(しょう)せず
法界(ほうかい)の衆生(しゅじょう)と同く妙覺(みょうがく)に登り
法界(ほうかい)の衆生(しゅじょう)と同く妙味(みょうみ)を服せん
若(も)し以(こ)の願力(がんりき)に依(よ)って六根相似(ろっこんそうじ)の位(くらい)
に至り若(も)し五神通(ごじんづう)を得ん時必ず自度(じど)を取らず正位(しょうい)を
證(しょう)せず一切に著(じゃく)ぜらん
願わくは必ず今生(こんじょう)無作(むさ)無縁の四弘請願(しぐせいがん)に
引導(いんどう)せられて
周(あまね)く法界を旋(めぐ)り遍(あまね)く六道(ろくどう)に入(い)り
佛国土(ぶっこくど)を淨(きよ)め衆生(しゅじょう)を成就(じょうじゅ)し
未来際(みらいさい)を尽くして恒に佛事(ぶつじ)を作(な)さん












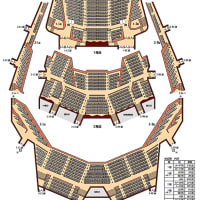





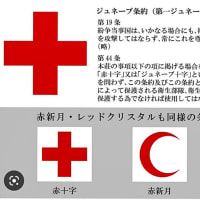
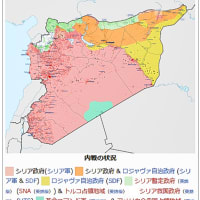
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます