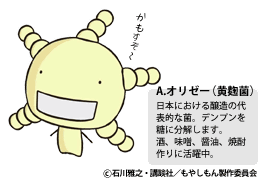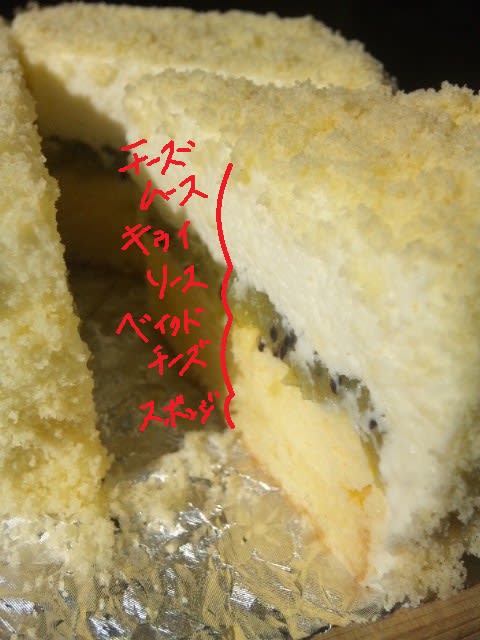しょうゆ情報センター&レシピブログ主催「勇気凛りんさんと学ぼう♪大人のためのしょうゆ出前授業」に参加してきました。
醤油についてのレクチャー&クイズ、料理デモ~試食という流れ。参加者は30名ほどでたぶん私が最年少でした。せっかくだからお話できたらいいな~と思っていたのですがクイズの際に二言三言言葉を発しただけで会話らしいものはほぼゼロ。自分のコミュ力の低さに涙が出そうです。
さて、気を取り直してレクチャーの概要をさらっと。醤油の香り・味・色や醸造工程、5種の醤油の各々の特徴、醤油のラべルについて……などなど盛りだくさんの内容でした。2013年12月には和食がユネスコの無形文化遺産に登録され、醤油はその食文化と共にますます関心を高めています。ヨーロッパを始め海外の料理人からも「万能調味料」として醤油が注目を集めている今、私たち日本人が醤油について何もわかっていないというのは悲しい話。今回のイベントは醤油をより深く知るよいきっかけとなったと思います。
では、当日の様子を掻い摘んでご紹介していきます。
醤油には大きく分けて「濃口」「淡口」「たまり」「再仕込み」「白」の5種類があります。今回はそのすべてを味見することができました☆普通の家庭でこの5種類が揃っていることなんてめったにないでしょうからこれは結構貴重な体験です。以下、それぞれの醤油を比較しながら説明していきます。

濃口醤油vs淡口醤油
濃口醤油は醤油消費量の8割以上を占める醤油で、味の五大要素、塩味・旨味・甘味・酸味・苦味をバランスよく併せ持っているのが特徴です。調理用・卓上用どちらにも使える、まさに万能調味料。
一方、淡口醤油(“うすくちしょうゆ”と読みます)は「うすくち」と言いながら濃口醤油よりも塩分高め。この高塩分により色が薄く仕上がります。色・香り共に控えめなので素材の色を活かしたい料理(代表的なのは京料理ですね)に使われます。「塩分が高いとただただ尖った味になってしまうんじゃない?」と思いますよね。そこで味をまろやかにするために醸造過程で甘酒を加えているそうですよ。
後述しますが、高野豆腐を煮る際 淡口醤油を使った方がしっとりなめらかな食感になるのだとか。実際に食べ比べた感想はまた後ほど♪
たまり醤油vs白醤油
上ふたつの醤油は大豆と小麦がほぼ1:1でできていますが、こちらの醤油はほぼ大豆orほぼ小麦という組成です。
ほぼ大豆からなるたまり醤油。同じく「原料の大半が大豆」である日本の発酵食品といえば豆味噌が思い浮かびますが、このたまり醤油はまさに豆味噌を作っている過程で生まれました。色が濃くとろみがあって、強い旨味・独特な香りが特徴です。すしや刺身のほか、加熱によりきれいな赤みがかった色になるため照り焼きにも使われます。
これに対して、ほぼ小麦からなる白醤油はその名の通りの薄い色合い。淡口醤油よりもさらに色が薄いです。味は淡泊ですが小麦由来の糖分が多いため甘味も強いのが特徴。色や味、香りなどの品質の劣化がほかの醤油よりも速いらしく、家庭では扱いが難しいとか。そのため一般的に使用している家庭はごくわずかなようですが、この日集まった方々は結構な人数が使っていらっしゃるようでした。さすがお料理ブロガーの会だわ。笑
最後に再仕込み醤油。
色・味・香り、どれをとっても濃厚なのが特徴。一般に醤油は麹を食塩水で仕込みますが、代わりに生揚げ醤油で仕込むという贅沢さ。「甘露醤油」とも呼ばれ、刺身や寿司、冷奴など主に卓上用として使われます。
醤油を味わうための料理は、鯛かぶら高野豆腐と鶏肉の照り焼きでした。勇気凛りんさん考案レシピです。


鶏の照り焼きはたまり醤油を使用しているので、赤みがかった焼き色がとてもおいしそう。焼いている間の香りもたまりませんでしたよ。シンプルな味付けだからこそたまり醤油のよさが存分に味わえる感じ。


醤油以外の材料は変えずに、左:濃口、右:淡口で煮てあります。出汁の色が明らかに違いますね。さて、気になる高野豆腐の食感は……確かに淡口で煮た方がしっとりした感じでした。濃口の方はちょっとぼそっとしていたかな(スポンジみたい?)。醤油の分量が同じだったので淡口の方が塩辛く感じられましたね。
さて話は変わって、醤油造りの要といっても過言でないのが醤油麹。その主役となるのが、漫画「もやしもん」で可愛らしい姿で描かれている、あのオリゼーです。

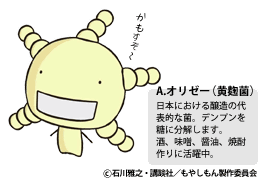
醤油に使用されるのはAspergillus oryzae(アスペルギルスオリゼー)のほか、Aspergillus sojae(アスペルギルスソーヤ)を加えた2菌種。これら麹菌たちは醤油の旨味や香りの成分を作るための様々な酵素の供給源として大事な存在です。上記2菌種が産生する酵素はそれぞれそ性質が少し異なるため出来あがる醤油の風味が微妙に異なるのだそう。さらには、同じ菌種の中でも菌株によって違いがあるため醸造元によって味わいが異なるそうですよ。醤油醸造元めぐりなんて楽しそう~
アスペルギルスといえばカビ毒が思い浮かびます。このカビ毒「アフラトキシン」は天然物最強といわれる発がん性を有しており、Aspergillus flavusやAspergillus parasiticusがその主な産生源。そして、これらの菌種はA. oryzaeやA. sojaeと分類上非常に近縁な関係にあります。それもそのはず、A. oryzaeの祖先はA. flavusとする説が有力なのだそう。A. flavusが長い時間をかけて飼い馴らされたのがA. oryzaeというわけです。
そうすると、気になるのはA. oryzaeが本当にカビ毒を産生しないのかどうか。それを遺伝子的にはっきりさせたのが、麹菌のゲノム解析なのでした。この研究により、アフラトキシン生合成遺伝子に欠損や変異が確認され、我が国で使用されている麹菌はアフラトキシンを産生しないことが明らかとなりました。
500年以上の家畜化の中で、必要でなくなった遺伝子(=アフラトキシン産生遺伝子)の機能を落とし、醸造に欠かせない遺伝子を増やしていった麹菌たち。なんだか健気で可愛く思えてきませんか?
昔は一世帯あたり年間10L近くの醤油を消費していましたが、最近では6Lほどに落ち込んでいるそう(我が家は主に和食なのできっと昔の水準に達しているはず☆)。日本が世界に誇る万能調味料である醤油、積極的に使っていきたいですね。
参考→★
イベントの詳細はほかの参加者の方が詳しく書いていらっしゃるので下のバナーから飛んでみてください☆

「これが麹菌ですよ」と培地に生やした菌を見せてくださった時、斜面培地だ~と微物の実習が懐かしく思い出されたのでした。笑
今日もぜひぜひ応援クリックお願いしまーす
こちらもどちらかぽちっと…