『筑波海軍航空隊』を観てきた。
ある老人にカメラが向けられる。
彼は、学徒出陣で徴用され、神風特攻隊員となった。
当時の若者には陸軍は人気がない。これまで特攻に関するいくつかのドキュメンタリーを観たけれど、皆言う。
「海軍の制服は、カッコいいんだよ」
「零戦に乗りたかった」
軍隊をそうやって選ぶ。なんとも、若者らしいファッションに満ちた選び方だ。
彼らは、普通の若者だったのだ。
そんな彼らが、突然国を背負わされる。そして、命を捨てて国を護れ、と言われる。
それでも、日々を楽しむ。訓練をし、飯を食う。
それでも、恋をし、手紙を書き、恋人の名を海に叫ぶ。
そして、仲間たちに「先に行くぞ」と告げ、彼方の空へ消えていく。
そう。どうしようもないぐらい、彼らは普通だった。
戦争の困ったところは、戦争は人の理性の発露の結果であるということだ。
奪うためじゃない。護るために殺しあう。
だが、負けが近付いてくると、理性が狂気と化し本能が暴れだす。何を護るのかが分からなくなってくる。いや、護るものがもう失われてしまっているのに、それに気付くことすら出来なくなってしまう。
“戦線から遠のくと、楽観主義が現実に取って代わる。そして、最高意志決定の段階では、現実なるものしばしば存在しない。戦争に負けているときは特にそうだ。”
ジェイムズ・F・ダニガン
戦闘機乗りが戦闘機を駆使して戦うのには1000時間の飛行訓練が必要だといわれていた。だが、学徒出陣により集められた彼らには200時間程度の訓練時間しかなかった。
おそらく。これはおそらくだけれど、海軍の首脳陣たちは彼らを、戦闘機で戦闘させる気は無かったんじゃないだろうか?
戦局と資源事情を鑑みれば、戦闘機乗りを大量に作り出す時間は無い。ならば、ギリギリ戦闘機を飛ばせる程度まで仕込んだ即席パイロットを作り、彼らには爆弾を抱えて敵艦に突っ込んでもらおう。即席パイロットが戦闘を展開した所で勝てるわけが無い。だが、特攻させるなら10に1程度は戦果があるだろう。
個を見れば万死零生の作戦でも、少し大所高所で見れば戦果があったとも言える。
自分で書いていても、自分の思考にゾッとするけれど。
なんて、楽観的で現実離れした発想だろう。
戦争は人殺し合いだ。
戦争は、外交の果てにある、国力の削り合いだ。国力は、資源力であり、戦艦や飛行機の生産力であり、そしてそれらを使う人を指す。中でも、人を削ることは国力の最も効果的な削り方だ。
だから、戦争は人殺し合いなのだ。
日本は戦後70年という節目にいながら、未だにあの戦争に決着を着けきれていない。
70年間もただただ太平洋の片隅に浮かんでいただけだ。
70年間も戦争をせずに済んだのは、そう思い込んでいるだけだ。PKO、イラク派兵で沢山の日本人が死んでいる。
最近の戦争はアウトソーシングが進み、イラク戦争ではアメリカ軍にケータリングをする会社があるそうだ。その会社には民間日本人がいて、実際にイラクで働いていたそうだ。
僕らは、戦争の中にいる。
僕が最も憤りを感じるのは、大人たちの始めた戦争を、自分たちで処理しきれず後世の者たちに引き継がせようとする姿勢なのだ。
「近年、外交状況が悪化したから、もしもの時のため開戦しやすくします。これで国民を護ることが出来ます」と言う。
外交状況を改善できるチャンスは70年間あれば、何度も何度もあったはずだ。それをしなかった所為で、中国、韓国との関係は良くないままだ。
大人がやらなければならないことを、子供たちに押し付けようとしている。
それは学徒出陣にも言えることだ。いや、その時に学ぶべきだったことだ。大人が始めた戦争に、なぜ子供を巻き込んだ?大人だけで解決しなければならなかったはずだ。
藤田暢明少尉という人物がいた。
彼は、神風特攻で戦死した。
彼には睦重という恋人がいた。
二人は結婚した。
彼の出撃後に、睦重さんは花婿のいない結婚式を挙げた。
親族も集まったそうだ。結婚式に反対の者はいなかったそうだ。
その結婚式の写真が残っている。
綺麗な、本当に綺麗な睦重さんの白無垢姿。
でも、その横にいるはずの花婿はいない。
今の問題を次世代に背負わせるとは、こういうことなのだ。
未来を奪い、得られるはずだった幸せを奪い、彼らの間に産まれるはずだった命さえ奪う。
特攻隊員たちは、未来を作るために、今を見つめ、そのとき自分の出来ることの全てをした。
僕たちは彼らを見習う必要がある。保身のためでなく、今、自分に出来ることが何かを考える、ということを。
ある老人にカメラが向けられる。
彼は、学徒出陣で徴用され、神風特攻隊員となった。
当時の若者には陸軍は人気がない。これまで特攻に関するいくつかのドキュメンタリーを観たけれど、皆言う。
「海軍の制服は、カッコいいんだよ」
「零戦に乗りたかった」
軍隊をそうやって選ぶ。なんとも、若者らしいファッションに満ちた選び方だ。
彼らは、普通の若者だったのだ。
そんな彼らが、突然国を背負わされる。そして、命を捨てて国を護れ、と言われる。
それでも、日々を楽しむ。訓練をし、飯を食う。
それでも、恋をし、手紙を書き、恋人の名を海に叫ぶ。
そして、仲間たちに「先に行くぞ」と告げ、彼方の空へ消えていく。
そう。どうしようもないぐらい、彼らは普通だった。
戦争の困ったところは、戦争は人の理性の発露の結果であるということだ。
奪うためじゃない。護るために殺しあう。
だが、負けが近付いてくると、理性が狂気と化し本能が暴れだす。何を護るのかが分からなくなってくる。いや、護るものがもう失われてしまっているのに、それに気付くことすら出来なくなってしまう。
“戦線から遠のくと、楽観主義が現実に取って代わる。そして、最高意志決定の段階では、現実なるものしばしば存在しない。戦争に負けているときは特にそうだ。”
ジェイムズ・F・ダニガン
戦闘機乗りが戦闘機を駆使して戦うのには1000時間の飛行訓練が必要だといわれていた。だが、学徒出陣により集められた彼らには200時間程度の訓練時間しかなかった。
おそらく。これはおそらくだけれど、海軍の首脳陣たちは彼らを、戦闘機で戦闘させる気は無かったんじゃないだろうか?
戦局と資源事情を鑑みれば、戦闘機乗りを大量に作り出す時間は無い。ならば、ギリギリ戦闘機を飛ばせる程度まで仕込んだ即席パイロットを作り、彼らには爆弾を抱えて敵艦に突っ込んでもらおう。即席パイロットが戦闘を展開した所で勝てるわけが無い。だが、特攻させるなら10に1程度は戦果があるだろう。
個を見れば万死零生の作戦でも、少し大所高所で見れば戦果があったとも言える。
自分で書いていても、自分の思考にゾッとするけれど。
なんて、楽観的で現実離れした発想だろう。
戦争は人殺し合いだ。
戦争は、外交の果てにある、国力の削り合いだ。国力は、資源力であり、戦艦や飛行機の生産力であり、そしてそれらを使う人を指す。中でも、人を削ることは国力の最も効果的な削り方だ。
だから、戦争は人殺し合いなのだ。
日本は戦後70年という節目にいながら、未だにあの戦争に決着を着けきれていない。
70年間もただただ太平洋の片隅に浮かんでいただけだ。
70年間も戦争をせずに済んだのは、そう思い込んでいるだけだ。PKO、イラク派兵で沢山の日本人が死んでいる。
最近の戦争はアウトソーシングが進み、イラク戦争ではアメリカ軍にケータリングをする会社があるそうだ。その会社には民間日本人がいて、実際にイラクで働いていたそうだ。
僕らは、戦争の中にいる。
僕が最も憤りを感じるのは、大人たちの始めた戦争を、自分たちで処理しきれず後世の者たちに引き継がせようとする姿勢なのだ。
「近年、外交状況が悪化したから、もしもの時のため開戦しやすくします。これで国民を護ることが出来ます」と言う。
外交状況を改善できるチャンスは70年間あれば、何度も何度もあったはずだ。それをしなかった所為で、中国、韓国との関係は良くないままだ。
大人がやらなければならないことを、子供たちに押し付けようとしている。
それは学徒出陣にも言えることだ。いや、その時に学ぶべきだったことだ。大人が始めた戦争に、なぜ子供を巻き込んだ?大人だけで解決しなければならなかったはずだ。
藤田暢明少尉という人物がいた。
彼は、神風特攻で戦死した。
彼には睦重という恋人がいた。
二人は結婚した。
彼の出撃後に、睦重さんは花婿のいない結婚式を挙げた。
親族も集まったそうだ。結婚式に反対の者はいなかったそうだ。
その結婚式の写真が残っている。
綺麗な、本当に綺麗な睦重さんの白無垢姿。
でも、その横にいるはずの花婿はいない。
今の問題を次世代に背負わせるとは、こういうことなのだ。
未来を奪い、得られるはずだった幸せを奪い、彼らの間に産まれるはずだった命さえ奪う。
特攻隊員たちは、未来を作るために、今を見つめ、そのとき自分の出来ることの全てをした。
僕たちは彼らを見習う必要がある。保身のためでなく、今、自分に出来ることが何かを考える、ということを。











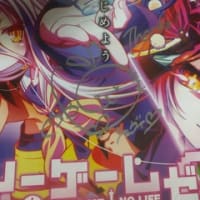

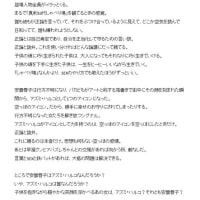
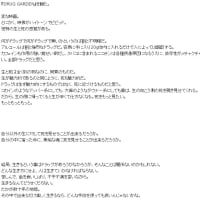





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます