


































今週は
北海道のパートナー企業(株)環境アシストさん
にお招き戴き
北海道のお客様に
サバンナブラン資材のご案内に行ってきました!
・
お話した内容は
「微生物資材(菌態資材)を活用した
肥培設計のガイドラインとオススメ資材」
です。
・
今年の北海道の冬は、
例年よりは
若干気温も高いらしいのですが
それでも気温は氷点下!
路面が凍り、足元も悪く、寒い中、
大勢のグリーンキーパーさん、支配人さんに来ていただき
ありがとうございました!

地元産ROYCEのチョコも
とっても美味しかったです!
北海道は雄大ですね!
雪が溶けたらまた行ってみたいです。
ありがとうございました!!
◆
今回は
季節ごとのオススメの微生物資材(菌態資材)と
菌のえさ、菌のすみか
を紹介しました。
・
まず、
季節ごとの
オススメ微生物(菌態)資材です。
春と秋は
更新作業との相乗効果のある
「デ・サッチャー(15-0-0)」(分解系バチルス菌)
夏は
施薬と相乗効果のある
「コンパニオン(2-3-2)」(抗菌系バチルス菌)
冬は
晩秋施肥と相乗効果のある
「リストア・プラス(3-0-2)」(貯蔵系こうぼ菌)
がオススメです。
・
次に
気候やグリーン面の状況に応じて
菌のえさ や 菌のすみか を選択します。
日照不足の時は
「ターフバイタル・プロ」
(グルタミン酸)
高温と芽数アップには
「エッセンシャル・プラス(1-0-1)」
(ケルプ入りアミノ酸)
乾燥している状況では
「ハイドロ・マックス」
(フミン酸入り浸透湿潤剤)
がオススメです。
◆
是非、来シーズンの資材候補として
ご検討して戴ければ幸いです!
本年も
このブログを読んで戴いてありがとうございました。
来シーズンも
宜しくお願いします!
(^。^)
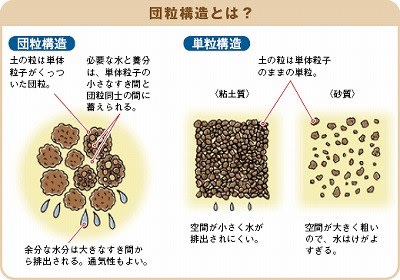
コスト面から目土に 川砂でなく 山砂を使う
テイーの造成や拡幅工事に 山砂を使う
最近は
コースの予算も厳しいので
そうせざるを得ない現場も多いです。
そのような現場で
グリーン面が乾燥しやすかったり
テイーグラウンドの芽数が減ってしまう
という声を耳にする事があります。
◇
「団粒構造」の反対語に
「単粒構造」があります。
「単粒」つまり1種類の粒構造。
ゴルフコースにおいては、
ピュアサンドのみでは 水持ちが悪い
粘土質のみでは 透水性が悪く撥水乾燥する 空相も少なく根張りが悪い
という問題が生じます。
◇
ゴルフコースの地山にある
山砂を目土や客土として使用する場合
地層によっては
シルト質・粘土質を多く含む土もありうる事が厄介です。
◇
造成や芝貼り直後は問題がなくても、
梅雨~夏のような降雨時期、高温時期には、
シルトな土壌は
透水性も悪く、土壌もうみやすく、
また
表層は撥水乾燥しやすく、
何度も芝を張り替える事になってしまいます。

↑ 地山から採取した客土のシルト成分により、芝付きを悪くなった例
◇
なかなか客土を入れ替えるのは困難なので、
土壌を団粒化できる資材を
エアレーションと併用して土壌改良を行ったり、
暗渠排水工事で水はけを改善する
事は大切ですね。
◆
土壌の団粒化には、
☆ グリーン面(刈高のコントロールが必要なターフ)には
「デ・サッチャー」+「ハイドロマックス」がオススメです!
☆ フェアウエイ、テイーグラウンド
(刈高のバラツキに許容範囲が許されるターフ)には
「バイオ8-0-9」がオススメです!
◇
団粒化には「デ・サッチャー」
「デ・サッチャー(15-0-0)」は
古茎根を分解する良性菌3種類を含有し、
新茎根成長のための土壌三相バランスを確立する資材です。
グリーンの透水性を大幅に改善し、
しつこいドライ状態やリングの原因となる撥水層を改善できます。
エアレーション、更新作業と並行して施肥するとたいへん効果的です。

上の写真は
雨が降り出して、5分もするとグリーン面に水が浮いてしまうよう状況(写真左)で、
「デ・サッチャー」を第1週、第3週、第7週にわたり
合計3回施肥した3ヶ月目の土壌(写真右)です。
更新作業と資材を併行使用した結果、ブラックレイヤーが減少し、
土壌が団粒化し、
長く新しい根が成長している事が観察できます。
◇
主成分は
バチルス・ズブチリス(5~55℃で活動)、バチスルメガテリウム(3~45℃で活動)、
バチルス・リヘニフォルミス(15~55℃で活動)のバチルス3種
プロテアーゼ、セルラーゼ、アミラーゼの分解酵素3種類
窒素 15.0%(*85%緩効果性メチレン尿素につき、徒長のリスクはほとんど見られません)
Lアミノ酸 9.5%
等です。
◇
資材「デ・サッチャー」を表層全体に到達させ、
三相(適切な気相と液相)を持続するには
「ハイドロ・マックス」です。

「ハイドロ・マックス」は
北米大陸の砂漠に自生する「ユッカシジゲラ」から抽出した
100%天然の浸透湿潤資材です。
さらに、
気相を持続する フミン酸2%含有で、
三相バランスを確保、持続する資材です。
資材自体が良性菌のえさとなる
100%有機の資材です。
主な成分は
ユッカシジゲラ抽出物 90%以上
フミン酸(天然レオナルダイト由来)2%
です。
「ユッカシジゲラ」とは

主に北米大陸に自生する植物で、
ステロイド・サポニン と ポリフェノールを豊富に含みます。

北米の原住民インデイアンが
シャンプー、すり傷治療、皮膚炎治療等の
薬用として活用していたといわれます。

「ハイドロ・マックス」の主な効能は
・土壌三相(固体/液/気)バランスを理想的に持続します。
・土壌の乾燥・固結を修復します。ドライスポットを抑制します。
・エアレーション後の乾燥、切り口からの病害侵入から根茎を守ります。
◆
宜しく、お願いします!
(^^)

6月7日(水)
気象庁は
四国、中国、近畿、東海、関東甲信地方の「梅雨入り」を発表しました。
本来であれば、
梅雨前線の影響を受けやすく、雲の広がる日が多くなるはずですが、
梅雨入り以降、
関東地方などでは、
そこそこ晴天で、南西方向からの風も強く、
フェアウエイなどが乾燥し、ダメージを受けています。
従来の「梅雨」とは思えません!
◇
ここ数年は 季節・気候の推移が予想しにくく、
次の1手を決断しなければならない
グリーンキーパーさんにとっては
厳しい気象環境が続きます。
◇

「ゴルフ場セミナー誌」で記事などを執筆されている
マイカ・ウッズ氏によれば、
グリーンキーパーさんが
管理(コントロール)できる6つの要素は
「光(葉身)」「空気(気相)(更新作業)」「水(散水)」
「肥料(肥培計画)」「病害虫(施薬)」
と著書「芝草科学とグリーンキーピング」で解説されています。

◇
たしかにそうなのですが、
昨今は、15~20年くらい前と違い、
コース管理の人員も少なく、
限られた予算の中で、
どのテーマを優先させて行うかを
決断しずらい事が多いと思います。
異常気象傾向のここ数年では
尚更に、「次の一手」を迷ってしまいます!
◆
そこで
参考になると思われるのが
「24節気(暦便覧)」
と
「72候(貞享暦:江戸時代に農作物の収穫拡大の為に作られた暦)
です。
季節の推移=太陽と地球の角度 であるので
太陽と地球の角度(15度)x24節気=360度(1年)
太陽と地球の角度(5度)x72候=360度(1年)
と考えます。
標高や地域によって 冬や夏の長い短いはあっても
24節気や72候(貞享暦)の順番を
逆行するような季節の推移はないので
1週後にどのような季節になるのか
双六(スゴロク)のように考える事はできると思うのです。
◆
私なりに
お客様(キーパーさん)達が優先させている
季節ごとのテーマ(優先課題)を
24節気ごとに 整理してみました。
1)「立春(2/4)」ごろ~「穀雨(4/20)」ごろ
「立春(2/4)」(春の初め)
「穀雨(4/20)」(穀雨とは、穀物成長を助ける雨)
テーマ:「根数と芽数」
2)「立夏(5/6)」ごろ~「芒種(6/6)」ごろ
「立夏(5/6)」(夏の気配が感じられる頃)
「芒種(6/6)」(芒ーのぎーを持った植物の種をまく頃)
テーマ:「表層透水性」
3)「夏至(6/21)」ごろ~「大暑(7/23)」ごろ
「夏至(6/21)」(一年で一番昼が長く夜が短い日)
「大暑(7/23)」(快晴が続き気温が上がり続ける頃)
テーマ:「病害と施薬」
4)「立秋(8/7)」ごろ~「白露(9/8)」ごろ
「立秋(8/7)」(初めて秋の気配が現れる頃)
「白露(9/8)」(大気が冷えて来て、露ができはじめる頃)
テーマ:「水管理」
5)「秋分(9/23)」ごろ~「小雪(11/22)」ごろ
「秋分(9/23)」(昼夜の長さがほぼ同じになる頃)
「小雪(11/22)」(わずかながら雪も降り始める頃)
テーマ:「晩秋施肥」
6)「大雪(12/7)」ごろ~「大寒(1/20)」ごろ
「大雪(12/7)」(雪が激しく降り始める頃)
「大寒(1/20)」(寒さが最も厳しくなる頃)
テーマ:「固結・乾燥、凍害・霜害」
◆
以上です。
よろしくお願いします!
(^。^)

4月5日頃は 24節気の「清明(せいめい)」
<万物がすがすがしく明るく美しいころ>
とあります。
また 72節気では「玄鳥至(げんちょういたる)」
<ツバメが南からやってくる頃>とあります。
昔の農業暦では
桜のつぼみが ほころぶ頃、稲作のモミを撒いたといいます。
「遅霜」の心配がなくなる頃だから、だと思われます。
そろそろ本格的な春がやってきそうです!
スポーツターフの1年もいよいよ開幕ですね!
◆
年間のコース管理作業(グリーン)には
ターフの成長を保つための「施肥」以外に
大きく分けて3つの作業があると思います。
1)病害を抑制するため、菌態バランスを健康に保つための「施薬」
2)三相バランスを保つための「エアレーション」
3)ターフクオリテイを保つための「グルーミング、サッチング」と「薄目砂」
です。
これらの作業をタイムリーに行う事が、
高いターフクオリテイを持続する鍵となると思うのですが、
昨今は、気象不安定、日照不足、ゲリラ豪雨、猛暑、
秋の長雨 等など
気象傾向がたいへん予測しにくい時代なので
各作業工程と相乗効果のある資材を併用し、
この一年を成功させていただきたいと思っています!
◆
各作業工程別に、相乗効果を発揮する
オススメの資材があります!
1)「施薬」と相乗効果のある資材は
「コンパニオン」と「ターフバイタル・プロ」です!
「コンパニオン」

善玉菌バチルスGB03が根茎を病害から守ります。
表層の有機残渣を分解しながら、
自ら生み出す抗生物質で病害の菌核を叩きます。
新根の成長を促すオーキシン様物質も生成します。
殺菌剤との相乗効果の高い資材なので
混合散布がたいへん効果的です。
菌態バランス(B/Fバランス)を整える資材の決定版です!
 ←バチルスGB03が病害を阻害します。
←バチルスGB03が病害を阻害します。
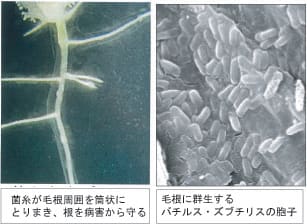 ←バチルスコロニーが根茎周囲を病害から守ります。
←バチルスコロニーが根茎周囲を病害から守ります。
「ターフバイタル・プロ」

日照不足下で光合成(炭酸同化作用)できにくい状況でも、
低温や高温で窒素吸収できにくい状況でも
タンパク質合成を代行する「グルタミン酸」が活性を向上し、持続します!
アミノ酸のトップメーカー味の素(株)の製品です。

←光合成不足による炭酸同化作用の低下、低温や高温による窒素同化の低下を
「グルタミン酸」のタンパク質合成が代行します。

←アスリートのための「アミノバイタル」と同じメカニズムを採用しています。
2)「エアレーション」と相乗効果のある資材は
「ブランXエックス」または「デ・サッチャー」です。
「ブランXエックス」は
グロース社の代表的な床資材である
「デ・サッチャー」、「ハイドロ・マックス」、
「エッセンシャル・プラス」
を1/3ずつブレンドした資材です。
・
撥水層を分解して
ドライ相を改善する「デ・サッチャー」が1/3
主成分は
床砂の表面に付着した有機残渣や
古茎根を分解する良性菌3種類と分解酵素3種類”です。
+
グリーン面の潤いを持続し、乾燥を抑制、
新根茎周囲の三相バランスを持続する
「ハイドロ・マックス」が1/3

「ハイドロ・マックス」は100%天然の浸透資材で、
主成分は
ユッカシジゲラ抽出物90%→ステロイドサポニンの浸透剤効果
フミン酸(天然レオナルダイト由来)2%→気相持続効果
 ←「フミン酸」で三相バランス持続!
←「フミン酸」で三相バランス持続!
+
新根新芽の成長を促進する
「エッセンシャル・プラス」が1/3

主成分は
アミノ酸 2.75%
フミン酸 7.0%
ケルプ抽出物(オーキシン様物質)
ジベレリン酸
リグニン、セルロース繊維
単糖、二糖類(トレハロース)、
ビタミンB2 ビタミンB6
です。
3)「グルーミング、サッチング」と「薄目砂」
と相乗効果のある資材
グルーミング、サッチング後に、
葉先を固くしボールの転がりを良くするには
確かに ケイ酸やカルシウム資材が効果的ですが、
ターフの腰をしっかりさせるK(カリウム)や
徒長(茎の軟弱徒長)を抑制するMg(マグネシウム)は
細く、アップライトな葉身をつくり、
芽数をアップさせる上で
さらに大切な要素と思われます。
ケイ酸+K 資材の「グリーンスピードSi(0-2-7)」や
カルシウム+Mg資材の「カル・マグ・マックス(7-0-3)」
はたいへん相乗効果の高い資材です。
同時に、薄目砂+PK資材は
芽数を増やし、
よこ根によるコンパクションを向上させます!
「ミスト12号(3-18-18)」は
気象不安定でも、吸収の良いPK資材として好評可です!
◆
よろしくお願いします!
(*´∀`*)

1月20日「大寒」を過ぎ、
もうすぐ、2月3日「節分」(2月4日「立春」)です。
早朝の気温はマイナスの日も多く、
北風の冷たい毎日が続いていますが、
一方で、
日もだいぶ長くなり、
昼間の日照も少しずつ強くなり、
常盤自動車道脇のスギの木が
花粉をたわわに蓄えて始めているのを見ると
春の遠くない事がうかがえます。
◆
グリーン面では
この先の ひと雨ごとに
表層の固結・乾燥が緩和され、
1月20日「大寒」以降は白根の発根が旺盛になり、
2月18日「雨水」以降のよこ根の成長
につながります。
「大寒」~「雨水」の時期の
根茎周囲の三相バランスが
春の新根の伸長と
芽出しを向上させると思われます。
◆
秋においては、
まず、夏でダメージを受けたよこ根を
亜リン酸やリン酸(P)で戻し、
さらに、たて根をリン酸(P)で成長させ、
根数→芽数を整えます。
晩秋には カリウム(K)の施肥により
冬越しのための貯蔵糖分の蓄積を促す
肥培が効果的であるように、
春においては
まず、早春の白根やよこ根を
気候不順でも吸収するタイプのリン酸(P)でスタートさせ、
その後、
鉄系(Fe)で下葉を代謝させると共に、
窒素(N)の供給で芽出しを促進し、
一旦、芽だしを充実させた後、
更新作業などとともに
窒素(N)+リン酸(P)の供給で、たて根(根量)を伸長させ
さらなる芽数につなげてゆく事が
効果的と思われます。
◇
おすすめの資材です。
まず、2~3月の
早春の白根、
初期のよこ根の成長を充実させるのに
効果的なミストは
「ミスト12号(3-18-18)」
です。

分子の鎖の長い 緩効性リン酸12%
+亜リン酸6% なので、
晴天でも、雨天でも約2週間に渡り、
表層土壌に留まり、
無駄なくリン酸を吸収するスペックです。
◇
次に、3~5月の
根数充実(よこ根→たて根)、
芽数アップ、
更新作業後の穴のふさがり や
播種後の発芽・発根には
メチレン尿素+水溶性リン酸の
「ミスト9号(8-32-5)」
が好評価です。

◆
是非、試してみて下さい!
(^。^)

この先
一年間の肥培を考えると
1)スタート前の三相バランス と
2)春秋の日照不足対策
が大きなテーマになると思います。
◇
最近は、
従来の大きなテーマであった
「夏越し」=「高温多湿病害への対策」
に関しては、
油断できないテーマですが、
かなり有効な対策が講じられてきているようです。
まず、かなり薬剤の性能が向上し、
その投入時期やローテーションに関しても
有効な情報が共有され、
ダラー、リング、ピシウムに関しては ほとんど対策が取られ、
炭疽病や細菌病に関しても
ここ2~3年有効な情報が更新されているようです。
さらに、扇風機やサブエア等の設備導入で
表層の加湿を回避されているコースも増えてきました。
◇
しかし、
近頃のキーパーさん達の声を聞くと
「春らしい春でなかったのでコーライ芝の立ち上がりが鈍く、
テイーや外周等ストレスのかかる
コーライ部分のダメージとその修復に手間がかかった。」
「秋の日照不足で、
秋の更新作業から、逆に活性が落ち、
その回復が晩秋までかかり、
高いターフクオリテイをつくるタイミングがなかった。」
というような声を複数耳にします。
◇
整理して考えると
まず、
春や秋のスタート前の三相バランス
= 酸欠の回避
→ 新根の(白根の段階での)成長環境確保
つまり、
1)旧暦の正月 2/1~10 頃 固結・乾燥を緩和する
2)旧暦の七夕 8/7~15頃 加湿・酸欠を緩和する
事が重要といえそうです。
次に
地球温暖化が原因なのか、
四季の変化がはっきりせず、春らしい春や秋らしい秋が
なくなってきています。
3)早春の冷たい長雨(2月/下旬~3月前半)と日照不足
→特にコーライ芝の立ち上がりに悪影響
4)秋の長雨(9/15~10/15頃)と日照不足
→特にベント芝の更新作業からの戻りに悪影響
この 4つの時期をどのようにフォローするかで、
ダメージを最小限に抑制すると共に
高いターフクオリテイを創る時間的余裕を
確保できるような気がしています。
◆
よろしくお願いします!
(^。^)

グリーンの健全な
成長を持続する上で、
リン酸(P)やカリウム(K)は
欠かせない要素ですね。
タイムリーな使い方としては
春にP、梅雨にK、夏にPを
積極的に施肥するのが
有効ではないかと思います。
いわば、「P-K-P」でいかがしょうか。
●
★春~梅雨明けまでの
新根成長(よこ根→たて根)、
芽数アップ、
更新作業の穴のふさがり や
播種後の発芽・発根には
やはり、
水溶性リン酸 が有効です。

グロース社の資材でいえば
「ミスト9号(8-32-5)」
です。
●
★梅雨時期、
温度・湿度が出てくる
梅雨時期~梅雨明け頃は
徒長を抑制し、
その分、
養分を夏越しの為の
地下部成長に使い、
日照不足で
軟化しやすい葉身に対して
ターフの「こし」をしっかりさせ、
病害へ抵抗する
細胞の強さを持たせるには
やはり
カリウムの摂取が欠かせません。
グロース社の資材でいえば
「ミスト6号(8-4-24)」です。

●
★そして、
夏(梅雨明け~9月上旬ごろ)は

生育サイクル上避けられない、
「根あがり」をなるべく抑制し、
厳しい高温状態でも
栄養摂取を持続する為に、
また、多湿状態で
「根腐れ」も起こるので、
なるべく根数を保つ上で
リン酸は欠かせません。
夏場のリン酸としては、
葉身からの吸収が大きく期待でき、
抗菌効果(ホセチル様効果)のある
亜リン酸が
たいへん効果的です。
グロース社の資材でいえば
亜リン酸を含有する
「ミスト10号(0-29-26)」

&
亜リン酸+緩効性リン酸+柳エキス 含有、
コストパフォーマンスの高い
「ミスト12号(3-18-18)」

がおすすめです!
是非試してみて下さい!
(^。^)
ターフクオリテイの指標として
「転がり」と「コンパクション」があります。
最近ではトーナメントのTV中継でも表示され
一般のプレーヤーも
グリーン転がりや コンパクションを意識するように
なってきました。

季節によりターフの活性も変わってくるので
一般のプレーヤーから のべつまくなしに
「スピードは何フィート?」「コンパクションは山中式でいくつ?」
などと、聞かれると、
「こっちの苦労も知らないで。。。。」と
つい「いらっ」としてしまいますね。(笑)

なるべく、刈高的には無理をせず、転圧を少なめにして
ターフに負担をかけないで、
転がりの良さとコンパクションは持続できたら!と思うんです。

芝自体から見れば、
(刈高、刈込方向、目砂等、「転がり」の要素は様々ありますが)
コンパクションは =「よこ根」の張り、
転がりの1+3要素は
「芽数(芝密度)」と
「硬く」「細く」「アップライト」な葉身
と思います。

✩「アップライト」な葉身は
酸欠、固結していない、
三相バランスの良い表層に生長した
まっすぐな茎から伸びる葉でつくられると思います。
(3/27記事で紹介しました。)
✩葉の「硬さ」に関しては
葉身の上半分(先っちょ)の「硬さ」は
「ケイ酸」や「カルシウム」の適宜な施肥で確保でき、
葉身の下半分(ターフのこし)の「硬さ」は
「カリウム」をいつも欠乏させない事で
成り立つと思います。
✩「コンパクション」は
しっかりした「よこ根」があれば、
転圧なしでも21~23は出ると思われます。
✩そのしっかりした
「よこ根」を「サッチング」で裁き、

「目砂(少量・多回数)」すれば
ベント芝は「分げつ(クリーピング)」し
「芽数」を増やします。
まさに「根数」=「芽数」です。
「芽数」が増え、株数が増えると、
施肥量が一定でも、
1株あたりの配当養分が減りますので、
ターフは自ら葉身を細くすると思うのです。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
おすすめの資材は
サッチングや薄目砂との相乗効果の高い
「ミスト12号(3-18-18)」+「グリーンスピードSi(0-2-5)」です。
「ミスト12号(3-18-18)」は

春の気候不順時にも効果的です!
晴天時は 6%の亜リン酸を葉身から吸収し、
12%は 分子の鎖の長い 緩効性リン酸 なので、
10~2週間に渡り、表層土壌に留まり、無駄なくリン酸を吸収し、
「よこ根」を生長させ、 「コンパクション」を向上させます。
「グリーンスピードSi(0-2-5)」は

7%のケイ酸を 2%の亜リン酸と共に素早く吸収し、
葉身を硬く、細くスリムにします。
5%のカリウムは「ターフのこし」をつくります。
ケイ酸とカリウムが同時に地上部の動きを抑制するので
薄目砂の後の分げつも旺盛になり、芽数(株数)がアップします。
是非、試してみてください!
よろしくお願いします! (^。^)
最近は 10~20年前に比べると
より多くのプレーヤーが
グリーンのクオリテイや転がりに
注目し、期待しているような気がします。

トーナメントや競技会でなくても、どんなレベルでも(笑)、
相応の転がりを期待しているような気がします。
昨今の40,000人/18Hを超える来場客数による踏圧や
異常な猛暑を考えれば、無理は禁物なのですが、
できるだけ、ターフの生育に無理をかけないようにしながら
転がりの良さとコンパクションは持続できたら!と思うんです。

芝自体から見れば、(刈高、刈込方向、目砂等の要素は様々ありますが)
転がりの3要素は
「硬い」「細い」「アップライト」な葉身
と思います。

「アップライト」な葉身は
「アップライト」=「まっすぐな茎」から成長していると思うのです。
まっすぐな茎は
透水性の良い、酸欠・固結していない表層に成長します。
(梅雨時や日陰などで、踏圧のかかる部分の
表層のソッドサンプラーで、斜めに茎が成長(徒長)し、
その延長上に傾いて成長している葉身を見る事があります)
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
おすすめの資材は
「デ・サッチャー(15-0-0)」です。
「デ・サッチャー(15-0-0)」は 古茎根を分解する良性菌3種類 です。
透水性を向上させ、
新茎根成長のための 土壌三相バランスを確立持続する資材です。
もちろん、グリーンの透水性も大幅に改善します。
この先、5月中旬や7月中旬に心配な
ドライやリングの原因となる撥水層も改善できます。

更新作業との相性もよく、施肥後は、新根も良く成長し、
コアが早くふさがる利点もあります!

是非、試してみてください! (^。^)
最近は
地球温暖化 や 異常気象 という言葉をよく聞きます。
とても 気象の流れは予想しにくく、
グリーン面は
次から次へと 様々な過酷な状況に直面し、
次の一手に迷う事も多くあると思います。
江戸時代に 旧暦24節気をさらに細かく区切り、
農業の生産性向上のために整理されたといわれる
72候(参考URL: http://www.nnh.to/yomikata/72kou.html)
<太陽と地球の角度(15°)x24節気=360° / 太陽と地球の角度(5°)x72候=360°>
を読んで行くと
肥培管理・施薬・更新作業・水管理にとってのヒント
が見えてくるような気がしました!
季節別のグリーン面のテーマ と
気になる72候の言葉は
1)春のテーマ「根」をつくる(活性)(2/4~3/31ごろ)


2月4日ごろ「東風解凍」 (とうふうこおりをとく)
2月19日ごろ「土脈潤起」 (つちのしょううるおいおこる)
3月1日ごろ「草木萌動」 (そうもくめばえいずる)
2)表層透水性を確保する(更新作業)(4/1~6/10ごろ)

4月25日ごろ「霜止出苗」 (しもやみてなえいずる)
5月15日ごろ「竹笋生」 (たけのこしょうず)
3)高温多湿系の病害を抑える(施薬)(6/11~8/3ごろ)


6月11日ごろ「腐草為蛍」 (ふそうほたるとなる)
7月29日ごろ「土潤辱暑」 (つちうるおいてじょくしょす)
8月3日ごろ「大雨時行」 (たいうときどきおこなう)
4)乾燥を抑える(水管理)(8/7~9/20ごろ)


8月7日ごろ「涼風至」 (りょうふういたる)
8月13日ごろ「寒蝉鳴」 (ひぐらしなく)
5)晩秋施肥(9/下旬~11/12ごろ)


10月23日ごろ「霜始降」 (しもはじめてふる)
11月12日ごろ「地始凍」 (ちはじめてこおる)
です。
よろしくお願いします!
(^。^)