
今年の梅雨は「6月弱、7月強」らしく
これまで6月は降雨量の少ない「空梅雨」傾向でしたが、
この先、梅雨の後半~梅雨明けまでには
そこそこ雨も降るものと思われます。
◇

しかし、ここ数年の傾向ですが
6~9月の雨に関して、
「ゲリラ豪雨」的な雨が目立ちます。
最近では、
6月21日、日本列島は梅雨前線を伴った低気圧の影響を受け、
各地で激しい雨が降りました。
静岡県内も記録的な大雨となり、
三十七万一千人に避難勧告が発令されました。
●
6月25日には
和歌山県で
1時間110ミリの記録的短時間大雨が観測されたそうです。
◇
この先、気温・湿度ともに上昇してくるので
グリーン面に殺菌剤を散布する機会も多いと思います。
しかし、集中降雨による薬剤の流亡には充分注意が必要です。
また豪雨の翌日に
表層に湿度が高い状態で日中温度が上昇すれば
最も病害侵入しやすい状況となるので
*表層の気相確保、透水性持続(エアレーション等)
*表層の加湿回避(扇風機等)
*殺菌剤のローテーションと充分な在庫
*7月7日「温風至(おんぷういたる)」頃からの
積乱雲の発生状況
などに留意して
6月下旬~8月下旬の
施薬の時期を乗り切っていただければ幸いです!
◇
オススメの資材があります!
「コンパニオン」+ケミカル殺菌剤 です。

「コンパニオン」は 善玉菌バチルスGB03が
根茎周囲に筒状のコロニーをつくり、根茎を病害から守る資材です。
★雨で殺菌剤が流亡して
根茎周囲に殺菌剤が届かない場合もあると思います。
★不透水層の下で、殺菌剤が届かなかった根茎周囲にピシウム菌などが
残存している場合もあると思います。
そんな場合に、
自ら生み出す抗生物質で
ピシウムや炭疽、細菌病等の病害の菌核を破壊・疎外します。
殺菌剤との相乗効果の高い資材なので
混合散布がたいへん効果的です。
高温多湿な時期の
菌態バランス(B/Fバランス)を整える資材の決定版です!
 ←バチルスGB03が病害を疎外します。
←バチルスGB03が病害を疎外します。
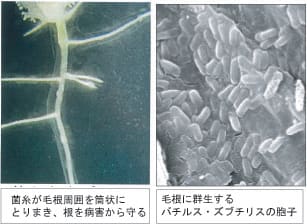 ←バチルスコロニーが根茎周囲を病害から守ります。
←バチルスコロニーが根茎周囲を病害から守ります。
◆
よろしくお願いします!
(^。^)











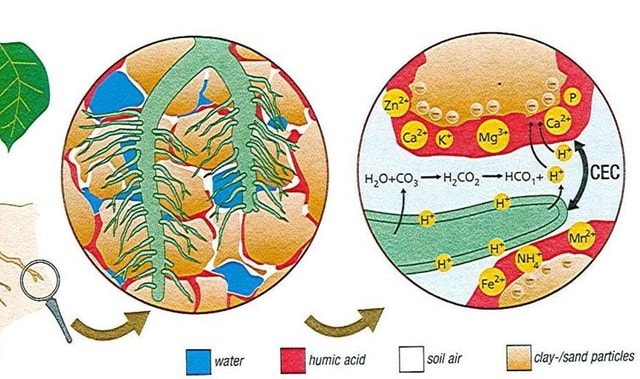







 ←6/21「乃東枯」(夏枯草ナツカレクサの枯れる頃)
←6/21「乃東枯」(夏枯草ナツカレクサの枯れる頃) ←関東地方
←関東地方 ←東海地方
←東海地方 ←近畿地方
←近畿地方








 ←ユッカシジゲラ
←ユッカシジゲラ





