「武士道の言葉」第38回 大東亜戦争・祖国の盾「特攻」その1 (『祖国と青年』27年9月号掲載)
男の崇高な美学
いさぎよく敵艦に体当たりした特別攻撃隊員の精神と行為のなかに男の崇高な美学を見るのである。(アンドレ―・マルロー)
昭和四十九年夏、元リヨン大学客員教授で特別操縦見習士官三期出身の長塚隆二氏は、フランス文化相を務めた作家のアンドレ・マルロー氏を訪問、マルロー氏は特攻隊について次の様に語られたと言う。
「日本は太平洋戦争に敗れはしたが、そのかわり何ものにもかえ難いものを得た。これは、世界のどんな国も真似のできない特別攻撃隊である。ス夕―リン主義者たちにせよナチ党員たちにせよ、結局は権力を手に入れるための行動であった。日本の特別攻撃隊員たちはファナチックだったろうか。断じて違う。彼らには権勢欲とか名誉欲などはかけらもなかった。祖国を憂える貴い熱情があるだけだった。代償を求めない純粋な行為、そこにこそ真の偉大さがあり、逆上と紙一重のファナチズムとは根本的に異質である。人間はいつでも、偉大さへの志向を失ってはならないのだ。」
「フランスはデカルトを生んだ合理主義の国である。フランス人のなかには、特別攻撃隊の出撃機数と戦果を比較して、こんなにすくない撃沈数なのになぜ若いいのちをと、疑問を抱く者もいる。そういう人たちに、私はいつもいってやる。《母や姉や妻の生命が危険にさらされるとき、自分が殺られると承知で暴漢に立ち向かうのが息子の、弟の、夫の道である。愛する者が殺められるのをだまって見すごせるものだろうか?》と。
私は、祖国と家族を想う一念から恐怖も生への執着もすべてを乗り越えて、 いさぎよく敵艦に体当たりをした特別攻撃隊員の精神と行為のなかに男の崇高な美学を見るのである。」
自虐史観に侵された日本人より、仏人の方が特攻隊の本質を言い当てている。特攻隊を志願した多くの青年達、彼らの真情は、残された膨大な手紙や日記や遺書を繙けば自ずと伝わって来る。そして、この様な潔い青年達が、七十年前の日本には多数居た事に改めて感慨を深くする。
自己犠牲
セルフ・サクリファイスといふものがあるからこそ武士道なので、身を殺して仁をなすといふのが、武士道の非常な特長である。(三島由紀夫「武士道と軍国主義」)
昭和十四年生れの三島由紀夫氏は特攻隊に散った青年達と同世代だった。三島氏は生前、江田島の教育参考館を訪れ、特攻隊員の遺書の前で釘付けになり涙を流されていたと言う(岡村清三氏の話)。
三島氏は昭和四十一年一月に書いた「日本人の誇り」の中で、「私は十一世紀に源氏物語のやうな小説が書かれたことを、日本人として誇りに思ふ。中世の能楽を誇りに思ふ。それから武士道のもつとも純粋な部分を誇りに思ふ。日露戦争当時の日本軍人の高潔な心情と、今次大戦の特攻隊を誇りに思ふ。すべて日本人の繊細優美な感受性と、勇敢な気性との、たぐひ稀な結合を誇りに思ふ。この相反する二つのものが、かくもみごとに一つの人格に統合された民族は稀である。」と記している。
更には、昭和四十五年に語った「武士道と軍国主義」の中で、「セルフ・リスペクト(自尊心)と、セルフ・サクリファイス(自己犠牲)ということが、そしてもう一つ、セルフ・リスポンシビリティー(責任感)、この三つが結びついたものが武士道である。」と述べ、「セルフ・サクリファイスといふものがあるからこそ武士道なので、身を殺して仁をなすといふのが、武士道の非常な特長である。」と話している。
自尊心・責任感、そして自己犠牲、特に自己犠牲こそが武士道の武士道たる所以であり、三島氏はその最たるものを特攻隊の青年達に見出していた。
三島由紀夫氏と親交のあったアイヴァン・モリス氏は『高貴なる敗北 日本史の悲劇の英雄たち』を著し、特攻隊の自己犠牲の行為を、日本の精神史の中で位置づけた。この本では、日本武尊・捕鳥部万・有馬皇子・菅原道真・源義経・楠木正成・天草四郎・大塩平八郎・西郷隆盛を扱い、最後を「カミカゼ特攻の戦士たち」で締めている。モリスは言う「特別攻撃隊員たちの場合、背後には武士の伝統がある。また日本という国のため生命を捨てた英雄精神がある。」と。
戦後教育は、生命尊重=自己保全のみを教え、自己犠牲を忌み嫌い、対極にある特攻隊を誹謗し、貶めて来た。だが、国家社会にとって、共同体の為の自己犠牲の精神は崇高な事であり、かつ不可欠なのだ、眼に見えぬ自己犠牲によって社会は支えられているのだ。今日、東日本大震災等の体験によって漸く、真実を直視する眼が養われつつある。
志願から始まった特攻
戦隊長、敵空母群を特攻しましょう。(比島・飛行第三一戦隊「戦闘会議」)
終戦七十年の今年、母校の済々黌同窓会でも同窓英霊顕彰祭が行われた。多士会館(同窓会館)には十年前に慰霊碑が建立され、その際に同窓十七柱の英霊に関する資料が小冊子にして配られており、その中に特攻ゼロ号の話がある。
特攻隊の編成と出撃は昭和十九年十月二十日となっている。ところが、その一か月前の九月十三日早朝、小佐井武士陸軍中尉(済々黌昭和十四年卒)と山下軍曹の隼二機は、百瓩爆弾を装着して、レイテ東方の敵機動部隊空母に向けて特攻攻撃を行っている。事情はこうである。
小佐井中尉は昭和十九年六月に中部比島ネグロス島の東北端のフアブリカ基地に展開、飛行第一中隊の第二小隊長を務め、隼戦闘機が愛機だった。九月十二日に、敵機動部隊のネグロス島攻撃が予想され、哨戒中に攻撃から帰還中の敵グラマン6F四十機、ノースアメリカ七十機と遭遇、中隊は敵十七機を撃墜した。
その日の夜、朝の戦闘体験から戦闘会議を飛行隊員全員で開いて議論した。その結果「敵のグラマン6Fは最高速度や旋回性能は隼と大差ないが、巡航速度から最高速度になる時間と上昇力には格段の差がある。敵機は二〇ミリ機関砲四門・十三ミリ機関砲四門に対し我が機は十三ミリ二門のみ。敵機の操縦席は厚い鋼板で囲まれ、タンクには厚い防弾装置があり中々撃墜できない。これらの現実と本日の戦闘体験により、敵との正面真面目の空中戦は、機数・性能・装備そのいずれの見地からも勝つ事は不可能と思われる。尚、軍司令部偵察機の報告によれば敵機動部隊は夜間黎明には哨戒護衛飛行は行っていない。」
そこで、結論として全員異口同音に「戦隊長、敵空母群を特攻しましょう。我々はもともと軽爆隊から襲撃隊となり戦闘隊となったのですから、超低空や急降下爆撃には習熟しています。この基地で戦っても全滅するのみです。また退避しても五十歩百歩です。それならむしろ我々は日本の国民に対して、愛機の戦闘機に爆弾をつけて体当たりしても戦っている姿を見せるのが、我々の任務でしょう」と述べた。
西戦隊長が特攻志願を募ると全員参加を希望。そこで師団司令部に電話で許可を求めるが許可が降りない。二時間に亘る声涙降る懇願の結果、マニラ湾で超低空艦船攻撃訓練を受けた小佐井中尉と山下軍曹二名のみ特攻の許可が降り、早朝五時に二機が出撃したのだった。
特攻の歴史の記憶が日本を甦らせる
後世において、われわれの子孫が、祖先はいかに戦ったか、その歴史を記憶するかぎり、大和民族は断じて滅亡することはないであろう。(大西瀧治郎海軍中将が報道班員・新名丈夫氏に語った言葉)
統率の邪道とも言える特攻作戦を正式に採用し「特攻隊生みの親」と称されたのが大西瀧治郎海軍中将である。何故、大西中将は特攻作戦を採用したのだろうか。
ミッドウェー海戦の敗北以来、熟練パイロットの減少が続き、飛行時間の短い戦闘機乗りが増加していた事。更には開戦当時圧倒的な優位を誇る戦闘機だったゼロ戦(海軍)や隼(陸軍)に勝る性能を持つグラマンなどが登場し、空中戦での戦果が期待できなくなりつつあった事。その様な中、現場から特別攻撃の要望が起こり、体当たり攻撃を実行する者達が出て来た事、などが上げられる。
実際、特攻は当初それ迄に無い画期的な戦果を挙げた。昭和十九年十月二十五日のレイテ海戦からフィリピン海域での戦闘が終わる二十年一月三十一日までの戦果は、わが軍の損失(特攻機378機、護衛機102機)に対し、敵の損失は、轟沈16隻(護衛空母2、駆逐艦3、水雷艇1、その他10)損傷87隻(大小空母22、戦艦5、重巡洋艦3、軽巡洋艦7、駆逐艦23、護衛駆逐艦5、水雷艇1、その他21)というものであった。
しかし、大西はこの作戦を展開しても戦況を覆す事は至難の業であると考えていた。大西は日本の将来を見据え、歴史を相手にして決断したのだった。『別冊一億人の昭和史 特別攻撃隊』には大西中将が第一航空艦隊司令部付報道班員・新名丈夫氏に語った言葉として「もはや内地の生産力をあてにして、戦争をするわけにはいかない。戦争は負けるかもしれない。しかしながら後世において、われわれの子孫が、祖先はいかに戦ったか、その歴史を記憶するかぎり、大和民族は断じて滅亡することはないであろう。」と紹介されている。
祖国に危難が迫った時、それに身命を賭して勇躍と立ち向う青年が陸続と生れて来るならば国家は守られる。だが、わが身可愛さのみで逃亡する者ばかりであったなら、他国に隷従するしかない。国家の独立とはその様にしてしか守られない。その勇気を抱く事を歴史は訴えているのだ。終戦七十年の八月十五日には、例年にも増して多くの人々が靖国神社や各県の護国神社に参拝した。それも若い人々が多かった。その姿の中に日本の未来があり、無言の内に他国に対する大いなる抑止力を示しているのである。
男の崇高な美学
いさぎよく敵艦に体当たりした特別攻撃隊員の精神と行為のなかに男の崇高な美学を見るのである。(アンドレ―・マルロー)
昭和四十九年夏、元リヨン大学客員教授で特別操縦見習士官三期出身の長塚隆二氏は、フランス文化相を務めた作家のアンドレ・マルロー氏を訪問、マルロー氏は特攻隊について次の様に語られたと言う。
「日本は太平洋戦争に敗れはしたが、そのかわり何ものにもかえ難いものを得た。これは、世界のどんな国も真似のできない特別攻撃隊である。ス夕―リン主義者たちにせよナチ党員たちにせよ、結局は権力を手に入れるための行動であった。日本の特別攻撃隊員たちはファナチックだったろうか。断じて違う。彼らには権勢欲とか名誉欲などはかけらもなかった。祖国を憂える貴い熱情があるだけだった。代償を求めない純粋な行為、そこにこそ真の偉大さがあり、逆上と紙一重のファナチズムとは根本的に異質である。人間はいつでも、偉大さへの志向を失ってはならないのだ。」
「フランスはデカルトを生んだ合理主義の国である。フランス人のなかには、特別攻撃隊の出撃機数と戦果を比較して、こんなにすくない撃沈数なのになぜ若いいのちをと、疑問を抱く者もいる。そういう人たちに、私はいつもいってやる。《母や姉や妻の生命が危険にさらされるとき、自分が殺られると承知で暴漢に立ち向かうのが息子の、弟の、夫の道である。愛する者が殺められるのをだまって見すごせるものだろうか?》と。
私は、祖国と家族を想う一念から恐怖も生への執着もすべてを乗り越えて、 いさぎよく敵艦に体当たりをした特別攻撃隊員の精神と行為のなかに男の崇高な美学を見るのである。」
自虐史観に侵された日本人より、仏人の方が特攻隊の本質を言い当てている。特攻隊を志願した多くの青年達、彼らの真情は、残された膨大な手紙や日記や遺書を繙けば自ずと伝わって来る。そして、この様な潔い青年達が、七十年前の日本には多数居た事に改めて感慨を深くする。
自己犠牲
セルフ・サクリファイスといふものがあるからこそ武士道なので、身を殺して仁をなすといふのが、武士道の非常な特長である。(三島由紀夫「武士道と軍国主義」)
昭和十四年生れの三島由紀夫氏は特攻隊に散った青年達と同世代だった。三島氏は生前、江田島の教育参考館を訪れ、特攻隊員の遺書の前で釘付けになり涙を流されていたと言う(岡村清三氏の話)。
三島氏は昭和四十一年一月に書いた「日本人の誇り」の中で、「私は十一世紀に源氏物語のやうな小説が書かれたことを、日本人として誇りに思ふ。中世の能楽を誇りに思ふ。それから武士道のもつとも純粋な部分を誇りに思ふ。日露戦争当時の日本軍人の高潔な心情と、今次大戦の特攻隊を誇りに思ふ。すべて日本人の繊細優美な感受性と、勇敢な気性との、たぐひ稀な結合を誇りに思ふ。この相反する二つのものが、かくもみごとに一つの人格に統合された民族は稀である。」と記している。
更には、昭和四十五年に語った「武士道と軍国主義」の中で、「セルフ・リスペクト(自尊心)と、セルフ・サクリファイス(自己犠牲)ということが、そしてもう一つ、セルフ・リスポンシビリティー(責任感)、この三つが結びついたものが武士道である。」と述べ、「セルフ・サクリファイスといふものがあるからこそ武士道なので、身を殺して仁をなすといふのが、武士道の非常な特長である。」と話している。
自尊心・責任感、そして自己犠牲、特に自己犠牲こそが武士道の武士道たる所以であり、三島氏はその最たるものを特攻隊の青年達に見出していた。
三島由紀夫氏と親交のあったアイヴァン・モリス氏は『高貴なる敗北 日本史の悲劇の英雄たち』を著し、特攻隊の自己犠牲の行為を、日本の精神史の中で位置づけた。この本では、日本武尊・捕鳥部万・有馬皇子・菅原道真・源義経・楠木正成・天草四郎・大塩平八郎・西郷隆盛を扱い、最後を「カミカゼ特攻の戦士たち」で締めている。モリスは言う「特別攻撃隊員たちの場合、背後には武士の伝統がある。また日本という国のため生命を捨てた英雄精神がある。」と。
戦後教育は、生命尊重=自己保全のみを教え、自己犠牲を忌み嫌い、対極にある特攻隊を誹謗し、貶めて来た。だが、国家社会にとって、共同体の為の自己犠牲の精神は崇高な事であり、かつ不可欠なのだ、眼に見えぬ自己犠牲によって社会は支えられているのだ。今日、東日本大震災等の体験によって漸く、真実を直視する眼が養われつつある。
志願から始まった特攻
戦隊長、敵空母群を特攻しましょう。(比島・飛行第三一戦隊「戦闘会議」)
終戦七十年の今年、母校の済々黌同窓会でも同窓英霊顕彰祭が行われた。多士会館(同窓会館)には十年前に慰霊碑が建立され、その際に同窓十七柱の英霊に関する資料が小冊子にして配られており、その中に特攻ゼロ号の話がある。
特攻隊の編成と出撃は昭和十九年十月二十日となっている。ところが、その一か月前の九月十三日早朝、小佐井武士陸軍中尉(済々黌昭和十四年卒)と山下軍曹の隼二機は、百瓩爆弾を装着して、レイテ東方の敵機動部隊空母に向けて特攻攻撃を行っている。事情はこうである。
小佐井中尉は昭和十九年六月に中部比島ネグロス島の東北端のフアブリカ基地に展開、飛行第一中隊の第二小隊長を務め、隼戦闘機が愛機だった。九月十二日に、敵機動部隊のネグロス島攻撃が予想され、哨戒中に攻撃から帰還中の敵グラマン6F四十機、ノースアメリカ七十機と遭遇、中隊は敵十七機を撃墜した。
その日の夜、朝の戦闘体験から戦闘会議を飛行隊員全員で開いて議論した。その結果「敵のグラマン6Fは最高速度や旋回性能は隼と大差ないが、巡航速度から最高速度になる時間と上昇力には格段の差がある。敵機は二〇ミリ機関砲四門・十三ミリ機関砲四門に対し我が機は十三ミリ二門のみ。敵機の操縦席は厚い鋼板で囲まれ、タンクには厚い防弾装置があり中々撃墜できない。これらの現実と本日の戦闘体験により、敵との正面真面目の空中戦は、機数・性能・装備そのいずれの見地からも勝つ事は不可能と思われる。尚、軍司令部偵察機の報告によれば敵機動部隊は夜間黎明には哨戒護衛飛行は行っていない。」
そこで、結論として全員異口同音に「戦隊長、敵空母群を特攻しましょう。我々はもともと軽爆隊から襲撃隊となり戦闘隊となったのですから、超低空や急降下爆撃には習熟しています。この基地で戦っても全滅するのみです。また退避しても五十歩百歩です。それならむしろ我々は日本の国民に対して、愛機の戦闘機に爆弾をつけて体当たりしても戦っている姿を見せるのが、我々の任務でしょう」と述べた。
西戦隊長が特攻志願を募ると全員参加を希望。そこで師団司令部に電話で許可を求めるが許可が降りない。二時間に亘る声涙降る懇願の結果、マニラ湾で超低空艦船攻撃訓練を受けた小佐井中尉と山下軍曹二名のみ特攻の許可が降り、早朝五時に二機が出撃したのだった。
特攻の歴史の記憶が日本を甦らせる
後世において、われわれの子孫が、祖先はいかに戦ったか、その歴史を記憶するかぎり、大和民族は断じて滅亡することはないであろう。(大西瀧治郎海軍中将が報道班員・新名丈夫氏に語った言葉)
統率の邪道とも言える特攻作戦を正式に採用し「特攻隊生みの親」と称されたのが大西瀧治郎海軍中将である。何故、大西中将は特攻作戦を採用したのだろうか。
ミッドウェー海戦の敗北以来、熟練パイロットの減少が続き、飛行時間の短い戦闘機乗りが増加していた事。更には開戦当時圧倒的な優位を誇る戦闘機だったゼロ戦(海軍)や隼(陸軍)に勝る性能を持つグラマンなどが登場し、空中戦での戦果が期待できなくなりつつあった事。その様な中、現場から特別攻撃の要望が起こり、体当たり攻撃を実行する者達が出て来た事、などが上げられる。
実際、特攻は当初それ迄に無い画期的な戦果を挙げた。昭和十九年十月二十五日のレイテ海戦からフィリピン海域での戦闘が終わる二十年一月三十一日までの戦果は、わが軍の損失(特攻機378機、護衛機102機)に対し、敵の損失は、轟沈16隻(護衛空母2、駆逐艦3、水雷艇1、その他10)損傷87隻(大小空母22、戦艦5、重巡洋艦3、軽巡洋艦7、駆逐艦23、護衛駆逐艦5、水雷艇1、その他21)というものであった。
しかし、大西はこの作戦を展開しても戦況を覆す事は至難の業であると考えていた。大西は日本の将来を見据え、歴史を相手にして決断したのだった。『別冊一億人の昭和史 特別攻撃隊』には大西中将が第一航空艦隊司令部付報道班員・新名丈夫氏に語った言葉として「もはや内地の生産力をあてにして、戦争をするわけにはいかない。戦争は負けるかもしれない。しかしながら後世において、われわれの子孫が、祖先はいかに戦ったか、その歴史を記憶するかぎり、大和民族は断じて滅亡することはないであろう。」と紹介されている。
祖国に危難が迫った時、それに身命を賭して勇躍と立ち向う青年が陸続と生れて来るならば国家は守られる。だが、わが身可愛さのみで逃亡する者ばかりであったなら、他国に隷従するしかない。国家の独立とはその様にしてしか守られない。その勇気を抱く事を歴史は訴えているのだ。終戦七十年の八月十五日には、例年にも増して多くの人々が靖国神社や各県の護国神社に参拝した。それも若い人々が多かった。その姿の中に日本の未来があり、無言の内に他国に対する大いなる抑止力を示しているのである。
















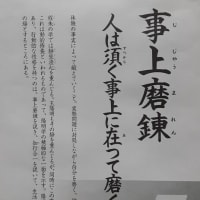



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます