その7:
プラントハンターになるまで。ジョージ・フォーレストのケース。
雲南、チベットの山岳地帯に分け入って、シャクナゲやサクラソウの膨大な品種を採集したフォーレスト(Forrest, George 1873-1932)にやっとたどり着いた。
(写真)フォーレスト(Forrest, George 1873-1932)の肖像画
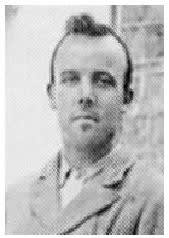
(出典)plantexplorers.com
スコットランドのプラントハンター、フォーレストは、西欧人として未踏の地、中国・雲南、チベットなどの植物探索をしたプラントハンターで、1904年から1932年に愛してやまなかったこの地で死亡するまで冒険に飛んだ7回にわたる探検を行い、数多くの植物を採取しツツジ、サクラソウ、クレマチスなどを英国エジンバラ王立植物園などのスポンサーに送った。
発見した新種は1200種にも及ぶという偉大なプラントハンターでもあったが、実績を著作物として残すということをしなかったために栄誉は得られなかった。しかし、現地の言葉を学び、現地に溶け込んでいき、愛する雲南の地にいまも眠る新しいタイプのプラントハンターでもあった。
というのが以前に書いたワンコメント的な紹介だった。
出会い
それにしても、ヒトの一生とは意外なところで決まるようだ。それは決してバラ色で輝くようには、 やって来ない。
フォーレストは、スコットランドのエジンバラとグラスゴーの中間にあるフォルカーク(Falkirk)で生れ、学校をでて薬剤師になるつもりでいたが、冒険心と野心があり彼が18歳の時の1891年に、ゴールドラッシュで沸いていたオーストラリアに向かい、10年の期間、金を求めて荒野を歩き回り鍋で土砂を洗っては砂金を探し続けた。
厳しい状況ではあったが一応は成功したようで、1902年にアフリカの岬を通って英国に帰国した。
スコットランドに帰国後、仕事を探してはいたがなかなか見つからず、釣り狩猟などで近所の野山を歩き回り多くの時間を野外で過ごした。
彼の生れ故郷フォルカークは、紀元1世紀頃にローマ軍がグレートブリテン島に侵攻し領土としたが、ケルト人からの北の防備を固めるために二つの長城ラインを建設した。
このうちの一つアントニヌスの長城(Antonine Wall)があるところであり、ローマ軍の北限にあたる。
彼の転換点は、そんな中で見つけた古い骨とそれが入っていた棺だった。これらをエジンバラの考古博物館に送り鑑定してもらったところ1500年前の遺骨だった。そして、博物館の管理者がフォーレストに興味を持った。
単に野性的だけでなく観察・探究心がある知性とオーストラリアで実証した独立心・野心を持ったフォーレストに好意を抱き、王立エジンバラ植物園の管理者バルフォア(Balfour ,Isaac Bayley1853-1922)に“気になる若者がいる。”とでも話したのだろう。
バルフォアと巡り会ったことがフォーレストの生涯を決定することになる。
(写真)若かりし頃のバルフォア(Balfour ,Isaac Bayley1853-1922)

(出典)auspostalhistory.com
王立エジンバラ植物園に園史の仕事を見つけた。最低賃金法がない頃であり相当安い賃金だったようだ。そこでバルフォアは、中国に派遣するプラントハンターを探していたリバプールの綿花仲買い商ビュアリー(Bulley, Arthur Kilpin 1861-1942)にフォーレストを紹介した。
というのが定説になっているが、ビュアリーはビジネスマンでありクチコミ・コネだけを当てにしていなかった。1855年に創刊された園芸紙「The Gardeners’ Chronicle」に求人広告を出していて、“ 求む!耐寒性の強い植物に通じている若者! そして、東方に出かけてこれらを集める若者。(Wanted, a Young Man well up on Hardy Plants, to go out to the East and Collect) ”というのが広告のコピーだった。
これからもビュアリーのかなりの本気度が伺える。
応募者が何人あったかわからないが、エジンバラ植物園の管理者バルフォアからの推薦であれば断れるはずがない。
というのは、ヴィーチ商会はキュー植物園の園長の推薦でもう一人の偉大なプラントハンター ウイルソン(Wilson、Ernest Henry 1876~1930)を既に(1899年)中国に派遣しているので、エジンバラ植物園と密接な関係を作るほうが得策だったのだろう。
これで、ヴィーチ商会・キュー植物園連合 対 ビュアリー・エジンバラ植物園連合という対抗図式が出来上がるが、彼らを動かしたのは中国清朝政府の税関に1881-1890年まで勤めたヘンリー(Henry ,Augustine 1857-1930)の影響がある。(→その3参照)
彼は、雲南地方でのフランスの宣教師デラヴェ(Delavay ,Père Jean Marie 1834–1895)の活動と成果を知り、宝の山がそこにあることを知っていた。
デラヴェを評価したのはパリ自然史博物館のフランシェ(Franchet, Adrien René 1834-1900)だけではなく、雲南へのプラントハンターの派遣をキュー植物園に要請していたヘンリーであり、この要請に最初に答えたヴィーチ・キュー連合だった。
ウイルソンは、帰国前のヘンリーと雲南省の思茅(スーマオ)で会談をしている。
ビジネスの世界では、“引継ぎ”というが、中国の植物に関しては、ヘンリー、デラヴェが第一人者なので、このハイレベルでの引継ぎ・バトンタッチには結構興味がわく。
ヘンリーに欲があれば肝心なことは教えないだろうし、弟子が先生に対する礼節がなければまた教えないだろう。どちらにしてもウイルソンはヘンリーから教えてもらうほど得するのでどう聞き出したのだろうか?
あいまいだったプラントハンター契約
脱線しすぎたので本線に戻るが、
フォーレストは1904年5月14日に中国に向かってエジンバラを出発したので、紹介者兼保証人のバルフォア、探検旅行スポンサーのビュアリーとの三者契約・合意事項が5月初旬頃に口約束でなされたようだ。
この内容があいまいだったためフォーレストの帰国後にトラブルとなる。
バルフォアは、植物標本と写真がエジンバラ植物園に全て帰属すると思い、ビュアリーは資金を全て出しているので、全てが自分のものと思っていた。フォーレストは複数ある植物標本及びタネは自分がもらえるものと思っていた。
三者三様に成果の分配・帰属を描くのは世の常であり、初めての場合ほどこの詰めが甘く、成功しても失敗してもトラブルが発生する。
さらに、最大の問題は、フォーレストの一年間の給与だった。探検に関わる全ての費用を含めて年間600ポンドが支払われる約束だった。給与と経費が分離されていないところが問題で必要経費の積算が帰国後に検討されるようになる。
この600ポンドという金額が妥当かどうかを検討すると、エジンバラ植物園でのフォーレストの給与は週給2ポンドでかなり安かったようだが年間100ポンド強となる。
キュー植物園が初めて海外にプラントハンターを出したのが1772年でこの時のフランシス・マッソンの年俸が100ポンド、探検旅行の上限経費100ポンドだった。
1800年代初め頃もこのルールが適用されたようだが、既に魅力ないものとなっていたので、1904年のフォーレストの契約時には、年俸300ポンドでも危険手当込みで魅力あるものではなかったと思われる。
フォーレスト帰国後のトラブル
フォーレストは、自分が作成した植物標本のコピーワンセットを所有し、タネは転売してしまった。契約としての成果報酬と受け取っていたのだろう。或いは、給与を含めた総経費600ポンドでは少なかったのでこの補填でもあったのだろう。
しかし、バルフォアは、植物標本を返してもらうためにトラックをさしむけこれをもっていってしまった。ビュアリーはタネを回収しようとしたが既に転売された後なので、この三者の関係が危険な関係となり、特にフォーレストとビュアリーの関係は悪化した。
ビュアリーがないものは植物学の知識とそのネットワークであり、バルフォアがないものは新しい植物情報を手に入れる探検の費用であり、それぞれ持たないものを知っている二人の関係は補完関係にあるので修復した。
バルフォアとフォーレストの関係は緊張感のある冷たい関係となったが、バルフォアはフォーレストのプラントハンターとしての才能を認め和解の話し合いを持った。自分を認めてくれたバルフォアに感激したフォーレストは、終生の友・師として付き合うことになる。
しかし、フォーレストとビュアリーの関係は、代替が効く雇用関係であり、悪化し続け契約解除となる。
現代でも当てはまる構造であり、雇用関係は弱い関係であり、信頼関係ほど強いものがない。これは親子関係を超えるかもわからない。
またトラブルの元は最初にあるというのが経験則としてあるが、見事に当てはまっている。
プラントハンターになるまで。ジョージ・フォーレストのケース。
雲南、チベットの山岳地帯に分け入って、シャクナゲやサクラソウの膨大な品種を採集したフォーレスト(Forrest, George 1873-1932)にやっとたどり着いた。
(写真)フォーレスト(Forrest, George 1873-1932)の肖像画
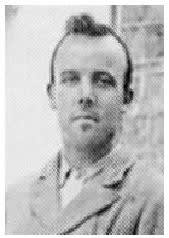
(出典)plantexplorers.com
スコットランドのプラントハンター、フォーレストは、西欧人として未踏の地、中国・雲南、チベットなどの植物探索をしたプラントハンターで、1904年から1932年に愛してやまなかったこの地で死亡するまで冒険に飛んだ7回にわたる探検を行い、数多くの植物を採取しツツジ、サクラソウ、クレマチスなどを英国エジンバラ王立植物園などのスポンサーに送った。
発見した新種は1200種にも及ぶという偉大なプラントハンターでもあったが、実績を著作物として残すということをしなかったために栄誉は得られなかった。しかし、現地の言葉を学び、現地に溶け込んでいき、愛する雲南の地にいまも眠る新しいタイプのプラントハンターでもあった。
というのが以前に書いたワンコメント的な紹介だった。
出会い
それにしても、ヒトの一生とは意外なところで決まるようだ。それは決してバラ色で輝くようには、 やって来ない。
フォーレストは、スコットランドのエジンバラとグラスゴーの中間にあるフォルカーク(Falkirk)で生れ、学校をでて薬剤師になるつもりでいたが、冒険心と野心があり彼が18歳の時の1891年に、ゴールドラッシュで沸いていたオーストラリアに向かい、10年の期間、金を求めて荒野を歩き回り鍋で土砂を洗っては砂金を探し続けた。
厳しい状況ではあったが一応は成功したようで、1902年にアフリカの岬を通って英国に帰国した。
スコットランドに帰国後、仕事を探してはいたがなかなか見つからず、釣り狩猟などで近所の野山を歩き回り多くの時間を野外で過ごした。
彼の生れ故郷フォルカークは、紀元1世紀頃にローマ軍がグレートブリテン島に侵攻し領土としたが、ケルト人からの北の防備を固めるために二つの長城ラインを建設した。
このうちの一つアントニヌスの長城(Antonine Wall)があるところであり、ローマ軍の北限にあたる。
彼の転換点は、そんな中で見つけた古い骨とそれが入っていた棺だった。これらをエジンバラの考古博物館に送り鑑定してもらったところ1500年前の遺骨だった。そして、博物館の管理者がフォーレストに興味を持った。
単に野性的だけでなく観察・探究心がある知性とオーストラリアで実証した独立心・野心を持ったフォーレストに好意を抱き、王立エジンバラ植物園の管理者バルフォア(Balfour ,Isaac Bayley1853-1922)に“気になる若者がいる。”とでも話したのだろう。
バルフォアと巡り会ったことがフォーレストの生涯を決定することになる。
(写真)若かりし頃のバルフォア(Balfour ,Isaac Bayley1853-1922)

(出典)auspostalhistory.com
王立エジンバラ植物園に園史の仕事を見つけた。最低賃金法がない頃であり相当安い賃金だったようだ。そこでバルフォアは、中国に派遣するプラントハンターを探していたリバプールの綿花仲買い商ビュアリー(Bulley, Arthur Kilpin 1861-1942)にフォーレストを紹介した。
というのが定説になっているが、ビュアリーはビジネスマンでありクチコミ・コネだけを当てにしていなかった。1855年に創刊された園芸紙「The Gardeners’ Chronicle」に求人広告を出していて、“ 求む!耐寒性の強い植物に通じている若者! そして、東方に出かけてこれらを集める若者。(Wanted, a Young Man well up on Hardy Plants, to go out to the East and Collect) ”というのが広告のコピーだった。
これからもビュアリーのかなりの本気度が伺える。
応募者が何人あったかわからないが、エジンバラ植物園の管理者バルフォアからの推薦であれば断れるはずがない。
というのは、ヴィーチ商会はキュー植物園の園長の推薦でもう一人の偉大なプラントハンター ウイルソン(Wilson、Ernest Henry 1876~1930)を既に(1899年)中国に派遣しているので、エジンバラ植物園と密接な関係を作るほうが得策だったのだろう。
これで、ヴィーチ商会・キュー植物園連合 対 ビュアリー・エジンバラ植物園連合という対抗図式が出来上がるが、彼らを動かしたのは中国清朝政府の税関に1881-1890年まで勤めたヘンリー(Henry ,Augustine 1857-1930)の影響がある。(→その3参照)
彼は、雲南地方でのフランスの宣教師デラヴェ(Delavay ,Père Jean Marie 1834–1895)の活動と成果を知り、宝の山がそこにあることを知っていた。
デラヴェを評価したのはパリ自然史博物館のフランシェ(Franchet, Adrien René 1834-1900)だけではなく、雲南へのプラントハンターの派遣をキュー植物園に要請していたヘンリーであり、この要請に最初に答えたヴィーチ・キュー連合だった。
ウイルソンは、帰国前のヘンリーと雲南省の思茅(スーマオ)で会談をしている。
ビジネスの世界では、“引継ぎ”というが、中国の植物に関しては、ヘンリー、デラヴェが第一人者なので、このハイレベルでの引継ぎ・バトンタッチには結構興味がわく。
ヘンリーに欲があれば肝心なことは教えないだろうし、弟子が先生に対する礼節がなければまた教えないだろう。どちらにしてもウイルソンはヘンリーから教えてもらうほど得するのでどう聞き出したのだろうか?
あいまいだったプラントハンター契約
脱線しすぎたので本線に戻るが、
フォーレストは1904年5月14日に中国に向かってエジンバラを出発したので、紹介者兼保証人のバルフォア、探検旅行スポンサーのビュアリーとの三者契約・合意事項が5月初旬頃に口約束でなされたようだ。
この内容があいまいだったためフォーレストの帰国後にトラブルとなる。
バルフォアは、植物標本と写真がエジンバラ植物園に全て帰属すると思い、ビュアリーは資金を全て出しているので、全てが自分のものと思っていた。フォーレストは複数ある植物標本及びタネは自分がもらえるものと思っていた。
三者三様に成果の分配・帰属を描くのは世の常であり、初めての場合ほどこの詰めが甘く、成功しても失敗してもトラブルが発生する。
さらに、最大の問題は、フォーレストの一年間の給与だった。探検に関わる全ての費用を含めて年間600ポンドが支払われる約束だった。給与と経費が分離されていないところが問題で必要経費の積算が帰国後に検討されるようになる。
この600ポンドという金額が妥当かどうかを検討すると、エジンバラ植物園でのフォーレストの給与は週給2ポンドでかなり安かったようだが年間100ポンド強となる。
キュー植物園が初めて海外にプラントハンターを出したのが1772年でこの時のフランシス・マッソンの年俸が100ポンド、探検旅行の上限経費100ポンドだった。
1800年代初め頃もこのルールが適用されたようだが、既に魅力ないものとなっていたので、1904年のフォーレストの契約時には、年俸300ポンドでも危険手当込みで魅力あるものではなかったと思われる。
フォーレスト帰国後のトラブル
フォーレストは、自分が作成した植物標本のコピーワンセットを所有し、タネは転売してしまった。契約としての成果報酬と受け取っていたのだろう。或いは、給与を含めた総経費600ポンドでは少なかったのでこの補填でもあったのだろう。
しかし、バルフォアは、植物標本を返してもらうためにトラックをさしむけこれをもっていってしまった。ビュアリーはタネを回収しようとしたが既に転売された後なので、この三者の関係が危険な関係となり、特にフォーレストとビュアリーの関係は悪化した。
ビュアリーがないものは植物学の知識とそのネットワークであり、バルフォアがないものは新しい植物情報を手に入れる探検の費用であり、それぞれ持たないものを知っている二人の関係は補完関係にあるので修復した。
バルフォアとフォーレストの関係は緊張感のある冷たい関係となったが、バルフォアはフォーレストのプラントハンターとしての才能を認め和解の話し合いを持った。自分を認めてくれたバルフォアに感激したフォーレストは、終生の友・師として付き合うことになる。
しかし、フォーレストとビュアリーの関係は、代替が効く雇用関係であり、悪化し続け契約解除となる。
現代でも当てはまる構造であり、雇用関係は弱い関係であり、信頼関係ほど強いものがない。これは親子関係を超えるかもわからない。
またトラブルの元は最初にあるというのが経験則としてあるが、見事に当てはまっている。


















