<以前書いた記事を復刻します。>
「ユニクロはブラック企業か?」という記事を書いたら、ある人から質問をいただいた。昔、私がテレビ局に勤めていたことをご存知らしく、「そのテレビ局もブラックではなかったか」というものだ。
考えてみると、昔のテレビ局も忙しかった。多忙であることには今と変わりがない。しかし、何かが違っていたと思う。それは何だったのだろうかと考えてみたが、よく分からない。そこで私なりに、今の会社(企業)と昔の会社の違いを勝手に考えてみた。
一番の違いは、「終身雇用制」と「年功序列制」が厳然としてあったかどうかということだろう。今の企業のことはよく知らないが、そういう制度が崩れてきたと聞いている。というのは、去年のいつだったかよく覚えていないが、野田前内閣が「40歳定年制」の導入について、専門家や識者に諮問するというニュースを聞いたことがある。
えっ、40歳定年制だって!? そんなことがあるのか。私は驚いたが、政府が諮問するというのだ。私は古い人間だから、40歳定年制なんて聞いたことがない。むしろ現実は、高齢化によって65歳とかそれ以上に定年を延長しようというのではなかったか。だから、40歳定年制なんてバカ言うな! と思った。
幸い40歳定年の話はその後聞いていないが、事ほど左様に、今や従業員を早く首切り、リストラを進めようという時代になっている。要するに、従業員や会社員は企業の単なる“コマ”に過ぎず、使い捨て自由な社会になっているのではないか。
資本主義とは本来そういうものだろう。昔も首切りやリストラはもちろんあった。基本的には、昔も今も変わらない。しかし、終身雇用制や年功序列制はなぜあったのだろうか。 これを“日本型資本主義の美徳”と捉える外国人が数多くいた。旧ソ連や中国など社会主義国の人達は「日本ほど素晴らしい社会主義社会はない」と、称賛したぐらいである。
ところが、日本はその後、国際化・グローバル化の“美名”のもとに大きく変わったようだ。構造改革とも言ったが、要するに弱肉強食、優勝劣敗の社会になっていった。マスコミはこれを「勝ち組・負け組」と呼んだが、資本主義的競争社会が徹底していったのだろうか。
私は、終身雇用制や年功序列制が100%良いと言っているのではない。古き良き時代の日本型制度だろうが、その弊害ももちろん知っている。こういった制度に安住するのは、本来の資本主義に背反することだろう。
しかし、今でもこうした制度は良かったと思っている。なぜなら、終身雇用制や年功序列制は膨大な中産階級を生み出し、日本の「総中流社会」を実現したからだ。このため社会も安定した。しかし、今や日本社会は崩れてきた。格差が拡大し、膨大な非正規雇用を生み出しているのだ。
あまりの格差拡大に、マスコミも「勝ち組・負け組」という言い方を自粛しているようだ。日本が誇る「総中流社会」は崩壊した。そして、終身雇用制も年功序列制も過去の“遺物”になろうとしている。それは時代の流れだから仕方がない面もあるが、そうした古き良き制度に替わるものを、日本はしっかりと準備しているだろうか。
残念ながら、それは「ない」と言っていい。政治も行政もまた企業経営も、ほとんどないと言っていいのではないか。特に政治と行政は“行き当たりばったり”という感じだ。
話が逸れてしまったが、今、どれほどの会社員・従業員が『会社は自分達のもの』と思っているだろうか。それは分からない。しかし、昔はほとんどの会社員・従業員が『会社は自分達のもの』と思っていただろう。今は「会社は株主のもの」とか「経営者のもの」と思っているのだろうか。
自分達はいつリストラに遭うかと戦々恐々としている人達に、どうして『愛社精神』など望めようか!? そんなものは完全に過去の遺物と化してしまったのだ。
ユニクロの柳井正会長兼社長は、次のように述べているそうだ。「将来は、年収1億円か100万円に分かれて、中間層が減っていく。仕事を通じて付加価値がつけられないと、低賃金で働く途上国の人の賃金にフラット化するので、年収100万円のほうになっていくのは仕方がない」(ウィキペディアを参照 ⇒http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E4%BA%95%E6%AD%A3) たしかに企業のグローバル化を考えれば、柳井氏の言っていることは当然だろう。前にも述べたように弱肉強食、優勝劣敗の世の中になっていくのだ。「総中流社会」は崩れ、格差が広がっていくのは当然かもしれない。私は企業を経営したこともなく、商売や経営にはまったく素人だ。商売はそんな甘っちょろいものではないはずだ。だから、柳井氏の言うことには脱帽せざるを得ない。
しかし、日本社会がズルズルとそうなれば良いとは思っていない。1人の成功者と99人の脱落者が出れば良いとは思っていない! それは間違いなく社会不安を生むものだ。
私は古い人間かもしれないが、昔は「1人が100歩進むよりも、100人が1歩進める社会を目指そう」とよく言ったものだ。これは社会主義的な発想から出た言葉だろうが、今やそうした考え方は陳腐で消えたのだろうか。
会社(企業)が利益を求めるのは当然だ。会社員・従業員はそのために働く。また、経営者が最大の利益を上げようと努力するのは正しい。それは結構だが、利益は何に使うのか。投資や配当、社内留保などいろいろあるだろう。しかし、どのくらい社員・従業員に回ってくるだろうか。
昔は「わが社の給料はどこにも負けない」が経営者のプライド、自慢のタネだったと思う。しかし、今そう考えている経営者がどのくらいいるだろうか。最近の会社のことはよく知らないが、利益最優先で社員への配分は“二の次”ではないのか。
社員・従業員が「会社は自分達のもの」と考えていた頃は、給料や手当、待遇は良かったと思う。しかし、今は違うだろう。会社は社員や従業員のものというより、株主や経営者のものという考えが強まっていると聞く。これでは、社員や従業員はごく一部を除いて“使い捨て”になっていくだけだ。
こういう話をするとやたらに長くなるが、昔の経営者はプライドや自負の念があったと思う。私が勤めていたテレビ局の社長らは、好き嫌いは別にして皆「日本一の会社」を目指していたと思う。それは企業利益だけでなく社員の給料、待遇の日本一を目指していたのだ。だから、自然と愛社精神が湧く。
例えば「週休2日制」というのがあるが、現場の管理職や社員が無理だと思っても、強引に2日制を導入するのだ。それは経営者の“見栄”かもしれない。「わが社は週休2日制を行なっていますよ」と言いたいのだろう。それにしては“少数精鋭主義”とか言って、新卒社員をなかなか採用しなかったが(笑)。
とにかく、昔の経営者は見栄であろうとも「最良の会社」を目指していた。しかし、今の経営者は利益しか眼中にないのではないか。最近の「ブラック企業」の話を聞くと、その思いを強くする。
こう言うと少し語弊があるが、今の経営者は従業員を出来るだけ低賃金で働かせ、こき使った上に“使い捨て”にしようという魂胆がありありと見えるのだ。これは私の偏見だろうか。失礼(終り)










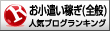


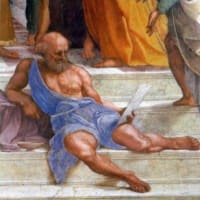













それらが重層をなして一つの商号と商標をなすのです。
どうも、昨今の会社の在り方についての論議は一面的に全てを語ろうとする傾向が強いと思います。
元も子もない話ですが、自分の持つ株式の会社を自分(達)のものと思う株主はいません。欧米でもそうです。
そのアイディアの元だった海外では、その人材の才能に対して期間を決めて雇用するという形であり、日本的な在り方は労働者の権利を100年前に戻すくらい世界に類をみないひどい在り方という批判があります。技術研修という名で東南アジアの人を安く使うやり方とも通底していますね。
アイディアの元となった先進国ではなんでも自由化すればよいというものではなかったという反省が一定の常識となっており、たとえば水道の自由化が水供給の安全安定にリスクをもたらしたことなどもその例ですが、日本では海外の事例に学ばないとぼけた導入議論が自治体でなされてたりします。大学の基礎研究予算は大幅に削られましたが、そのツケとして、次世代の主要な市場と呼ばれる技術分野での日本の競争力は、2周遅れ3周遅れという状況。
おっしゃるように行政は場当たりで近視眼です。
今や次のビジネスの見えない財界はかつての高度成長を思い出し、あの時代の人件費コストで競争力を得たいといあ発想しかないのかなと感じます。
一方で半径何メートルであたりを見回すと、事業構造を変えながら、後の世代のためにもこの会社をよい形で残したいという経営者の話や、プロジェクトの推進ノウハウなどで技術の伝承で人を育てるというリーダーの気持ちを見てたりして、まだこの会社は頑張りそうだぞと思っている自分もいたりします。
法人は人とは違う目的をもった生物という喩えはよくありますが、ブラックであったり、反対にSDGsであったり、SNSのなかで情報がはやく伝わるなかで問われるのは、人にとってよいのではないでしょうかね。
企業経営などの経験がない私には、会社の良し悪しを論じる資格はありません。せいぜい、日本社会が良くなれと願うだけです。
そして、働きやすい労働環境になればと思っています。
「ユニクロ」がアパレル業界で世界一になったとか・・・世の中は大きく変わっていきますね。