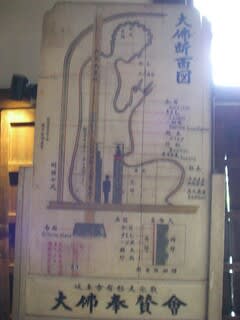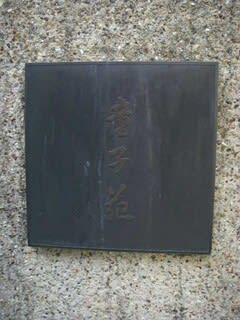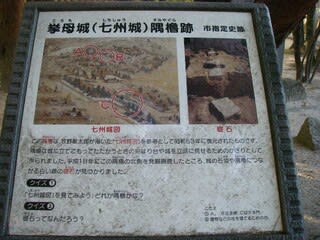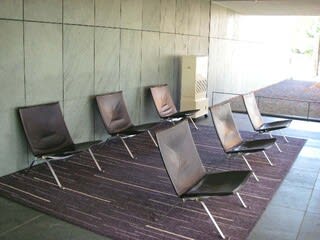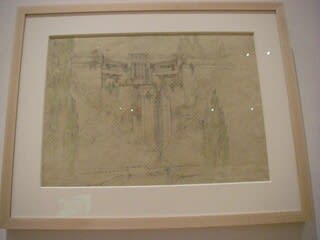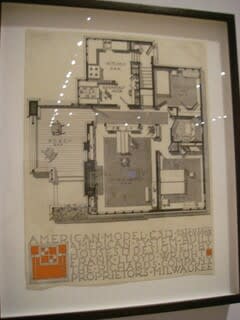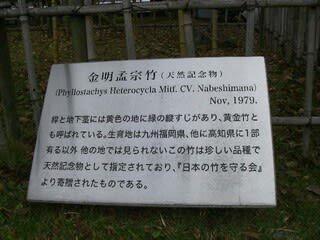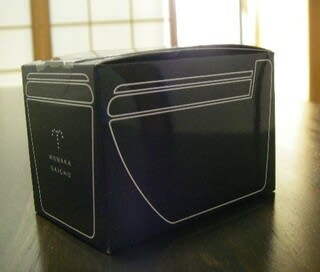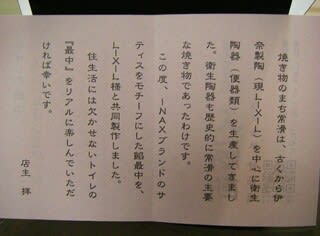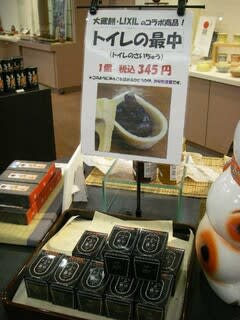兵庫県宝塚市にある『手塚治虫記念館』
現在、開館30周年をお祝いして
【 火の鳥展 】を開催しているとのことで
この機会に行って来ました。
手塚治虫記念館での【火の鳥】の展示は
実に、20年ぶりになるのだそうです。
これは見ておかなくては…!
で、
名古屋から宝塚市までの移動です。
新幹線が早くて便利なのですが…
せっかくなので
《 ひのとり 》に乗って行こう!
もちろん、本物の火の鳥ではなく…
こちらです ↓
近鉄特急ひのとり広告ポスター

近鉄名古屋駅から大阪難波を結ぶ特急電車で
毎時00分に発車します。
《 ひのとり 》に乗って
【 火の鳥展 】を見に行こう!っていうわけです。
近鉄電車のホーム内には
《 ひのとり 》って
電車好きさんにはかなりの人気のようで…
まさか!の、
ひのとりプリントシール機 ↓

確かに記念になりますよね。
しかも、この場所限定らしいです ↓
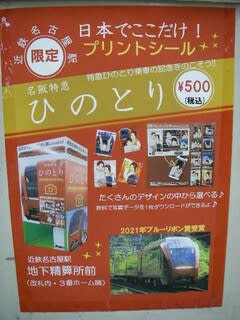
私は撮りませんでしたが
ひのとり好きさんは是非!
さらに、近鉄電車の車両が並んだ広告ポスター ↓

スター選手並の扱いですよね(笑)
乗車時間までまだ時間があったので
ホーム内をウロウロして
気になったのがこちら、
駅弁です。
(ひのとり弁当) ↓

(しまかぜ弁当) ↓

駅弁にも登場です。
さらに、
この販売店での駅弁売り上げランキングまでありました。
お弁当人気1位 しまかぜ弁当 ↓

2位 ひのとり弁当 ↓

3位 天むす ↓
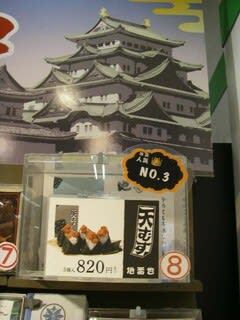
駅弁の人気は
しまかぜが上でした。
ちなみに《しまかぜ》は、
大阪難波、京都、名古屋の各駅から
三重県伊勢志摩の賢島(かしこじま)までを
結ぶ観光特急なのだそうです。
そうこうしているうちに
ホーム内にひのとりが入って来ました ↓

このロゴマークも良いですね ↓

特急ひのとりですが、
手塚先生の『火の鳥』とは関連はないそうです。
それでは車内に入りたいと思います。
ひのとり車内にある自販機 ↓

軽食や鉄道グッズが販売されています。
ひのとり鉄道グッズ ↓

コーヒーメーカーも ↓

紙コップはひのとりのロゴマーク入り ↓

挽きたてコーヒーを購入 ↓

そして座席です。
今回
プレミアム車両の座席を予約しました ↓

特急ひのとりは
くつろぎの空間が特徴なのだそうです。
座り心地も良く、さあ、くつろぐか…と思った矢先、
通路を挟んで座った隣のカップルが
まぁビックリするほどしゃべる、しゃべる、しゃべる…
嫌な予感がします…
初めは、まぁ仕方ないよなぁ…と寛大な気持ちで
いたのですが
静まる気配がありません…。
気持ちを切り替えようと
車内からの風景を撮影してみました。
木曽川を渡っていることころです ↓

隣のカップルはしゃべり続けています。
どこからそんなに話題が出てくるのか…
イヤホンをして音楽を聴き、気を紛らせていたのですが
大音量で聴くのは耳に良くないとボリュームを下げると
しゃべり声がイヤホン越しに聞こえてきて
まだしゃべっているのか…と。
車内での会話禁止でもないわけだから
注意するわけにもいかず、
かと言って特別車両の料金を支払っているだけに
納得できない自分もいて…
悶々とした時間が過ぎていきます。
乗車前のウキウキ感も半減どころか急降下です。
指定席にしているばっかりに移動できないし…
“会話席”と“くつろぎぐっすり睡眠席”っていうのを
創ってもらえないだろうか…なんて考えたり
さらに悶々とした時間が過ぎていき…
で、結局、
くつろぎ睡眠する時間のないまま到着しました…
大阪難波駅へ到着前にメロディと照明の演出 ↓

噓だろ、って思うかもしれませんが
名古屋から大阪難波までの2時間8分の乗車時間内を
隣のカップルはずっとしゃべり続けていたのです…
こんな事ならプレミアム車両に乗らなきゃ良かった…
今回、
くつろぎ空間は絶対に確保されるものではないって事を
学びました。
悲しい出だしになってしまいましたが
ここでめげている場合ではありません。
大阪難波から宝塚までの移動が待っています。
大阪難波から歩いて、大阪メトロの御堂筋線へ向かいます。
なんば駅から梅田まで乗車し、
梅田で下車してから歩いて大阪駅へと移動。
大阪駅から
JR福知山線に乗って宝塚駅で下車しました。
宝塚駅に到着です ↓

これは阪急宝塚駅の階段です。
宝塚に来た!って感じがします。
長くなってしまったので
次回、【火の鳥展】に続きます。
お疲れ様でした!
現在、開館30周年をお祝いして
【 火の鳥展 】を開催しているとのことで
この機会に行って来ました。
手塚治虫記念館での【火の鳥】の展示は
実に、20年ぶりになるのだそうです。
これは見ておかなくては…!
で、
名古屋から宝塚市までの移動です。
新幹線が早くて便利なのですが…
せっかくなので
《 ひのとり 》に乗って行こう!
もちろん、本物の火の鳥ではなく…
こちらです ↓
近鉄特急ひのとり広告ポスター

近鉄名古屋駅から大阪難波を結ぶ特急電車で
毎時00分に発車します。
《 ひのとり 》に乗って
【 火の鳥展 】を見に行こう!っていうわけです。
近鉄電車のホーム内には
《 ひのとり 》って
電車好きさんにはかなりの人気のようで…
まさか!の、
ひのとりプリントシール機 ↓

確かに記念になりますよね。
しかも、この場所限定らしいです ↓
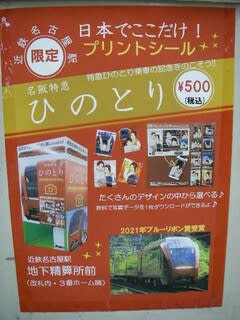
私は撮りませんでしたが
ひのとり好きさんは是非!
さらに、近鉄電車の車両が並んだ広告ポスター ↓

スター選手並の扱いですよね(笑)
乗車時間までまだ時間があったので
ホーム内をウロウロして
気になったのがこちら、
駅弁です。
(ひのとり弁当) ↓

(しまかぜ弁当) ↓

駅弁にも登場です。
さらに、
この販売店での駅弁売り上げランキングまでありました。
お弁当人気1位 しまかぜ弁当 ↓

2位 ひのとり弁当 ↓

3位 天むす ↓
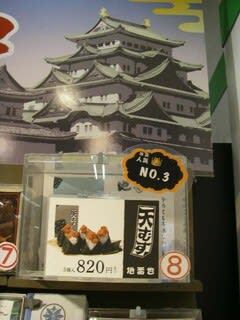
駅弁の人気は
しまかぜが上でした。
ちなみに《しまかぜ》は、
大阪難波、京都、名古屋の各駅から
三重県伊勢志摩の賢島(かしこじま)までを
結ぶ観光特急なのだそうです。
そうこうしているうちに
ホーム内にひのとりが入って来ました ↓

このロゴマークも良いですね ↓

特急ひのとりですが、
手塚先生の『火の鳥』とは関連はないそうです。
それでは車内に入りたいと思います。
ひのとり車内にある自販機 ↓

軽食や鉄道グッズが販売されています。
ひのとり鉄道グッズ ↓

コーヒーメーカーも ↓

紙コップはひのとりのロゴマーク入り ↓

挽きたてコーヒーを購入 ↓

そして座席です。
今回
プレミアム車両の座席を予約しました ↓

特急ひのとりは
くつろぎの空間が特徴なのだそうです。
座り心地も良く、さあ、くつろぐか…と思った矢先、
通路を挟んで座った隣のカップルが
まぁビックリするほどしゃべる、しゃべる、しゃべる…
嫌な予感がします…
初めは、まぁ仕方ないよなぁ…と寛大な気持ちで
いたのですが
静まる気配がありません…。
気持ちを切り替えようと
車内からの風景を撮影してみました。
木曽川を渡っていることころです ↓

隣のカップルはしゃべり続けています。
どこからそんなに話題が出てくるのか…
イヤホンをして音楽を聴き、気を紛らせていたのですが
大音量で聴くのは耳に良くないとボリュームを下げると
しゃべり声がイヤホン越しに聞こえてきて
まだしゃべっているのか…と。
車内での会話禁止でもないわけだから
注意するわけにもいかず、
かと言って特別車両の料金を支払っているだけに
納得できない自分もいて…
悶々とした時間が過ぎていきます。
乗車前のウキウキ感も半減どころか急降下です。
指定席にしているばっかりに移動できないし…
“会話席”と“くつろぎぐっすり睡眠席”っていうのを
創ってもらえないだろうか…なんて考えたり
さらに悶々とした時間が過ぎていき…
で、結局、
くつろぎ睡眠する時間のないまま到着しました…
大阪難波駅へ到着前にメロディと照明の演出 ↓

噓だろ、って思うかもしれませんが
名古屋から大阪難波までの2時間8分の乗車時間内を
隣のカップルはずっとしゃべり続けていたのです…
こんな事ならプレミアム車両に乗らなきゃ良かった…
今回、
くつろぎ空間は絶対に確保されるものではないって事を
学びました。
悲しい出だしになってしまいましたが
ここでめげている場合ではありません。
大阪難波から宝塚までの移動が待っています。
大阪難波から歩いて、大阪メトロの御堂筋線へ向かいます。
なんば駅から梅田まで乗車し、
梅田で下車してから歩いて大阪駅へと移動。
大阪駅から
JR福知山線に乗って宝塚駅で下車しました。
宝塚駅に到着です ↓

これは阪急宝塚駅の階段です。
宝塚に来た!って感じがします。
長くなってしまったので
次回、【火の鳥展】に続きます。
お疲れ様でした!