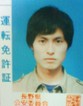2/15(木)、イオンシネマ新潟西で大林宣彦監督の『花筐』を観て来ました!

このポスター、実はすごく細かく色々書いてあるので、気になる方のために大きな画像も貼っておきます。
ひとまず予告編はこちらです。
と言う訳で、感想を書いていく前に、これだけは言っておきたいんですが、私、大林宣彦監督が大好きなんです。
…と言っても、全作品を網羅しているような熱心なファンという訳でもないし、有名どころしか観てはおりませんが、子供の時から大人になってまで、どんな作品にもワクワクさせられてきました。
確か最初に観たのは小学生の時にレンタルビデオで観た『水の旅人 SAMURAI KIDS』だったように思います。特撮を使用したファンタジーの物語と、少年少女の冒険と、当時から問題になっていた環境問題や家族の問題などに対する強いメッセージなど、子供ながらに強く感動させられてしまいました。
その後、高校時代くらいに友人の家ですすめられて観た『時をかける少女』も、やっぱり特撮の不思議な映像の中で描かれる青春のノスタルジーとSFが見事に融合していて、さすが名作だと思わせられました。
大人になってからは、松本に住んでいた時に、演劇をやっていた友人(おもケン)と、「観てみようぜ!」という好奇心で大林宣彦監督のデビュー作『HOUSE』を観たのですが、映像からストーリーから何もかもぶっ飛んだまさにカルト映画で、こんな映画でデビューした大林監督、やべえ…と思ったのです。
大林宣彦監督、全体的に特撮を利用することが多いんですが、CGが発達した今から見るとすごく古いというか違和感が全開の映像なんですけど、でもその「大林宣彦的」としか言えないあの不思議な有り得ない映像美が、何故か妙に心地よいというか、そしてその心地よさが、作品の中に漂っているノスタルジックな雰囲気にすごーく合ってるんですよねコレが…
なんていうか、子供の時に図書館で読んだ絵本や小説や、テレビで観た子供向けのテレビアニメ、それから保育園での映画の上映会…なんかそんな自分が物語と出会った時の懐かしい記憶にトリップさせられてしまうような、そんな気持ちにさせられてしまうのです。
で、そんな大林宣彦監督の映画を初めてスクリーンで観たのが、新潟の長岡を舞台に2012年に公開された『この空の花 長岡花火物語』だったんですけど、これがまあ!本当に素晴らしくて、その年に観た映画の中で迷わず1位にしてしまったという、本当に大好きな映画なんです。
何がすごいかと言いますと、やっぱりそのデビュー作『HOUSE』でも使われていた、あの本当に大林的としか言いようがない実験的で不思議な特撮の映像美、あのこだわりは最初から今までまったくブレていない、にもかかわらず、それが現代に合わせて進化しているというか、下手したら「古いもの」に見えてしまいがちなあの映像が、本当にフレッシュな「新しいもの」に見えてしまった凄さというか…
要するに「こんなもの観たことない!」っていう驚きが映画全体を通して全開になっておりまして、今や巨匠と呼ばれる年齢になった大林監督が、尖りに尖った若手映画監督のデビュー作のような挑戦をまったく忘れていないことに気付かされ、そんな大林宣彦監督の映画にかける強い思いに感動させられてしまったのです。
しかも、それに加え、そんな不思議な映像に翻弄されつつも、さらに物語にも翻弄されてしまうという…本当に一言で説明しづらい映画なんですが、長岡の戦時中の記憶と、中越沖地震の記憶と、東日本大震災の記憶と、そして現代の長岡とが縦横無尽に展開する四次元のような映画で、もっと言えば、そうやって作られたこの映画の中の物語と、この映画を撮っている人間達のドキュメンタリーさえも融合しているというか、そういう凄まじい情報量を2時間半くらいの時間で一気に脳内に叩き込まれて本当にクラクラしてしまってですね…
とにかく一言、自分が何に感動していたのか自分でも未だによく分かっていないのですが、何がすごいのか分からないけどとにかく、すごい!の一言に尽きる映画だったのです。
ただ一つ分かるのは、物語は難解ではあるものの、大林監督の平和に対する強い思いは、本当にこれでもか!と、痛いくらいに伝わってくるのです。
だからきっと僕はこの映画を一生忘れないと思いますし、それはつまり、大林監督の平和への願いは僕の中で一生消えないということでもあり、本当にこういう映画に出会えて幸せだったなあと思っています。
その後、テレビやネットなどで、大林監督が戦争体験者としてこの時代を生きる人々へ平和への願いを訴え続けている、その気持ちを込めて映画を作っている、ということも知り、ますます大好きになってしまったのです。
なんか、前置きが長くなってしまいましたが…はい、ここからいよいよ、大林宣彦監督の最新作『花筐』の感想を書いていこうと思います!
と言う訳で観て来た『花筐』、この映画は、ちょうど今にも戦争が始まろうとしている時代の、佐賀県唐津市を舞台に、若者たちの青春の日々を描いたものなのですが、とにかく強烈なインパクトを持った映画でした!
『空の花 長岡花火物語』のように、ぶっ飛んだ有り得ない映像表現の連発と、時間と空間が行ったり来たりする四次元的なストーリー展開にクラクラし、そしてそこに若者たちのむきだしの青春が花火のように強烈に輝き、何が何だか分からないけど感動させられてしまい、そんな映画に翻弄され続けるうちに3時間があっという間に過ぎ、振り返ってみると大林監督の平和への願いが強烈に心に刺さっている…という、要するにいつもの大林宣彦ワールドが全開というか、集大成のような映画だったと思います。
この映画の凄かったポイントの一つは、さっきから何度も言っているような強烈な映像表現です。
特に、ほぼすべてのシーンで背景が何らかの合成になっているんですよね。
しかも、現代の技術だったらまったく違和感なく本当にそういう風景があるかのように見せることも全然可能だと思うんですけど、大林監督の手にかかると、凄まじい違和感が全開!なんですよね。本当に、大林的!としか言えないというか。
しかし、じゃあその違和感のある映像がマイナスに働いているかとまったくそんなことはなく、寧ろその絶妙な違和感が非常に心地いいというか、美しくすらあるという…こればっかりは見ていただかないと分からないと思うんですけど、本当に、何かこう、圧倒的な凄まじさがあるんですよね。
そんな強烈な映像の連続の中で、次々と様々な人間ドラマが展開していくのですが、中心となるのは男女の若者たちの青春です。
時に友情を育んだり、恋をしたり、すれ違ったりと、二転三転していく人間関係の一つ一つのエピソードが、何度も書いたような強烈な映像によって表現されるので、その度に画面に釘付けになってしまい、そんな物語に翻弄されてしまう気持ちになりました。
そんな二転三転する人間関係は、一つ一つは強烈であるものの、一つの映画の中の物語としてどこに向かっているのかが正直よく分からない気もするのですが、でも、よく考えたら思春期ってまさにそういうものだよなあ…なんて思ったりするのです。
だから、一つ一つのエピソードや映像が強烈なばかりで一本の物語として理解するのはなかなか難しいとは思いますが、それでも通して見ていると、青春を生きる若者たちの花火のように強烈に光り輝き命を燃やす姿が、強烈に胸に残ります。
脚本も演出もエキセントリックで不思議な映画である一方で、青春という誰もが体験する普遍的なものを描いている映画でもあるかなあという気もします。
しかし、この映画が描いているのは青春の輝かしさばかりでは決してありません。
若者の苦悩や、登場人物に病気の人物がいるように、死の恐怖もかなり痛切に描いています。
特に、この映画を語る上で欠かすことが出来ないこととして、戦争が今まさに始まろうとしている日本の不穏な空気も描いているのです。
生きる苦しみも、死の恐怖も、そして戦争への不安も、決して過去のものではなく、どの時代のどの人間たちも同じように感じているもの、普遍的なものだと思います。
大林宣彦監督がこの時代に敢えてこの映画を作ったことは、このような目を背けてしまいがちな人間の弱さや悲しみ、恐怖などを、決して忘れてはならないというメッセージだったのかも知れないなと思いました。
まさにこの時代に作られるべきだった映画だと思います。
そんなわけで、今まで書いてきたようなことをまとめると、この映画が素晴らしいのは、そんな死や戦争の恐怖を痛切に描きながらも、それでもなお、必死に青春を生き抜こうとする若者たちを、本当に力強く、美しく、愛を込めて描いていることだと思うのです。
戦争を行ってしまうような人間の醜さ、恐ろしさはどんな時代でも変わらない普遍的なものであると同時に、人間の美しさもまた、普遍的なことだと思うのです。
人間の弱さから目を背けずに描きながらも、それでもなお、強さを描くことも諦めない、そここそがこの映画の描こうとしている希望だったのではないかと僕は思いました。
この映画を代表する台詞に、「青春が戦争の消耗品なんてまっぴらだ」というものがあります。
抗うことの出来ないような恐ろしい時代がきたとしても、それでも生き抜いていこうとする力強さが、この映画にはあると思うのです。
この時代に、こんなにも美しく、こんなにも力強い映画を作っていただき、大林宣彦監督、本当にありがとうございます!という気持ちです。