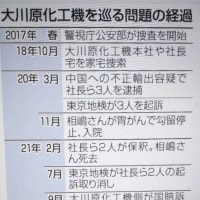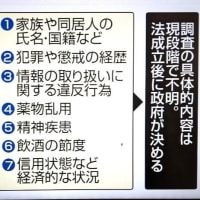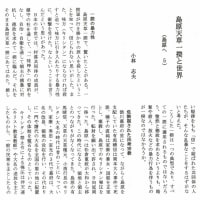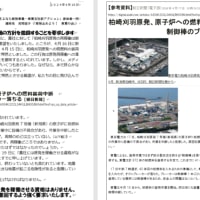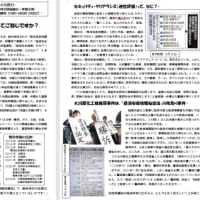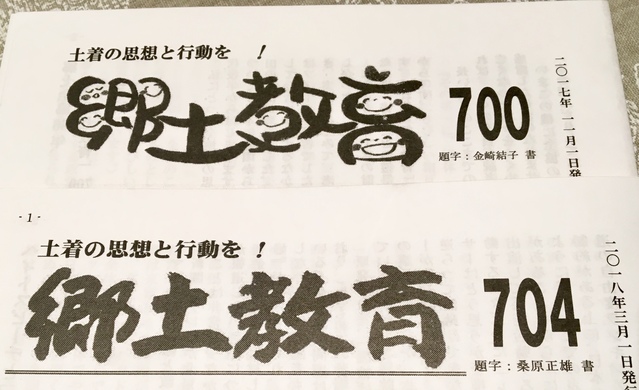私が関わっている「江戸川教育文化センター」のブログに以下の文を投稿したのは2019年3月でした。
この状況は基本的に現在も変わっていないではないでしょうか・・・。
結果的に教員になったばかりのBさんは職場を去ってしまうのですが、この時にAさんは彼女にとって唯一の頼れる存在だったに違いありません。
因みにAさんはその後、機関誌『郷土教育』の読者になり、何度となく現場実践を投稿していただいたものです。
なお、この「若い教員を育てられない教育委員会と学校現場」は、今後、数回にわたって連載することにします。
教員OBとして黙ってはいられない状況が各地の学校現場に発生し続けている。
文科当局はもちろんのこと、地教委や現場責任者の校長たちにまで学校教育の劣化現象に拍車をかける言動が蔓延しているのだ。
このクニの教育を司る政府機関である文科省は、現政権の腐敗状況に合わせるがごとく教育を国家の支配体制に押し込もうと躍起になっている。
それを忖度するかのように各教育委員会幹部や校長連中、さらに校長の意を受けた副校長や主幹等の幹部教員たちが自分にとっての目先の利益のみを追究して動いているからである。
そこには、いかにして学校における主役である子どもたちに学習主体としての力をつけていくべきか、そして、子どもたちを指導する教員たちがいかに主体的・協働的に仕事ができるようになっていくべきか・・・、という視点が完全に欠落している。
そこで、私の友人Aさんからの情報を具体例にとりあげて検証していきたいと思う。
Aさんは、新規採用されたBさんと同じ学校の低学年グループに属していた。
ところが、昨年、Bさんは勤務開始からわずかの期間で退職してしまったというのだ。
彼女の身に何が起こったのか、私は未だ明確には分かっていないが、おおよそのことは想像できる。
以下に、BさんからAさんに宛てられた手紙文を紹介する。
この度、私は学校をやめることになりました。
子どもにも、先生方にも、散々迷惑をかけたままやめてしまうのは無責任だろうかとくりかえし考えましたが、どうしても学校に戻る決断ができませんでした。
Aさんには色々と相談にのっていただいたのに、このようなことになってしまい、本当に申し訳ないです。
低学年の先生の中でAさんには一番お世話になりました。
何かわからないことがあったらいつも丁寧に教えていただいて、本当にありがたかったです。
私が休み出してしまってからも、唯一連絡をくださったのがAさんで、嬉しかったです。
私は、一旦学校をやめることになりますが、子どもや教員という職が嫌になった訳ではありません。
休んでいる間に、私は子どもが好きなのだと実感しました。
少し時間をおいて、来年でも、再来年でも、気持ちが落ち着いたらもう一度チャレンジできればと思っています。
短い時間の中で、本当にお世話になりました。
たった2ヶ月、我慢が足りない、こらえ性がないと思われても仕方がないかもしれません。
逃げるようにやめてしまう私を許してください。
いつかまた、ゆっくりお話しできる日が来ることを願っています。
この手紙を読んで、私は何とも言えない悲しさと怒りのようなものが湧いてきた。
私にこれを紹介してくれたAさんにしても同様な思いがあるに違いない。
(つづく)
-S.S-
この状況は基本的に現在も変わっていないではないでしょうか・・・。
結果的に教員になったばかりのBさんは職場を去ってしまうのですが、この時にAさんは彼女にとって唯一の頼れる存在だったに違いありません。
因みにAさんはその後、機関誌『郷土教育』の読者になり、何度となく現場実践を投稿していただいたものです。
なお、この「若い教員を育てられない教育委員会と学校現場」は、今後、数回にわたって連載することにします。
教員OBとして黙ってはいられない状況が各地の学校現場に発生し続けている。
文科当局はもちろんのこと、地教委や現場責任者の校長たちにまで学校教育の劣化現象に拍車をかける言動が蔓延しているのだ。
このクニの教育を司る政府機関である文科省は、現政権の腐敗状況に合わせるがごとく教育を国家の支配体制に押し込もうと躍起になっている。
それを忖度するかのように各教育委員会幹部や校長連中、さらに校長の意を受けた副校長や主幹等の幹部教員たちが自分にとっての目先の利益のみを追究して動いているからである。
そこには、いかにして学校における主役である子どもたちに学習主体としての力をつけていくべきか、そして、子どもたちを指導する教員たちがいかに主体的・協働的に仕事ができるようになっていくべきか・・・、という視点が完全に欠落している。
そこで、私の友人Aさんからの情報を具体例にとりあげて検証していきたいと思う。
Aさんは、新規採用されたBさんと同じ学校の低学年グループに属していた。
ところが、昨年、Bさんは勤務開始からわずかの期間で退職してしまったというのだ。
彼女の身に何が起こったのか、私は未だ明確には分かっていないが、おおよそのことは想像できる。
以下に、BさんからAさんに宛てられた手紙文を紹介する。
この度、私は学校をやめることになりました。
子どもにも、先生方にも、散々迷惑をかけたままやめてしまうのは無責任だろうかとくりかえし考えましたが、どうしても学校に戻る決断ができませんでした。
Aさんには色々と相談にのっていただいたのに、このようなことになってしまい、本当に申し訳ないです。
低学年の先生の中でAさんには一番お世話になりました。
何かわからないことがあったらいつも丁寧に教えていただいて、本当にありがたかったです。
私が休み出してしまってからも、唯一連絡をくださったのがAさんで、嬉しかったです。
私は、一旦学校をやめることになりますが、子どもや教員という職が嫌になった訳ではありません。
休んでいる間に、私は子どもが好きなのだと実感しました。
少し時間をおいて、来年でも、再来年でも、気持ちが落ち着いたらもう一度チャレンジできればと思っています。
短い時間の中で、本当にお世話になりました。
たった2ヶ月、我慢が足りない、こらえ性がないと思われても仕方がないかもしれません。
逃げるようにやめてしまう私を許してください。
いつかまた、ゆっくりお話しできる日が来ることを願っています。
この手紙を読んで、私は何とも言えない悲しさと怒りのようなものが湧いてきた。
私にこれを紹介してくれたAさんにしても同様な思いがあるに違いない。
(つづく)
-S.S-