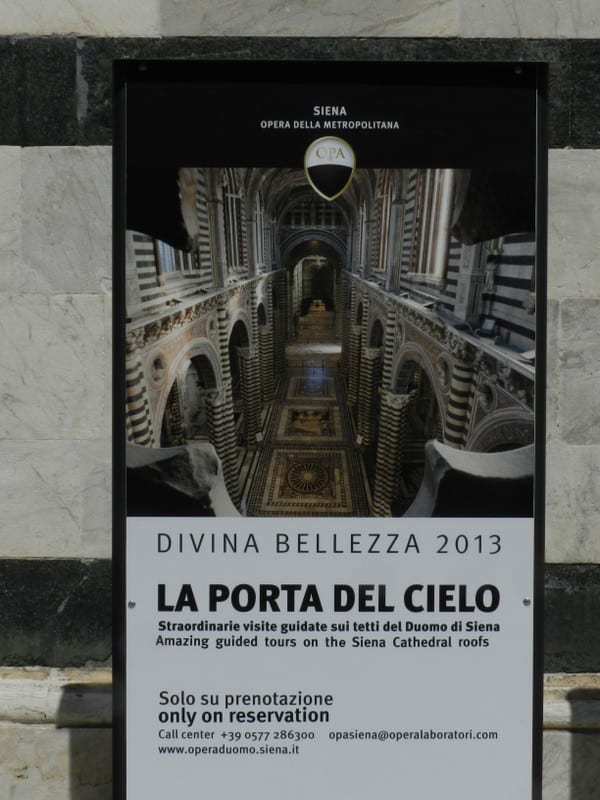通称Forte Belvedere
(フォルテ・ベルヴェデーレ/ベルヴェデーレ要塞)
と呼ばれていますが、
正式名称は
Fortezza di Santa Maria in San Giorgio del Belvedere
(サンタ・マリア・イン・サン・ジョルジョ・
デル・ベルヴェデーレ要塞)。
フィレンツェにある二つの要塞のうちの一つです。
因みにもう一つの要塞はFortezza da Basso(バッソ要塞)。
ベルヴェデーレ要塞はボボリ庭園の広がる丘の最丁部にあり、
その眺望の良さもよく知られています。
ルネッサンス期の要塞として現存するもののなかでも
最も美しい要塞の一つとされています。

1590年から1595年にかけて
コジモ1世の息子である
Ferdinando I de' Medici
(トスカーナ大公フェルディナンド1世)の命で
建設されました。
手がけたのはメディチ家のお抱え建築家
Bernardo Buontalenti(ベルナルド・ブオンタレンティ)。
メディチ家がフィレンツェ追放から復帰し、
1527年のフィレンツェ掠奪を経て
1529年に建設されたバッソ要塞は
当時のメディチ家の邸宅があったVia Larga
(現在のメディチ・リッカルディ宮殿周辺)の
防衛目的がメインでしたが、
ベルヴェデーレ要塞は
コジモ1世以降にメディチ家が居住するようになった
ピッティ宮殿とその周辺(アルノ川左岸地区)の防衛と
メディ家の権力誇示の目的で建設されています。
ヴェッキオ宮殿からウフィツィ、ヴェッキオ橋を経て
ボボリ庭園からピッティ宮殿に繋がる
かの有名な「ヴァザーリの回廊」プロジェクトの
延長線上にある要塞です。
ピッティ宮殿の裏手に広がる要塞であり、
なにかの時にはメディチ家が避難できる場所として
重要なポイントでもありました。
このため、アルノ川から引き込んだ水を利用できるように
巨大な井戸も作られ、現在も円筒形の建物が残っています。

*画面のちょうど正面にある円筒形の建物が井戸です。
実際、1600年に街にペストが流行したとき、
フェルディナンド1世はピッティ宮殿から要塞に移り、
ただ市民の反感を煽らないようにするためだけに
毎日数時間街におりて様子を見るという
日々を過ごしたとも言われています。
フィレンツェにある二つの要塞が
メディチ家の命で建てられ
それぞれが実際には外敵から街を護るためではなく
街の中にいる様々な敵に自分たちの権力を見せつけ
彼らからの攻撃を抑制するために使われたのです。
この二つの要塞が建設されてから
メディチ家に表立って逆らうものがいなくなり、
実際、高台にあるベルヴェデーレ要塞には
立派な砲台が設けられていますが、
正午を知らせる時報を打つ以外は
一度も敵に向けて発砲されたことはありませんでした。
1700年代の終わりにPietro Leopoldo
(トスカーナ大公ピエトロ・レオポルド)が
要塞に逃げ込み、
彼に対して反逆し始めた市民に向けて
発砲するように命じていますが、
防衛にあたっていた兵士たちは
自国民に向けて発砲できないとして任務を放棄しています。
高い城壁と大きな砦をもちながら
その中央にある建物は城というよりは
エレガントな白壁の3階建ての邸宅で
Palazzina di Belvedere
(ベルヴェデーレの小宮殿)と呼ばれます。
1570年のBartolomeo Ammannati
(バルトロメオ・アンマンナーティ)の
デザインによるものとされています。

メディチ家はその長い統治期間中に
市内に数多くの秘密の通路を作らせています。
そのうちの一つがピッティ宮殿から
ボボリ庭園の下を通過してベルヴェデーレ要塞に至るもので
その先には「メディチ家の秘宝の間」があったと
長いこと言い伝えられていました。
ごく近年になって、
実際にその秘宝の間が存在したことが明らかになっていますが、
発見された時はもちろん中は空っぽでした。
ベルヴェデーレ要塞の小宮殿の
開廊の地下深くにある岩に掘られた小さな部屋で
容易に近づくことができないように
ブオンタレンティによって
様々な罠が仕掛けられていたようです。
たとえば、小宮殿からは
狭い小さな階段を使って
アクセスできるようになっていましたが、
その一部は木製の梯子で、
必要に応じて取り外しが可能な、
跳ね橋のような構造になっていたり、
下に鋭利な刃を満たした落とし穴があったり、
フェルディナンド1世とブオンタレンティしか
解錠の仕方を知らない、複雑な鍵がかけられていたり、
侵入者がいた場合に自動で発射する銃が仕掛けられていたり。
すべてを乗り越えて秘密の部屋に到達しても
最終的に部屋全体を水で満たして溺死させ、
アルノ川に流しだすシステムまで備えられていたようです。
この秘密の部屋にはアクセスできませんが、
2013年7月8日から5年ぶりに
ベルヴェデーレ要塞が一般公開になっていますので
機会があれば、
ミケランジェロ広場とはまたちょっと違う高さからの
フィレンツェ一望を楽しんでみてください。


ヴェッキオ橋を渡った先から
Costa San Giorgioを登っていくと
サン・ジョルジョ門を越えて右手に入り口があります。

コスタ・サンジョルジョは結構な上り坂。
でもお散歩にはもってこいの道でもあります。

これはサン・ジョルジョ門を
ベルヴェデーレ方面から見たところ。
坂から登っていくと、門のアーチの下には
ボロボロの「聖レオナルドと聖ジョルジョと聖母子」の
ルネッタがかけられています。
(フォルテ・ベルヴェデーレ/ベルヴェデーレ要塞)
と呼ばれていますが、
正式名称は
Fortezza di Santa Maria in San Giorgio del Belvedere
(サンタ・マリア・イン・サン・ジョルジョ・
デル・ベルヴェデーレ要塞)。
フィレンツェにある二つの要塞のうちの一つです。
因みにもう一つの要塞はFortezza da Basso(バッソ要塞)。
ベルヴェデーレ要塞はボボリ庭園の広がる丘の最丁部にあり、
その眺望の良さもよく知られています。
ルネッサンス期の要塞として現存するもののなかでも
最も美しい要塞の一つとされています。

1590年から1595年にかけて
コジモ1世の息子である
Ferdinando I de' Medici
(トスカーナ大公フェルディナンド1世)の命で
建設されました。
手がけたのはメディチ家のお抱え建築家
Bernardo Buontalenti(ベルナルド・ブオンタレンティ)。
メディチ家がフィレンツェ追放から復帰し、
1527年のフィレンツェ掠奪を経て
1529年に建設されたバッソ要塞は
当時のメディチ家の邸宅があったVia Larga
(現在のメディチ・リッカルディ宮殿周辺)の
防衛目的がメインでしたが、
ベルヴェデーレ要塞は
コジモ1世以降にメディチ家が居住するようになった
ピッティ宮殿とその周辺(アルノ川左岸地区)の防衛と
メディ家の権力誇示の目的で建設されています。
ヴェッキオ宮殿からウフィツィ、ヴェッキオ橋を経て
ボボリ庭園からピッティ宮殿に繋がる
かの有名な「ヴァザーリの回廊」プロジェクトの
延長線上にある要塞です。
ピッティ宮殿の裏手に広がる要塞であり、
なにかの時にはメディチ家が避難できる場所として
重要なポイントでもありました。
このため、アルノ川から引き込んだ水を利用できるように
巨大な井戸も作られ、現在も円筒形の建物が残っています。

*画面のちょうど正面にある円筒形の建物が井戸です。
実際、1600年に街にペストが流行したとき、
フェルディナンド1世はピッティ宮殿から要塞に移り、
ただ市民の反感を煽らないようにするためだけに
毎日数時間街におりて様子を見るという
日々を過ごしたとも言われています。
フィレンツェにある二つの要塞が
メディチ家の命で建てられ
それぞれが実際には外敵から街を護るためではなく
街の中にいる様々な敵に自分たちの権力を見せつけ
彼らからの攻撃を抑制するために使われたのです。
この二つの要塞が建設されてから
メディチ家に表立って逆らうものがいなくなり、
実際、高台にあるベルヴェデーレ要塞には
立派な砲台が設けられていますが、
正午を知らせる時報を打つ以外は
一度も敵に向けて発砲されたことはありませんでした。
1700年代の終わりにPietro Leopoldo
(トスカーナ大公ピエトロ・レオポルド)が
要塞に逃げ込み、
彼に対して反逆し始めた市民に向けて
発砲するように命じていますが、
防衛にあたっていた兵士たちは
自国民に向けて発砲できないとして任務を放棄しています。
高い城壁と大きな砦をもちながら
その中央にある建物は城というよりは
エレガントな白壁の3階建ての邸宅で
Palazzina di Belvedere
(ベルヴェデーレの小宮殿)と呼ばれます。
1570年のBartolomeo Ammannati
(バルトロメオ・アンマンナーティ)の
デザインによるものとされています。

メディチ家はその長い統治期間中に
市内に数多くの秘密の通路を作らせています。
そのうちの一つがピッティ宮殿から
ボボリ庭園の下を通過してベルヴェデーレ要塞に至るもので
その先には「メディチ家の秘宝の間」があったと
長いこと言い伝えられていました。
ごく近年になって、
実際にその秘宝の間が存在したことが明らかになっていますが、
発見された時はもちろん中は空っぽでした。
ベルヴェデーレ要塞の小宮殿の
開廊の地下深くにある岩に掘られた小さな部屋で
容易に近づくことができないように
ブオンタレンティによって
様々な罠が仕掛けられていたようです。
たとえば、小宮殿からは
狭い小さな階段を使って
アクセスできるようになっていましたが、
その一部は木製の梯子で、
必要に応じて取り外しが可能な、
跳ね橋のような構造になっていたり、
下に鋭利な刃を満たした落とし穴があったり、
フェルディナンド1世とブオンタレンティしか
解錠の仕方を知らない、複雑な鍵がかけられていたり、
侵入者がいた場合に自動で発射する銃が仕掛けられていたり。
すべてを乗り越えて秘密の部屋に到達しても
最終的に部屋全体を水で満たして溺死させ、
アルノ川に流しだすシステムまで備えられていたようです。
この秘密の部屋にはアクセスできませんが、
2013年7月8日から5年ぶりに
ベルヴェデーレ要塞が一般公開になっていますので
機会があれば、
ミケランジェロ広場とはまたちょっと違う高さからの
フィレンツェ一望を楽しんでみてください。


ヴェッキオ橋を渡った先から
Costa San Giorgioを登っていくと
サン・ジョルジョ門を越えて右手に入り口があります。

コスタ・サンジョルジョは結構な上り坂。
でもお散歩にはもってこいの道でもあります。

これはサン・ジョルジョ門を
ベルヴェデーレ方面から見たところ。
坂から登っていくと、門のアーチの下には
ボロボロの「聖レオナルドと聖ジョルジョと聖母子」の
ルネッタがかけられています。