
―表象の森― ある文明の幻影
渡辺京二「逝きし世の面影」より -№1-
著者渡辺京二は、幕末から明治にかけ来日した多くの外国人たちが書き残した記録や文書、邦訳されているものだけでも130にも及ぶ夥しい資料を踏査、彼ら異邦人たちなればこそ語り得た、この国の姿、庶民たちの生活実相を、12の章立てで本書を構成、近代日本の夜明け前の風景が一大絵巻の如く眼前にひろがる感がある。
1.ある文明の幻影
・まずは本章の最後に置かれた著者の言を引く。
私の意図するのは古きよき日本の愛惜でもなければ、それへの追慕でもない。私の意図はただ、ひとつの滅んだ文明の諸相を追体験することにある。外国人のあるいは感激や錯覚で歪んでいるかもしれぬ記録を通じてこそ、古い日本の文明の奇妙な特性がいきいきと浮かんでくるのだと私はいいたい。そしてさらに、われわれの近代の意味は、そのような文明の実態とその解体の実相をつかむことなしには、けっして解き明かせないだろうといいたい。
・また、本章半ばあたりに展開される論
文化人類学の青木保によれば、翻訳-interpretation-不可能性の自覚こそ、異文化の核心に近づくための前提である。
Singular-風変わりな-とかstrange-奇妙な-というのは、理解不能あるいは理解の必要のないものとして対象を突き放す-そういいたければ差別する-態度の表白でもありうるが、おのれの異質なものに接した驚きを起点として、おのれの文化的拘束を自覚し、他文化をその内面に即して理解しようとする真摯な努力に道を開くものでもありうるのだ。
・オズボーン-Sherard Osborne、1822-75-と、オリファント-Laurence Oliphant、1829-88-はともに、1858(安政5)年日英修好通商条約締結のため来日したエルギン卿使節団の一員、Osborneに「A Cruise in Japanese Waters」、Oliphantに「エルギン卿遣日使節録」などの著書
Os「この町でもっとも印象的なのは男も女も子どもも、みんな幸せで満足そうに見えるということだった」
「衣服の点では、家屋と同様、地味な色合いが一般的で、中国でありふれているけばけばしい色や安ぴかものが存在しない。ここでは、上流夫人の外出着も、茶屋の気の毒な少女たちや商人の妻のそれも、生地はどんなに上等であっても、色は落ち着いていた。役人の公式の装いにおいても、黒、ダークブルー、それに黒と白の柄がもっとも一般的だった。彼らの家屋や寺院は同様に、東洋のどこと較べてもけばけばしく塗られていないし、黄金で塗られているのはずっと少ない」「あらゆる懐旧の普段着の色は黒かダークブルーで模様は多様だ。だが女は適当に大目に見られており、その特権を行使して、ずっと明るい色の衣服を着ている。それでも彼女らは趣味がよいので、けばけばしい色は一般に避けられる」
Ol「個人が共同体のために犠牲になる日本で、各人がまったく幸福で満足しているように見えることは、驚くべき事実である」「われわれの最初の日本の印象を伝えようとするには、読者の心に極彩色の絵を示さなければ無理だと思われる。シナとの対照がきわめて著しく、文明が高度にある証拠が実に予想外だったし、われわれの訪問の情況がまったく新奇と興味に満ちていたので、彼らの引き起こした興奮と感激との前にわれわれはただ呆然としていた。この愉快きわまる国の思い出を曇らせる嫌な連想はまったくない。来る日来る日が、われわれがその中にいた国民の、友好的で寛容な性格の鮮やかな証拠を与えてくれた」
・ブラック-John Reddie Black、1826-80- 1860年代初めから15年を超える滞在、著書「ヤング・ジャパン」
「思うに、他の国々を訪問したあとで、日本に到着する旅行者たちが、一番気持ちのよい特徴の一つと思うに違いないことは、乞食がいないことだ」
・いわゆるジャパニーズ・スマイルについて-フランス人画家レガメ-Felix Regamey、1844~1907- 著書「日本素描紀行」
日本人のほほえみは、「すべての礼儀の基本」であって、「生活のあらゆる場で、それがどんなに耐え難く悲しい状況であっても、このほほえみはどうしても必要なのであった」。それは金で購われるのではなく、無償で与えられるのである。
このようなほほえみ、後年、不気味だとか無意味だとか欧米人から酷評される日本人の照れ笑いではなく、欧米人にさえ一目でわかったこの古いほほえみは、レガメが二度目の来日を果たした1899(M33)年には、「日本の新しい階層の間では」すでに「曇り」を見せ始めていた。少なくともレガメの目にはそう映った。
・リュドヴィク・ボーヴォワル-Ludvic Beauvoir-1849~1929、1867(慶応3)年来日、著書「ジャポン1867」
彼にとって、日本は妖精風のLilliput-小人国-であった。「どの家も樅材で作られ、ひと刷毛の塗料も塗られていない。感じ入るばかりに趣があり、繊細で清潔且つ簡素で、本物の宝石、おもちゃ、小人国のスイス風牧人小屋である。‥日が暮れてすべてが閉ざされ、白一色の小店の中に、色さまざまな縞模様の提灯が柔らかな光を投げる時には、魔法のランプの前に立つ思いがする」
「漆塗りの小さな飾り物、手袋入れの箱、青銅のブローチ」など、「つまらぬものだが可愛い品々」、この「こまごまとした飾り物」こそ彼が発見した日本だった。彼はそういったものに「目がまわらんばかりに酔わされた」、漆器にいたっては、彼の魅了されぶりは「まさに熱病そのものであった」
・エミール・ギメ-Emile Guimei、1836-1918- 世界有数の東洋博物館として知られるギメ博物館の創設者1876(M9)年来日、滞在3ヶ月、著書「1876ボンジュールかながわ」「東京日光散策」
日本の第一印象は「すべてが魅力にみちている」、古代ギリシャのような日本人の風貌や、井戸に集う「白い、バラ色の美しい娘たち」や、ひと目で中を見通せる住居の、すべてが絵になるような、繊細で簡素なよい趣味や、輝くばかりの田園風景について、惜しみない讃嘆の声をあげる。
サンパンの漕ぎ手たちが発する「調子のとれた叫び声」、重い荷車を引く車力が一引きごとに繰り返す「ソコダカ・ホイ」という歌に似た叫びや、漁師たちの櫓のひとかきごとに出す「鋭い断続的な叫び」、ホテルの窓の下を通る「幅の広い帯を締め、複雑な髪を結った」女たちの、笑い声や陽気で騒々しい会話や、宿屋で見送りの女中たちが叫ぶ「サイナラ」という裏声にいたるさまざまな音に心奪われ、ギメにとって日本はなによりもまず、このような肉感的な物音のひしめく世界として現れた。
彼は、鎌倉の八幡宮や大仏を見たあと、片瀬の宿屋に泊まった。床について灯りを消すが、耳慣れぬ物音が続いて眠れぬ夜を過ごした。まずは波の音-海が震えている、その規則正しい音に混じって、ジ・ジというリズミカルな「一種の鳴き声が家の周りを走る」。そして「木から木へ飛び移る恐ろしい呻き声」、その正体は、風が聖なる杉林を揺り動かし、山が震え唸っているのだ。「星がきらめく夜空の下で、山が海に応え、陸と海とが」二重唱を歌っているのだった。日本の夜にはさまざまの霊や精が呼吸していて、人々はその息吹に包まれて眠るのだと感じて、感銘を覚えずにおれなかったのだ。
・チェンバレン-Basil Hall Chamberlain- 1873(M6)来日、1911(M44)年までの長きを滞在、著書「日本事物誌」「明治旅行案内」
「古い日本は妖精の住む小さくて可愛いらしい不思議の国であった」。しかし「教育ある日本人は彼らの過去を捨ててしまっている。彼らは過去の日本人とは別の人間、別のものになろうとしている」
・ポルスブルック-Dirk de Graeff van Polsbroek、1833-1916-オランダ商館員、著書「ポルスブルック日本報告1857-1870」
「私の思うところヨーロッパのどの国より高い教養を持っているこの平和な国民に、我々の教養や宗教が押しつけられねばならないのだ。私は痛恨の念を持って、我々の侵略がこの国と国民にもたらす結果を思わずにいられない。時がたてば、分かるだろう」
・エドウィン・アーノルド-Edwin Arnold、1832~1904- 1889(M22))年来日、原書「Japonica」
「地上でParadise-天国-あるいはLotus land-極楽-にもっとも近づいている国だ」と賞讃し、「その景色は妖精のように優美で、その美術は絶妙であり、その神のように優しい性質はさらに美しく、その魅力的な態度、その礼儀正しさは、謙虚ではあるが卑屈に堕することなく、精巧であるが飾ることもない。これこそ日本を、人生を生き甲斐あらしめるほとんどすべてのことにおいて、あらゆる他国より一段と高い地位に置くものである」
「あなた方の文明は隔離されたアジア的生活の落ち着いた雰囲気の中で育ってきた文明なのです。その文明は、競い合う諸国家の衝突と騒動の只中に住むわれわれに対して、命を甦らせるようなやすらぎと満足を授けてくれる美しい特質を育んできたのです」
「寺院や妖精じみた庭園の睡蓮の花咲く池の数々のほとりで、鎌倉や日光の美しい田園風景の只中で、長く続く荘重な杉並木のもとで、神秘で夢みるような神社の中で、茶屋の真っ白な畳の上で、生き生きとした縁日の中で、さらにまたあなたの国のまどろむ湖のほとりや堂々たる山々のもとで、私はこれまでにないほど、わがヨーロッパの生活の騒々しさと粗野から救われた気がしているのです」
などと歓迎晩餐会でスピーチをしたが、翌朝の主要各紙の論説は、彼が日本の産業、政治、軍備における進歩にいささかも触れなかったことに、日本の軽視であり侮蔑であると憤激した。
<連句の世界-安東次男「風狂始末-芭蕉連句評釈」より>
「雁がねの巻」-35
馳走する子の痩てかひなき
花の比談義参りもうらやまし 越人
花の比-ころ-
次男曰く、花どきともなれば、子を連れて法話の一つも聞きに参詣するのが世の親の常だが、生薬屋に「痩てかひなき」と云われては気後れする。先生などに首筋を掴まれたのが運の尽きかも。とぼやきながらも、陰気にふさぎ込んでいるわけではない、花疲れの微妙な心を読取らせる句ぶりである。
「花の比」という遣方は、芭蕉の脇「この比の月」と一対にする狙いだろう。腐されたりおだてられたり、まあそのうちなんとかなるさ、見ていてほしいと言いたげな口吻である。肚をくくった句姿はなかなか良い、と。
⇒⇒⇒ この記事を読まれた方は此処をクリック。











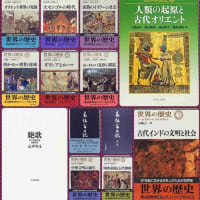
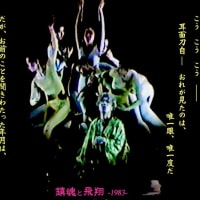
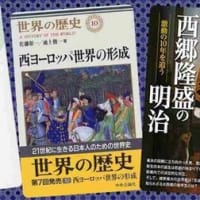
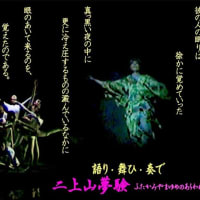
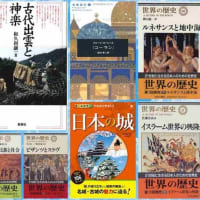
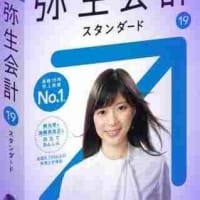
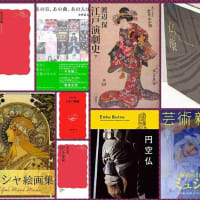
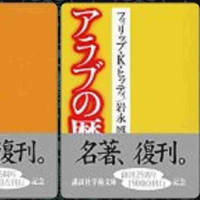
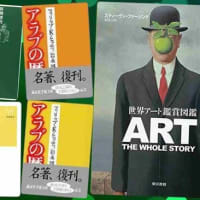
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます