
―表象の森― 嗅覚と観念の相似性
<A thinking reed> 中井久夫「徴候・記憶・外傷」より
T.S.エリオットは「観念を薔薇の花の匂いのごとくに感じる」と、ある評論の中で言った。
観念には匂いと非常に似ているところがある。それは一時には一つしか意識の座を占めない。二つの匂いが同じ強度で共在することはあり得ないが、観念もまた、二つが同じ強度で共存することは-ある程度以下の弱く漠然としたものを除いては-きわめて例外的で、病的な状態において辛うじてありうるか否か、というくらいだ。
また、匂いは、20秒くらいしか留まらない。匂い物質はなお送られてきていても、それに対する嗅覚は急速に作動しなくなってしまう。これは嗅覚が新しい入力に対応するためで、こうでなくてはならない。
観念を虚空に把握しつづけることも、20秒以上は難しいのではないか。とすれば、持続的といわれる幻覚、妄想、固定観念も、絶えざる入力によって繰り返し再出現させて維持されていることを示唆する。ただ、この入力は、決して<自由意志>によるものではない。
さらに、両者とも、起こそうとして起こせるものではなく、ともに、基本的には意識を<襲う>ものである。少なくとも重要な気づきは、はげしい香りと同じく、人を撲つ、科学的、思想的発見であっても、パーソナルな気づきであっても。
匂いも、観念も、ごく僅かな原因物質によって触発される。観念もきわめて些細な、しばしば意外な因子によって触発される。決して方法論に還元し得ないというところがある。
精緻な<意識的方法論>ら拠る研究は堂々たる構えを持ちながら、その向う側が意外に貧しい場合も皆無ではない。これは方法論に拠る人の問題ではなく、方法論に拠るということ自体の持つ欠陥である。観念は生き物であって、鮮度を失わずに俎上にのせることにはある職人的熟練を要する。
なお、匂いはしばしば同定しがたい。観念もまた、その由来を尋ねるに由ないところがある。また、的確な定義のはなはだ難しいことは、よく人の知るところだろう。
「限定され尽くせばその観念の歴史においては結末、いわばその観念の死あるいは化石死である」とさえ言いうる。
<連句の世界-安東次男「風狂始末-芭蕉連句評釈」より>
「雁がねの巻」-34
いかめしく瓦庇の木薬屋
馳走する子の痩てかひなき 芭蕉
痩-やせ-てかひ-甲斐-なき
次男曰く、馳走は奔走である。設けなくして奔走することはないから、転じてもてなしの意にもなれば、大切にする意にもなる。
一読、伝統も学問も財産もあるらしい生薬屋には得てして病弱の子が生まれる、前を読んだ作りのようにみえるが、「馳走する子」を越人と読替えればここにも当意即妙の含が生まれる。
尤もいくらなんでも、お前は育て甲斐がない、では越人に酷と思われるかもしれぬが、ここは一巻中とりわけ大切な名残の花の座の前である。最初の花を芭蕉-亭主-が務めていれば名残は当然越人-客-が務める。
「砧も遠く」の句以下主客ところを取替え、師弟の位相が読取れる応酬の展開になっていた。その客の位をもう一度越人に返すところに、この付の妙味がある。こういう面白さは両吟であってのことで、数人で興行してもなかなか現れてこない。
「痩てかひなき」と云い一層大切にする狙いがある、とはおのずと納得できる。軽口で返しながらまったく骨太い句を作るものだ。
そういう句を諸注は、
「構へいかめしく裕福なる家の、愛児のためにさまざま骨折れども、萎黄憔悴して、其功無きなり」-露伴-とか、
「なかなかままならぬというのが世相の一面というものであろう。前句とあわせて、薬屋の子の病がちというところに、俳諧的な皮肉と笑いがこめられている」-中村俊定-などと読んで済ます。
これではどうにもならぬ。越人が心機一転して務める花の定座の心底も見えてこないだろう、と。
⇒⇒⇒ この記事を読まれた方は此処をクリック。











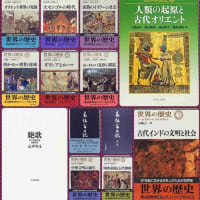
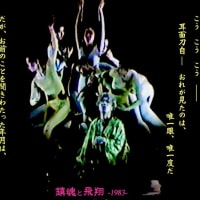
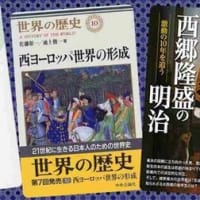
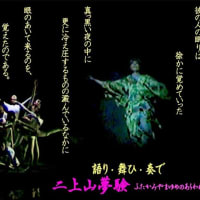
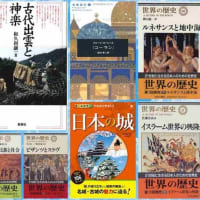
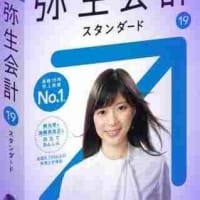
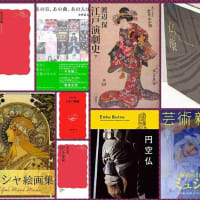
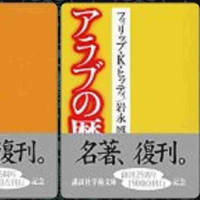
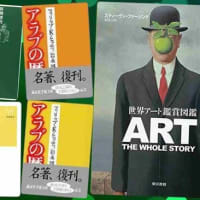
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます