
-表象の森- 白土三平の「忍者武芸帳」
漫画-アニメの系譜における巨匠といえばなんといっても手塚治虫なのだろうが、漫画-劇画-コミックスの系譜で革命的な存在であったのは白土三平が屈指だろう。
私が嘗て長編の漫画をまがりなりも通読したのは、白土三平の「忍者武芸帳」と山岸涼子の「日出処の天子」くらいなのだが、それでも「ガロ」などに連載されていた白土の「カムイ伝」や「カムイ外伝」を時折は読んだりしていた。
このほど四方田犬彦の「白土三平論」(作品社2004年刊)をざっと読んでみたのだが、彼の代表作「忍者武芸帳」や「カムイ伝」に関する詳細な読解に導かれ、お蔭で遠い記憶が甦ってきた。
1950年代後半から60年代、貸本漫画のドル箱的名作、白土三平の「忍者武芸帳」は59年から62年まで、足かけ3年にわたって執筆された。当時としては型破りのこの長編劇画は、貸本漫画界において記念碑的ともいえる作品であった。
白土三平の父岡本唐貴(1903年生れ)は、1946(S21)年の終戦まもなく矢部友衛と共著で「民主々義美術と綜合リアリズム」を上梓出版、1967(S42)年には松山文雄とともに大部の「日本プロレタリア美術史」を執筆刊行した左翼的理論派の画家であった。白土三平の本名は登、1932年、その唐貴の長男として生まれた。1948年から紙芝居の世界に関わるようになり、紙芝居作家として、また指人形劇団に所属し舞台の背景画家として、57(S32)年頃まで活躍し、以後、漫画家へと転身している。彼が紙芝居の世界に入った頃は、東京だけで3000人、全国では5万人の街頭紙芝居屋が居たと伝えられる全盛期であったが、昭和30年代のテレビの普及ともに、紙芝居は急速に衰退し消えゆく運命となった。三平に漫画家へと転身の機会を与えたのは牧数馬であり、牧の少女漫画などの下絵描きからスタートした。ちなみに「太郎座」という指人形劇団には、後に民話探訪などで活躍する瀬川拓男や児童文学者松谷みよ子らがともに居たというが、このあたりの事情については「白土三平ファンページ」に詳しい。
白土三平の「忍者武芸帳」が貸本漫画に続々と登場してきた60(S35)年前後は漫画のみならず文芸や映画など大衆芸術でも時ならぬ忍者ブームであった。それは安保闘争に揺れ動いた激動の季節という時代相の反映でもあったろう。59(S34)年には司馬遼太郎の「梟の城」がこの年の直木賞を受賞。これと相前後するように、山田風太郎が「風太郎忍法」シリーズを次から次と世に出し大衆的人気を博していた。映画界では市川雷蔵主演の「忍びの者」シリーズの第1作が、名匠山本薩夫監督で62(S37)年12月に公開され、3作目からは監督が代わるものの、以後、66(S41)年12月公開の「新書・忍びの者」まで8作品を生み出しているが、この原作は、劇作家として演出家として戦前戦後の左翼的演劇につねに指導的役割を演じてきた村山知義の同名小説「忍びの者」であり、この小説は60年11月から62年5月まで、「赤旗日曜版」に毎週連載されたものであった。父親の岡本唐貴と親しい知己にあった村山知義の「忍びの者」が、ほぼ時を同じくするように書き継がれていった白土三平の「忍者武芸帳」に少なからぬ影響を及ぼしていたことは十分考えられることである。
村山知義の「忍びの者」は、山田風太郎や司馬遼太郎作品に比べても、忍者というものの生態やその術のありようなど、あらゆる面ではるかにリアリスティックな描写世界となっている。上忍と下忍という身分差別や過酷な主従関係のもとに、敵対し死闘を演じつづける二つの忍者組織が、真相は同一人物によって支配されていたものであり、擬装の権力構造のカラクリが物語の進行とともに暴かれ、主人公石川五右衛門の人間的な苦悩に焦点が絞られていくという社会派時代小説だったのだが、この「忍びの者」がとりわけ日曜版とはいえ「赤旗」連載の小説であったことを考えると、映画化するについても当時の制作会社大映としては相当の勇気ある英断を要したにちがいない。
社会の現実の悲惨を綺麗ごととして処理せず、あらゆる感傷を排除してリアリスティックな眼差しをそこに向けようとする強い意志は、村山知義と同様、白土三平の姿勢にもよく顕われているといえよう。エロティシズムであれグロティシズムであれ、人間的なるものの一切を隠蔽せずに描いてゆくとともに、その人間的なるものが大自然の法則を前にしてはほとんど無意味・無価値たらざるをえないことをも提示していくのが白土三平の「忍者武芸帳」であり、その後の「カムイ伝」であった。
四方田の「白土三平論」に依拠すれば、「彼の忍者漫画を他の作家のそれから決定的に峻別しているものがあるとすれば、それは忍者を単に人間界における権力争いの中での暗殺者の位置に置くことに満足せず、さらに認識をひろげて、自然と人間のとり結ぶトリックスター的な媒介者と規定したところ」に特徴づけられよう。白土作品のなかの忍者たちとは、「彼らの活動の領域にあっては特権的な個人など存在せず、だれもが交換可能で本来的に匿名の存在であるという原理」に貫かれており、「忍者武芸帳」において主人公影丸が殺されても殺されても蘇生してくる超自然的なありようは、「歴史における個人の、抽象的な代替可能性ではなく、あらゆる個人が狭小な個人性の枠から離脱し、歴史的な闘争の主体として匿名を帯びることと本質的に複数制のもとにあるというシステムを体現するもの」であり、白土三平は「忍者武芸帳」において、「歴史が闘争を通して、みずからに必然的な自己実現を遂げてきたとする、ヘーゲル=マルクス主義を下敷きとした世界観に裏打ちされたかのように展開」された作品をものし、「60年代の新左翼の学生運動家たちにとって、当時の第三世界の解放神話と並んで、人民解放の神学的基礎ともいうべき言説として受けとめられ、漫画とはいえ一大叙事詩の世界を描きあげた白土三平はカリスマ的な存在」となったのである。
<歌詠みの世界-「清唱千首」塚本邦雄選より>
<夏-26>
われはけさうひにぞ見つる花の色をあだなるものといふべかりけり
紀貫之
古今集、物名、さうび。
邦雄曰く、薔薇(ショウビ)、和様に訛って「さうび」を上句に詠み込んだ物名歌。現在の野茨に類する花だが、貫之は李白の詩等に用いられた文字による知識で、歌に採り入れたのだろう。実際に舶来栽培されるのは鎌倉期頃とされている。また夏の襲(カサネ)色目にも薔薇(サウビン)が見える。今日見る薔薇は、唐代では長春花等の名で呼ばれた。古歌に薔薇はこれ一首のみ、と。
みよしのの吉野の瀧に浮かび出づる泡をか玉の消ゆと見つらむ
紀友則
古今集、物名、をがたまの木。
邦雄曰く、詠み込まれたのは木蓮科の香木「小賀玉の木」。花は泰山木同様芳香を放ち、多く神域に植えられている。古今伝授三木の一。一首の表層の意味も悠々たる眺めをもち、主題の木と両々響き合うところがある。友則はこの物名歌で、「女郎花」「桔梗の花」「龍膽(リョウタン)の花」等に、物名に止まらぬ秀作を見せている。古歌の小賀玉の木も他にない、と。
⇒⇒⇒ この記事を読まれた方は此処をクリック。















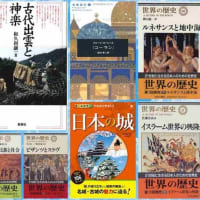




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます