
風姿花伝にまねぶ-<4>
十二、三より
「此年の比(ころ)よりは、はや、やうやう、声も調子にかゝり、能もこころづく比なれば、
次第々々に、物数を教ふべし。先(まづ)、童形(どうぎゃう)なれば、何としたるも、幽玄なり。声も立つ比也(ころなり)。-略-
児(ちご)と言ひ、声と言ひ、しかも上手ならば、何かは悪かるべき。さりながら、此花は、まことの花にはあらず。たゞ時分の花なり。-略-
さる程に、一期(いちご)の能の定めには、成るまじきなり。此比(このころ)の稽古、易き所を花に当てゝ、技をば大事にすべし。働きをもたしやかに、音曲をも文字にさはさはと当たり、舞をも手を定めて、大事にして稽古すべし。」
十二、三歳、自覚と自負も生まれる少年期。
幼名鬼若といった世阿弥自身、
将軍足利義満に見出される幸運が開けたのは、童形十二歳だった。
なお幼さの影を残す少年の姿-童形の美-は、幽玄へと直に結びつく。
さらに声もしっかりと立ってくる。
ようやく謡の節回しも調子にのり、曲の面白味出てくる。
能の演技にも理解がついてくる頃なので、いろいろと基本にのっとって手数を教える。
声と姿の二つながらの美点のみが発揮されて、欠点はあまり目立たず、この時期特有の上手の花と大いに認められるが、
これは「まことの花」ではなく、「時分の花」だ、と。
だから、この時期の花でもって、能役者としての生涯の定まるものではない、ということ。
この年頃の稽古は、おのずとみえる童形の花は花として見せつつ、しっかりと技術の基礎を身につけさせる。
働き-キビキビとした強い所作-なども一挙手一投足を確かに、音曲も一語一語を大切に正確に、舞いの動きも一つ一つの所作事としてきちんと心にかけて身につけよ、と。
参照「風姿花伝-古典を読む-」馬場あき子著、岩波現代文庫











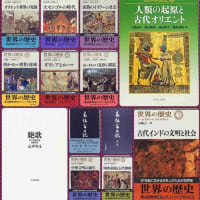
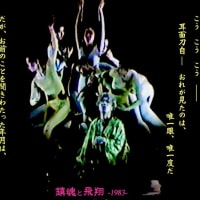
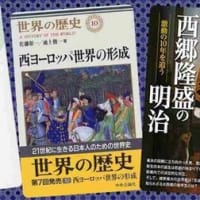
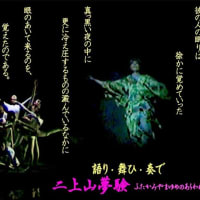
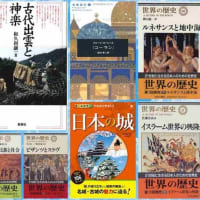
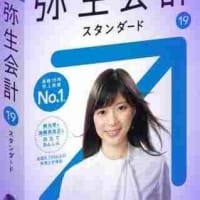
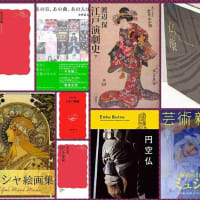
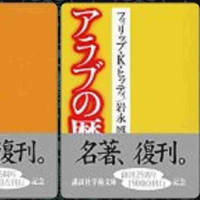
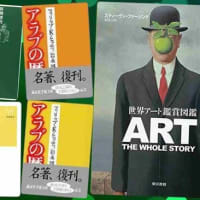
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます