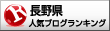サッカー延長戦 延長戦後半に1失点 残念至極
※人生には延長戦はありません。どこかで決着を付けなくてはと思いますが、中々終着人生が見えて来ません。
有賀の祖先のお墓です。

日向共同墓地の草刈り

崩落防止工事 大分落ち着いて来ました。

国分寺赤米出穂 9月10日ごろに稲刈りが出来ればと考えています。

米作りで大変なのは、土手の草刈りと水見です。土手の草を刈ってたい肥化して、少しでも化学肥料を減らす。それで脱炭素化が出来ればと考えています。
1.担い手支援 2.地域交流 3.企業地域貢献(CSR) 4.SDGs 持続可能な地域社会→5年後の農業そして10年後の地域社会を
中山間地域の農業は、少子高齢化が急激に進み農業・地域の空洞化で地域崩壊の危機に陥っています。農業特に稲作で、高齢者、担い手が負担を感じているのは毎日の水管理と、年4回ほどの土手の草刈り作業です。このような状況下で、企業と農家を結び付ける「地域農業支援モデル事業(田んぼの里親制度)」を試験的に実施し、企業・首都圏の皆さんの支援で、中山間地区の農業に、地域に活力を与えたい。企業の地域貢献、社員の福利厚生、企業のイメージアップと、農村を結び付けたい。
〇適切なほ場管理によるCO2削減と刈敷の堆肥化に伴い化学肥料の削減によるCO2削減
※森林のCO2吸収基準を田んぼの土手草刈り作業、刈敷の堆肥化等の評価基準を早急に設定する。
〇遊休荒廃農地の解消により、田んぼが本来持つ貯水能力を高める。適正な草刈りによる土手の強靭化
〇田舎暮らし、農業を体験し、地域住民との交流から農業への就業、移住・定住に繋げる。
〇CO2吸収評価認定を行い、企業の社会的責任(CSR)に基づく田んぼの里親制度をPRし、疲弊する地域と企業との橋渡しを行う。社員その家族が、農業体験を通じて田舎暮らしを身近に感じ移住に繋がることを期待する。
読書マラソンreading 42books marathon 現在12冊目「新選組 幕末の青嵐」に挑戦中!
爺さんのひとり言:着た切りスズメ 野良にいれば着物に無頓着、これからは下着、ズボン、シャツを買ってと思っています。明日シマムラに行こう!
※人生には延長戦はありません。どこかで決着を付けなくてはと思いますが、中々終着人生が見えて来ません。
有賀の祖先のお墓です。

日向共同墓地の草刈り

崩落防止工事 大分落ち着いて来ました。

国分寺赤米出穂 9月10日ごろに稲刈りが出来ればと考えています。

米作りで大変なのは、土手の草刈りと水見です。土手の草を刈ってたい肥化して、少しでも化学肥料を減らす。それで脱炭素化が出来ればと考えています。
1.担い手支援 2.地域交流 3.企業地域貢献(CSR) 4.SDGs 持続可能な地域社会→5年後の農業そして10年後の地域社会を
中山間地域の農業は、少子高齢化が急激に進み農業・地域の空洞化で地域崩壊の危機に陥っています。農業特に稲作で、高齢者、担い手が負担を感じているのは毎日の水管理と、年4回ほどの土手の草刈り作業です。このような状況下で、企業と農家を結び付ける「地域農業支援モデル事業(田んぼの里親制度)」を試験的に実施し、企業・首都圏の皆さんの支援で、中山間地区の農業に、地域に活力を与えたい。企業の地域貢献、社員の福利厚生、企業のイメージアップと、農村を結び付けたい。
〇適切なほ場管理によるCO2削減と刈敷の堆肥化に伴い化学肥料の削減によるCO2削減
※森林のCO2吸収基準を田んぼの土手草刈り作業、刈敷の堆肥化等の評価基準を早急に設定する。
〇遊休荒廃農地の解消により、田んぼが本来持つ貯水能力を高める。適正な草刈りによる土手の強靭化
〇田舎暮らし、農業を体験し、地域住民との交流から農業への就業、移住・定住に繋げる。
〇CO2吸収評価認定を行い、企業の社会的責任(CSR)に基づく田んぼの里親制度をPRし、疲弊する地域と企業との橋渡しを行う。社員その家族が、農業体験を通じて田舎暮らしを身近に感じ移住に繋がることを期待する。
読書マラソンreading 42books marathon 現在12冊目「新選組 幕末の青嵐」に挑戦中!
爺さんのひとり言:着た切りスズメ 野良にいれば着物に無頓着、これからは下着、ズボン、シャツを買ってと思っています。明日シマムラに行こう!