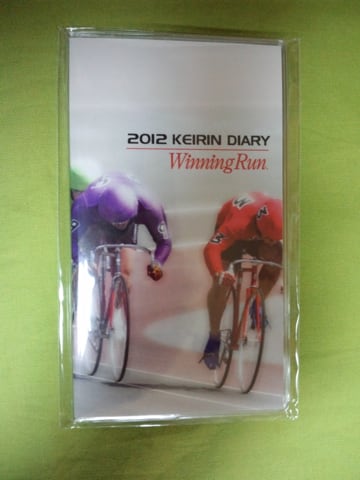今まではコブの上からの写真+シェーマを使って基礎とモーグルのライン取りの解説をしていましたが滑っている写真がなく分かりづらかったと思います。今回ちょうど祓川貴広先生のレッスンで二種類の滑りを練習する機会があったので、これならその差が顕らかであろうと思い祓川先生をモデルに連続写真を作ってみました。斜面はいずれもさのさかB級公認モーグルコース。
上がバンク的なラインを滑ったもの(B)、下がモーグルのライン(M)。
ええっ?と思われる部分があるかも知れませんが、上下のコマはほぼ完全にターンの同じ場所(タイミング)です。
その差はあきらかで、Bは胴体からスキー板は遠くはなれ身体の長い軸を使ったマニューバが認められ、スキー板の移動距離は大きい。
対してMは常に身体の下にスキー板が存在しています。全ての動作がコンパクトで上体は決してフォールライン方向から外れていません。
なので基礎スキーでモーグルのラインを滑りたいと云う方はラインに合わせた動作が必要で、それが出来なければ数ターンではみ出てしまうことになります。
参考までに時間はB1~B5で約1.4秒、M1~M5で約1.2秒となっていました。
これらより分かることは、じゅうらいの基礎の小回り動作のイメージの10分の1の素早さのイメージで(実際にはそこまで必要ないかも知れません)動作を行うことが必要であり、またフォールラインでニュートラルポジションとなるB1とB2の間に相当するM1とM2の間がちょうどコブの膨らみに来ているため、ここで吸収動作が自然に入るのだとイメージ転換することがよいかも知れません。もちろん脚を伸ばして雪面を捉えにいくなどという動作はすでにしていないという前提ありきです。
それよりあまり『吸収』や『ポーパス(ネズミイルカ)な動き』を意識するより、このM1~M2でいかに重心を下方に保つかということに集中するべきでしょう。
それが可能になれば自ずからモーグルの滑りになります。
今日は日曜日でびわ湖バレイの天気も良かったようですが、このところタイトスケジュールと仕事が余りに多忙だったためちょっとお休み。
ゆっくり朝寝してmia嬢とVIGOREさんまでポタリングして来ました。晴れた真冬の京都市内の自転車日和も悪くないものであります。
ところで日本糖尿病学会から、ついに2012年4月1日からHbA1cの表記をJDS値からNGSP値へ切り替えるよう通達が来ました。
今までから両方併記していたので診療には問題ないですが、えっと。。。5月の総会の発表はどうなるの?アブストラクトはJDSで出してるんですが換算しなくちゃいけないのかなぁ。。。めんどくさい(-.-;)
上がバンク的なラインを滑ったもの(B)、下がモーグルのライン(M)。
ええっ?と思われる部分があるかも知れませんが、上下のコマはほぼ完全にターンの同じ場所(タイミング)です。
その差はあきらかで、Bは胴体からスキー板は遠くはなれ身体の長い軸を使ったマニューバが認められ、スキー板の移動距離は大きい。
対してMは常に身体の下にスキー板が存在しています。全ての動作がコンパクトで上体は決してフォールライン方向から外れていません。
なので基礎スキーでモーグルのラインを滑りたいと云う方はラインに合わせた動作が必要で、それが出来なければ数ターンではみ出てしまうことになります。
参考までに時間はB1~B5で約1.4秒、M1~M5で約1.2秒となっていました。
これらより分かることは、じゅうらいの基礎の小回り動作のイメージの10分の1の素早さのイメージで(実際にはそこまで必要ないかも知れません)動作を行うことが必要であり、またフォールラインでニュートラルポジションとなるB1とB2の間に相当するM1とM2の間がちょうどコブの膨らみに来ているため、ここで吸収動作が自然に入るのだとイメージ転換することがよいかも知れません。もちろん脚を伸ばして雪面を捉えにいくなどという動作はすでにしていないという前提ありきです。
それよりあまり『吸収』や『ポーパス(ネズミイルカ)な動き』を意識するより、このM1~M2でいかに重心を下方に保つかということに集中するべきでしょう。
それが可能になれば自ずからモーグルの滑りになります。
今日は日曜日でびわ湖バレイの天気も良かったようですが、このところタイトスケジュールと仕事が余りに多忙だったためちょっとお休み。
ゆっくり朝寝してmia嬢とVIGOREさんまでポタリングして来ました。晴れた真冬の京都市内の自転車日和も悪くないものであります。
ところで日本糖尿病学会から、ついに2012年4月1日からHbA1cの表記をJDS値からNGSP値へ切り替えるよう通達が来ました。
今までから両方併記していたので診療には問題ないですが、えっと。。。5月の総会の発表はどうなるの?アブストラクトはJDSで出してるんですが換算しなくちゃいけないのかなぁ。。。めんどくさい(-.-;)