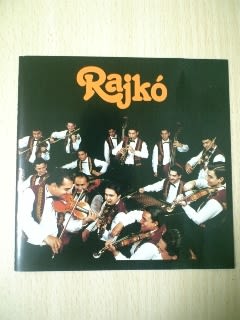今日は三田市吹の個人練習日…ということで脱サイレント(笑)で1時間強の練習。それにしても、一週間欠かさず楽器を吹いたなんて…何年ぶりかなぁ…。
今日はコンクール&袋吹定演曲の「できないとこさらい」。ひたすら反復練習に徹した。
でも、こうなってくると今さらながら楽器中毒だなぁ…。 まぁ、残業規制中の今のうちに貯金をしておくか…。
まぁ、残業規制中の今のうちに貯金をしておくか…。
ところで今日の練習場は某市民センター内のホール。160席・置き椅子(非固定席)なのにフルコンのピアノがあるし、ピアノ庫の広さも十分。

ホールを作る時にフルコンの予算が計上できず、余剰金を集めてようやく購入した某市のレベルが情けない…。 そうそう、明日の袋吹はピアノ合わせなのだが、出し入れ、大丈夫かなぁ…心配な元小屋守である…。(あ、某市じゃなくなっちゃった)
そうそう、明日の袋吹はピアノ合わせなのだが、出し入れ、大丈夫かなぁ…心配な元小屋守である…。(あ、某市じゃなくなっちゃった)

今日はコンクール&袋吹定演曲の「できないとこさらい」。ひたすら反復練習に徹した。
でも、こうなってくると今さらながら楽器中毒だなぁ…。
 まぁ、残業規制中の今のうちに貯金をしておくか…。
まぁ、残業規制中の今のうちに貯金をしておくか…。
ところで今日の練習場は某市民センター内のホール。160席・置き椅子(非固定席)なのにフルコンのピアノがあるし、ピアノ庫の広さも十分。

ホールを作る時にフルコンの予算が計上できず、余剰金を集めてようやく購入した某市のレベルが情けない…。
 そうそう、明日の袋吹はピアノ合わせなのだが、出し入れ、大丈夫かなぁ…心配な元小屋守である…。(あ、某市じゃなくなっちゃった)
そうそう、明日の袋吹はピアノ合わせなのだが、出し入れ、大丈夫かなぁ…心配な元小屋守である…。(あ、某市じゃなくなっちゃった)















 で
で




 俺はそのために来たようだから…
俺はそのために来たようだから… 。
。