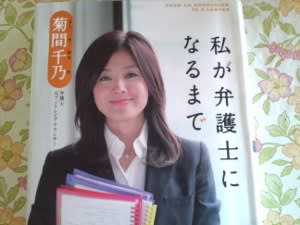ここ何年か、自分の病気についてより、誤解を恐れずに言えば『発達障害』について
とても興味を持っている。
これは、10年ほど前に「発達障害」と言う定義づけがされて、子供の中から問題行動の
ある子に、適切な支援を行う・・・ということが学校で行われるようになった。
しかし、近年、大人の『発達障害』についての記述が多く見られるようになった。
これは、職場や家庭などで悩んでいる人が多いことを示しているように思う。
かく言う私も、なぜこの障害に興味があるかと言えば、程度の軽い人も(というより
そういう傾向がある・・・くらい)いれると、10人に1人くらいに見られるということを
知ったからだ。(この数字は、欧米のものではあるけれど)
『そういや、あの人は変わっていたな~』とか、『何を言い出すか、やりだすかわからなくて
困ったなぁ~』なんて人が、やっぱり、そのくらいの割合でいたので、妙に納得してしまった。
「発達障害と向き合う」 竹内 吉和著 幻冬舎ルネッサンス新書
によると、大人の発達障害は、
・相手構わず一方的に、自分の言いたいことだけを話している。
・こちらの指示が、ほとんど理解されていないような印象を受ける。
・話し合いのとき、ボーっとしていて、話についてこれない。
・適切な速さで話すのが難しく、とても早口だったり、たどたどしく話す。
・意識しても読みにくい字しか書けない。
・簡単なお金や物の個数を間違える。
・目的に沿って、行動することや必要に応じて、それを修正することが難しい。
・物事の優先順位がつけられない。
・早合点や飛躍した考え方をする。
・上司が話をしているのに、話に関係ないことをいきなり発言する。
・手足をそわそわ動かしたり、座っていても常にどこかが動いている。
・指示に従えず、また、仕事を最後までやり遂げることができない。
・仕事を勝手に突然休んでも「すみません」の一言もなく平気な顔で出社してくる。
・デスクの周りに荷物が散乱していて、仕事をするスペースがほとんどない。
・物の置き場所やルールを少し変えただけで、ひどく怒る。
・どこを見ているか判らない様な視線で常に無表情だ。
・その服はあなたには似合わないとか、給料はいくらかとか、言わなくても
いいことを言う。
のうち半分ほどが該当していれば疑わしいのだとか。
けれど、このポイントは、周りで見ている人が気づくポイントであって、
決して、本人が気づくようなないようではない。
ただ、「あ~~そうだったのね~~」と、周りでひそやかに思われて、
避けられるだけ・・・のような気がする。
「発達障害に気づかない大人たち」(職場編)
星野 仁彦著 祥伝社
によると、発達障害に気がつきにくい理由として
・成績がよかった
・趣味や部活など打ち込めるものがあった
・発達のバランスの程度が軽かった
・家庭環境に恵まれていた
などがあると言う。
また、社会性の面でつまづくことが多いので、
・きちんと挨拶が出来る
・上司の言うことが聞ける。
・仕事を頼まれたら、気持ちよく引き受ける
・同僚と協力して仕事が出来る
・身だしなみに気が配れる
・一週間は休まず、遅刻せずきちんと働ける
・報告・連絡・相談ができる
ことを、教えていくことが大事なんだそう。
しかし、これも本人は「出来ている」または「出来る」と、
思いがちなものが多いので、本人はいたって気がつきにくい。
これもまた、周りが「変な人・・・」で終わりそうだ。
社会性をなばす方法として、著者は
「部活」と「アルバイト」をあげていた。
「部活」は、チームプレイの運動部がベストだが、個人技でも
最低の集団性や協調性は身につけられるとのこと。
また、体力不足は。集中力や持久力に影響し心身の疲労度を重くするのだそう。
著者いわく、特別支援が必要ではないけれど、という子供には、放置すると
「パソコン・科学・生物部等」に入ってしまうので、協調性の必要なものへと
導く必要があるとのことだったけれど、子供が希望していないものを
親が誘導するのは、難しいような~。
もう一つの「アルバイト」にいたっては、小さなパン屋さんのような少人数の
職場が理想的なんだそうで、それに周りがその人に理解があること(これが一番だと思うけれど)
が必要なんだそうだ。
医療現場には、発達障害が増えていると、医師でもあり、本人も発達障害をもっていると
告白している著者は言う。
対人援助職といわれる、医療や教師などの職業には、
機能不全家族に育ち、トラウマを抱えた人が少なからずいるのだとか。
機能不全家族で育った場合、自分の持っている劣等感を解消するための手段として
その職種を無意識のうちに選んでいることもあるのだとか・・・。
まあ、著者は医師だから医療現場に増えているような気がするのだろうけれど、
どこの会社も、皆、多くなっているような気がしていると思う。
効率化がどこでも求められて、進められているような状態なので、
チームワークのちょっとしたつまづきを、カバーする余裕がなくなっているし、
周りにいる「健常な?」人間も社会性のスキルが落ちているだろうから、
我慢できなくなっているし・・・・。
まあ、個人的には実態が増えてきたのか、自分の知識が増えてきたからかどうかは不明ですが、
多いな~と正直感じます。
多いだけなら、それなりに対応してきましたが、「箸にも棒にもかからん相手」に初めて遭遇しまして
毎日頭を悩ます日々でございます。
とても興味を持っている。
これは、10年ほど前に「発達障害」と言う定義づけがされて、子供の中から問題行動の
ある子に、適切な支援を行う・・・ということが学校で行われるようになった。
しかし、近年、大人の『発達障害』についての記述が多く見られるようになった。
これは、職場や家庭などで悩んでいる人が多いことを示しているように思う。
かく言う私も、なぜこの障害に興味があるかと言えば、程度の軽い人も(というより
そういう傾向がある・・・くらい)いれると、10人に1人くらいに見られるということを
知ったからだ。(この数字は、欧米のものではあるけれど)
『そういや、あの人は変わっていたな~』とか、『何を言い出すか、やりだすかわからなくて
困ったなぁ~』なんて人が、やっぱり、そのくらいの割合でいたので、妙に納得してしまった。
「発達障害と向き合う」 竹内 吉和著 幻冬舎ルネッサンス新書
によると、大人の発達障害は、
・相手構わず一方的に、自分の言いたいことだけを話している。
・こちらの指示が、ほとんど理解されていないような印象を受ける。
・話し合いのとき、ボーっとしていて、話についてこれない。
・適切な速さで話すのが難しく、とても早口だったり、たどたどしく話す。
・意識しても読みにくい字しか書けない。
・簡単なお金や物の個数を間違える。
・目的に沿って、行動することや必要に応じて、それを修正することが難しい。
・物事の優先順位がつけられない。
・早合点や飛躍した考え方をする。
・上司が話をしているのに、話に関係ないことをいきなり発言する。
・手足をそわそわ動かしたり、座っていても常にどこかが動いている。
・指示に従えず、また、仕事を最後までやり遂げることができない。
・仕事を勝手に突然休んでも「すみません」の一言もなく平気な顔で出社してくる。
・デスクの周りに荷物が散乱していて、仕事をするスペースがほとんどない。
・物の置き場所やルールを少し変えただけで、ひどく怒る。
・どこを見ているか判らない様な視線で常に無表情だ。
・その服はあなたには似合わないとか、給料はいくらかとか、言わなくても
いいことを言う。
のうち半分ほどが該当していれば疑わしいのだとか。
けれど、このポイントは、周りで見ている人が気づくポイントであって、
決して、本人が気づくようなないようではない。
ただ、「あ~~そうだったのね~~」と、周りでひそやかに思われて、
避けられるだけ・・・のような気がする。
「発達障害に気づかない大人たち」(職場編)
星野 仁彦著 祥伝社
によると、発達障害に気がつきにくい理由として
・成績がよかった
・趣味や部活など打ち込めるものがあった
・発達のバランスの程度が軽かった
・家庭環境に恵まれていた
などがあると言う。
また、社会性の面でつまづくことが多いので、
・きちんと挨拶が出来る
・上司の言うことが聞ける。
・仕事を頼まれたら、気持ちよく引き受ける
・同僚と協力して仕事が出来る
・身だしなみに気が配れる
・一週間は休まず、遅刻せずきちんと働ける
・報告・連絡・相談ができる
ことを、教えていくことが大事なんだそう。
しかし、これも本人は「出来ている」または「出来る」と、
思いがちなものが多いので、本人はいたって気がつきにくい。
これもまた、周りが「変な人・・・」で終わりそうだ。
社会性をなばす方法として、著者は
「部活」と「アルバイト」をあげていた。
「部活」は、チームプレイの運動部がベストだが、個人技でも
最低の集団性や協調性は身につけられるとのこと。
また、体力不足は。集中力や持久力に影響し心身の疲労度を重くするのだそう。
著者いわく、特別支援が必要ではないけれど、という子供には、放置すると
「パソコン・科学・生物部等」に入ってしまうので、協調性の必要なものへと
導く必要があるとのことだったけれど、子供が希望していないものを
親が誘導するのは、難しいような~。
もう一つの「アルバイト」にいたっては、小さなパン屋さんのような少人数の
職場が理想的なんだそうで、それに周りがその人に理解があること(これが一番だと思うけれど)
が必要なんだそうだ。
医療現場には、発達障害が増えていると、医師でもあり、本人も発達障害をもっていると
告白している著者は言う。
対人援助職といわれる、医療や教師などの職業には、
機能不全家族に育ち、トラウマを抱えた人が少なからずいるのだとか。
機能不全家族で育った場合、自分の持っている劣等感を解消するための手段として
その職種を無意識のうちに選んでいることもあるのだとか・・・。
まあ、著者は医師だから医療現場に増えているような気がするのだろうけれど、
どこの会社も、皆、多くなっているような気がしていると思う。
効率化がどこでも求められて、進められているような状態なので、
チームワークのちょっとしたつまづきを、カバーする余裕がなくなっているし、
周りにいる「健常な?」人間も社会性のスキルが落ちているだろうから、
我慢できなくなっているし・・・・。
まあ、個人的には実態が増えてきたのか、自分の知識が増えてきたからかどうかは不明ですが、
多いな~と正直感じます。
多いだけなら、それなりに対応してきましたが、「箸にも棒にもかからん相手」に初めて遭遇しまして
毎日頭を悩ます日々でございます。