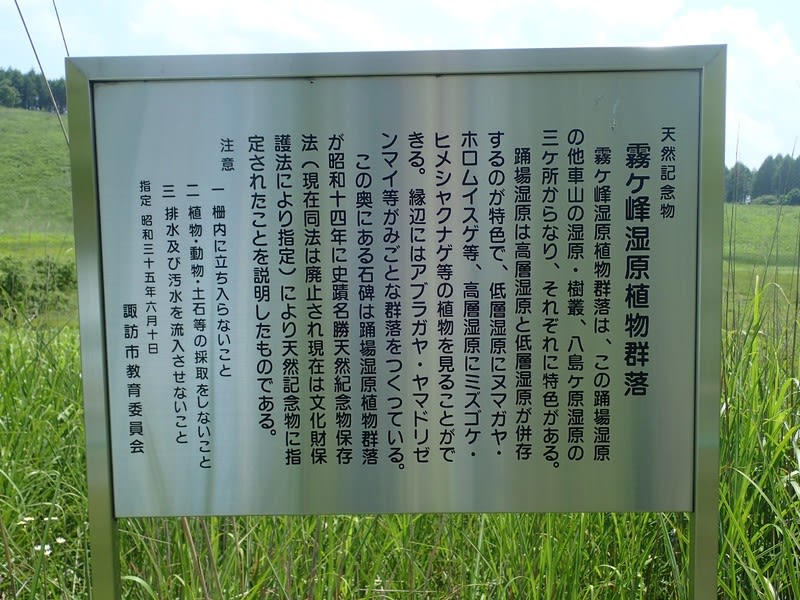開田高原アメダス 今朝の最低気温 17.1℃ 昨日の最高気温 30.7℃
木曽町新開 午前7時の気温 19.5℃ 今朝の天気 晴れ
拙宅は標高1000メートル
かなりの山の中である。
すぐそばを川が流れ
窓を開けると
川の音が大きく聞こえる。
都会と違って
虫に囲まれて
生活していると言っても
過言ではない。
今回は家の周りで
見つけた虫たちを
見ていただこう。
まず美しい甲虫の中に
入ると思われる
ルリボシカミキリ。

毎年1~2度
薪を積んでいるあたりで
見かける。

甲虫に疎い私でも
知っている有名な
カミキリムシだ。

この子も
小さいがなかなか
味のある色艶をしている
リンゴコフキゾウムシ。

金属光沢が美しいけど
名前が分からない甲虫も。

タマムシのように美しい
アオハムシダマシ
今回で2度目の出会い。

交尾中のスジグロベニボタルに
おじゃま虫でした。

川が近いので
カゲロウやカワゲラの
仲間はわんさかといる。

(カワゲラの仲間)
夜あかりに集まる
蛾の仲間は
数えきれないぐらい
飛んでくる。
今回は昼間見つけた
蛾の仲間。
蝶のように美しい
ホシベッコウカギバ。

何かに擬態でも
しているの?
尋ねたくなる
スカシサン。

まだまだ
撮りためた写真が
多数あるのだが
名前が分からず
お蔵入りの予定。
北海道のブロ友
昆虫探偵団の
だんちょうさん
名前間違っているかも?
不明種もお教えください。