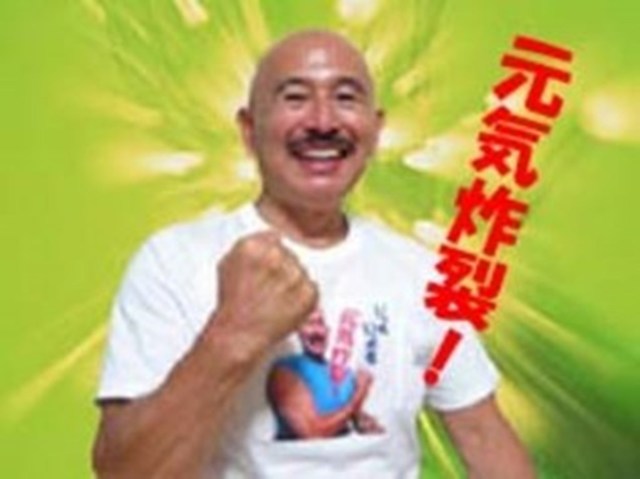先週の24日は風が強く厚着をしていても冷たい空気が体にしみ込むような
本当に寒い一日だったが、こころ温まる思い出の一日となった。
その日、私たち夫婦は朝8時過ぎに家を出て、車で足利市の美術館などを
巡る計画を実行し、忘れられない寒さと共にその何倍もののいい思い出を
作ることができた。
岩槻インターから佐野藤岡までは高速を利用し、流れの良い50号線を
快適走行して最初の目的地の『華雨蔵珍之館』に到着したのは開館(10時)の
20分ほど前であった。
ここは事前(1週間ほど前)に予約が必要ということを聞いていたので私たちも
月末近くになるかな?・・・と思いながら3日後の見学を問い合わせると
応対された方は親切な対応で快く承知してくださりスタートからラッキーだった。
この『華雨蔵珍之館』には2000点以上もの中国石材拓本が収蔵されていて
ネットの説明などにも『中国本土ではすでに失われていて、今やここでしか
見られない拓本も多く、中国文明の中核とも骨格ともいえるような文化遺産が
うず高く収められている、言わば“知と文化の宝庫”だ』という
杉山正明京都大学教授の説明もある。
高い天井の館内では圧倒されるような大きな拓本の数々と孔子に関する多くの
所蔵品やその説明に2000年を遥かに超える時代に思いを馳せと自分が如何に
小さなものであるのか・・・と再認識させられた。
と同時に長い歴史の中国文明の偉大さや重み、日本が受けた影響と進化の素晴らしさ、
などを強く感じた。
そしてこんな素晴らしい文明、文化を作り上げた中国とその思想の雄大さを思うと
昨今話題に取り上げられている現在の中国人のマナーの問題などに激しい違和感を
覚え、考えさせられるものがあった。
今後は日本、中国共に論語の精神のいいところをもっともっと汲み取り、猜疑心や
疑心暗鬼に振り回されることなく、奢らず謙虚な心で素直でより良い交流を続けて
いくべきであろうと思った。
書道家や専門家だけではなくできれば誰でも気軽に足を運び素晴らしい作品や
いろいろな説明を聞き、拓本の体験教室などを通じて身近に感じていただきたい
と思った。
当日私たちに案内や説明をしてくださった松葉さんという方が素晴らしい方だったので
このブログをみてくださった方にも是非行っていただきたいと思う。
足利市内を流れる渡良瀬川を見ながら次の目的地『市立美術館』へ・・・
ところが12月25日から1月25日までは展示替えのための休館で後日改めていくことにした。
続いて『足利学校』へ・・・
足利学校は以前一度訪れたことがあるが今回は時間をかけてゆっくりと見ることにした。
足利学校は平安時代、或いは鎌倉時代に創設されたという説や室町時代に開かれたという
説もあるようだがその歴史が明らかになり整備されたのは室町時代の中期以後だという。
戦乱の世の中でも学問が尊ばれ、その後も武士、僧侶、歌人、文人、そして町民の
為にも活用され、今後も「教育の原点」「生涯教育の場」としてさらに充実した
活動と利用がされていくという素晴らしい場所に佇み穏やかに流れる時間を楽しみ
学校門、杏壇門をくぐるときには自然に厳かな気持ちになっていた。
足利学校の次はアートと厄除の寺『龍泉寺美術館へ』・・・
棟方志功や横山大観、伊藤若冲の作品も素晴らしいがこの美術館の企画展も
見ごたえがあるようなので今後も二度三度と訪れてみたいと思った。
本当に寒い一日だったが、こころ温まる思い出の一日となった。
その日、私たち夫婦は朝8時過ぎに家を出て、車で足利市の美術館などを
巡る計画を実行し、忘れられない寒さと共にその何倍もののいい思い出を
作ることができた。
岩槻インターから佐野藤岡までは高速を利用し、流れの良い50号線を
快適走行して最初の目的地の『華雨蔵珍之館』に到着したのは開館(10時)の
20分ほど前であった。
ここは事前(1週間ほど前)に予約が必要ということを聞いていたので私たちも
月末近くになるかな?・・・と思いながら3日後の見学を問い合わせると
応対された方は親切な対応で快く承知してくださりスタートからラッキーだった。
この『華雨蔵珍之館』には2000点以上もの中国石材拓本が収蔵されていて
ネットの説明などにも『中国本土ではすでに失われていて、今やここでしか
見られない拓本も多く、中国文明の中核とも骨格ともいえるような文化遺産が
うず高く収められている、言わば“知と文化の宝庫”だ』という
杉山正明京都大学教授の説明もある。
高い天井の館内では圧倒されるような大きな拓本の数々と孔子に関する多くの
所蔵品やその説明に2000年を遥かに超える時代に思いを馳せと自分が如何に
小さなものであるのか・・・と再認識させられた。
と同時に長い歴史の中国文明の偉大さや重み、日本が受けた影響と進化の素晴らしさ、
などを強く感じた。
そしてこんな素晴らしい文明、文化を作り上げた中国とその思想の雄大さを思うと
昨今話題に取り上げられている現在の中国人のマナーの問題などに激しい違和感を
覚え、考えさせられるものがあった。
今後は日本、中国共に論語の精神のいいところをもっともっと汲み取り、猜疑心や
疑心暗鬼に振り回されることなく、奢らず謙虚な心で素直でより良い交流を続けて
いくべきであろうと思った。
書道家や専門家だけではなくできれば誰でも気軽に足を運び素晴らしい作品や
いろいろな説明を聞き、拓本の体験教室などを通じて身近に感じていただきたい
と思った。
当日私たちに案内や説明をしてくださった松葉さんという方が素晴らしい方だったので
このブログをみてくださった方にも是非行っていただきたいと思う。
足利市内を流れる渡良瀬川を見ながら次の目的地『市立美術館』へ・・・
ところが12月25日から1月25日までは展示替えのための休館で後日改めていくことにした。
続いて『足利学校』へ・・・
足利学校は以前一度訪れたことがあるが今回は時間をかけてゆっくりと見ることにした。
足利学校は平安時代、或いは鎌倉時代に創設されたという説や室町時代に開かれたという
説もあるようだがその歴史が明らかになり整備されたのは室町時代の中期以後だという。
戦乱の世の中でも学問が尊ばれ、その後も武士、僧侶、歌人、文人、そして町民の
為にも活用され、今後も「教育の原点」「生涯教育の場」としてさらに充実した
活動と利用がされていくという素晴らしい場所に佇み穏やかに流れる時間を楽しみ
学校門、杏壇門をくぐるときには自然に厳かな気持ちになっていた。
足利学校の次はアートと厄除の寺『龍泉寺美術館へ』・・・
棟方志功や横山大観、伊藤若冲の作品も素晴らしいがこの美術館の企画展も
見ごたえがあるようなので今後も二度三度と訪れてみたいと思った。