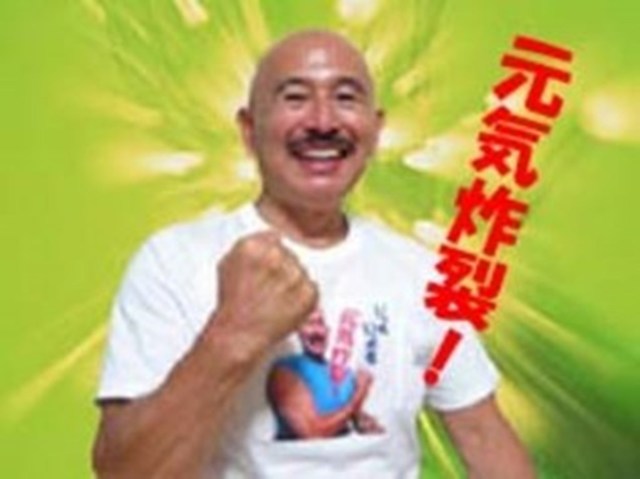まだ食べられるものが日々大量に捨てられているという「食品ロス」、
日本では年間643万トンものロスが発生しているという。
わかりやすく言うと国民一人当たり毎日茶碗一杯のご飯を無駄に
捨てている数字と言うことになるようだ。
アフリカをはじめ世界各地には飢餓に苦しむ子供たちが数多くおり、
飢餓人口が増え続けていることを忘れてはいけないと思う。
コンビニ大手のセブンイレブンやローソンでも廃棄ロスに取り組んでいる
ことが伝えられているが今朝の新聞に食品ロスの削減は働き方改革でもある・・・
という記事があった。
記事によれば日本人は見た目に厳しく、農家が収穫しても規格外で
出荷されないものもたくさんあるとのこと。
また消費者優先の為か販売店では棚には常に新しい物、新鮮なものを
並べ、賞味期限内でも撤去するという。
『捨てられるものを最初から作らなければ働く人はもっと楽だし、資源も無駄にならなかった』と食品ロス問題専門家の井出留美さんは発想の転換を促している。
また料理研究家の土井善晴さんは『食べられないほどのものを買っては
いませんか』と問いかけ、食べ物にストレスや不安の解消を求めたり
加工食品に頼る暮らしをしたりする人が増えたことについても
『人間が料理をしなくなった影響は大きい』と感じているそうだ。
土井さんはまた『子供も一人暮らしの人も、ご飯と味噌汁が作れれば
自分に自信がつく。無駄を出す暮らし方は選ばなくなるでしょう』とも
話している。
過日の新聞でも昨年土井さんがツイッターに朝食の写真を投稿し、
物議を醸したことが報じられていた。
それは三重県の和菓子「赤福」と味噌汁についてだが・・・・。
『正しい日本の朝食ではない』『健康に悪そう』という読者の反応に
土井さんは『何言うてんねん。石頭やな-』『家の中の多様性を認めてください』と
切り返し、「背中を押された」「救われた思い」などと沢山の支持を得たという。
土井さんがどうして家の中の多様性を大切にするのか・・・の
インタビューをしたジャーナリストで作家でもある中原一歩さんは
土井さんの『家にあるもんを食べる、当たり前のこと、普通のことだと
思いますよ。赤福だって早く食べないとダメになるし、勿体ないでしょ』
『なんでみんな一緒の朝ごはん食べなあかんのですか(中略)
自分と違う考えを持っている人が気になるのは、ほんまに
弱い人です』という言う言葉の中に日本人の多くの人が縛られている
無意味なルールのようなものがあぶり出し、何をどのように食べるか
各家庭違っていいし、自由でいいというメッセージは多くの人を
開放すると伝えている。
料理研究家土井さんの言葉には食品ロスの削減に繋がるごく自然な
日常が大切であることを感じる。
全国にあるファミリーレストラン「デニーズ」では今年の春(4月)から
食べ残した料理を持ち帰ることができるようになった。
以前は衛生上懸念されることから持ち帰りは原則的にダメだったが
食品ロス削減のために一定の条件付きでルールを変えたのだという。
それは持ち帰りの申し出があった場合「持ち帰りは客の責任において」
というような説明文を確認してもらう。
「持ち帰り用の容器、ポリ袋、保冷剤などは店側で用意する」
「容器への詰め替えは客が自ら行う」ということで持ち帰る食材は
客の判断によるもの…ということらしい。
デニーズでは食べ残しを減らすようにライスの小盛りにも対応し、
同社が運営する喫茶店などでも食品ロス削減のために持ち帰りが
できるようにしている。
居酒屋などを運営する「ワタミ」でも持ち帰りに対応し、長野県では
かなり前から『食べ残しを減らそう県民運動』という活動があり、
中華料理店などでも持ち帰り用の容器を用意しているという。
更に食べ残すことを想定し、『持ち帰り用の容器を持ち歩こう』という
消費者側からの運動もあるとのこと。
年間の食品ロス643万トンのうち外食産業から出るものは133万トン
以上もあり、食べ残しによるものがその60%を占めるという。
食中毒予防には最大限の注意を払っての持ち帰りや、「食べきり」
「小盛メニュー」の選択なども含め、我々一人一人が食品ロスを考え
ながら食事を楽しくすることを考えたいと思う。
まさに一人一人の小さな心がけで食品ロスは大きく削減できるのだから。