その3.の①
久々に見る懐かしい「胴乱」
「らんまん」のテーマ曲あいみょんの「愛の花」を聴きながら
その画面を見ていくと万太郎(神木隆之介)が「胴乱」を肩から
掛けながら歩いている。(宙を飛んでいる姿も・・)
私が小学3、4年生の頃だと思うが、父と弟の3人で時々出かけることが
あり、歩いて行ける範囲の雑木林などへも出かけていた。
社会科や地理の教師で郷土の市史編纂委員もしていた父は日頃何かと
忙しく、その中で時間がある時には5人の子供たちの4番目、5番目である
私たちに様々なことを体験させたかったのだと思う。
そのいくつかの体験の中でよく覚えているのが「※倶利伽羅峠の戦い」が
あった場所や土器などの採掘場所に連れて行ってくれたことである。
※「倶利伽羅峠の戦い」
(平安時代の末期、越中(富山)と加賀(石川)の国境にある砺波山の
倶利伽羅峠と呼ばれる場所で源義仲軍と平維盛率いる平家軍が激突した
戦のこと)
その外出時に常に私が担当係のような役目(?)で持って行ったのが
「胴乱」・・・
土器の欠片を入れたり、雑木林で拾った何種類かの葉っぱや木の実、
そして時々は弟が好きだった昆虫なども入れていたと思う。
下の写真で私が腿の上に乗せている鞄のようなものがその「胴乱」・・・


私たち子供は「どうらん」という発音で覚えたまま大人になり、
今日に至ったが今回、「らんまん」をみて「どうらん」とは
日本語なのか、外国語なのか・・どんな文字で表すのだろう?と思い、
検索してみて初めて「胴乱」という漢字であることを知った。
さらに由来や使用についても調べると・・・
〇日本古来の小型のかばんの呼び名。
〇筒卵とも表記される。
〇薬や印などを入れて腰に下げる長 方形 の袋。.
〇江戸時代初期に鉄砲の 弾丸 入れとして用いられたのが始り。
〇 最初は革、のちには 羅紗 などの布で作られたが、明治初期には
再び革製が流行して、手さげ胴乱、肩掛け胴乱も作られた。.
〇採集した植物を入れて持ち歩く円筒状の容器。
などということがわかった。
「胴」や「筒」が使われるのは何となくわかるような気がするが
その後に「乱」や「卵」がつくのはなぜだろう?
私が使っていたのは下図のような軽い金属製のもの。


昔の胴乱の画像をみると素晴らしいと思えるものも多かった。
上方落語の演目の一つに「胴乱の幸助」というのがあるそうだが
どんな話なのか興味が湧いてきた。


























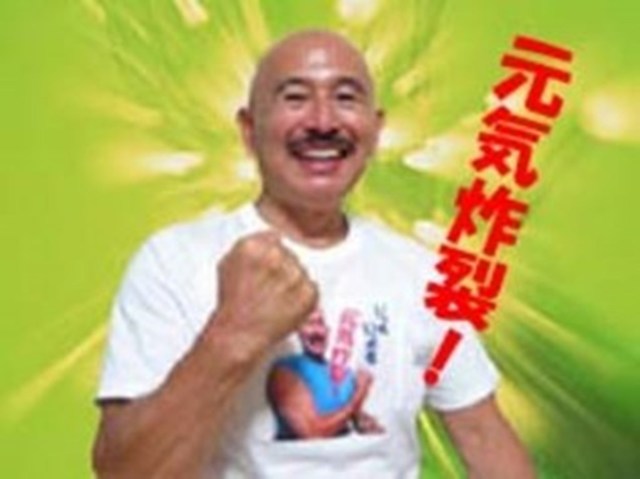

貴重な写真をみせていただきありがとうございます。
何処かの待合室?駅かな?
白黒写真を見るとほんとに懐かしい日本の風情感じます。
お父様と一緒に色んなところを探検されたんですね。
実際に目で見て体験させることは、良い思い出にもなるし最高の教育だと思います。
胴乱、そういえば、こういうものを祖父が持ってたような。うるおぼえですが祖父も獣医だったので、この中に薬とか注射器を入れてたような……
倶利伽羅峠の乱、これもなつかしいことばです。
家から車で10分くらいのところに三之倉という集落があります。
木曽義仲が近江国粟津で敗れ、その家臣今井四郎兼平が一族とこの三之倉に隠れ住んで、棒の手を村人たちに教えだという歴史があります。
胴乱の幸助、
ちょっと興味湧きました。
さっそくしらべてみようとおもいます。
令和でも流行りそうな感じです(^-^)
土器の採掘良いですね♪ 我が家の三姉妹も 鹿嶋市で 遺跡発掘調査した事があります。それはとても良い体験になりました♪
胴乱、そういう名前のものだとしか
思っていませんでした。
>〇江戸時代初期に鉄砲の 弾丸 入れとして用いられたのが始り。
なぜそれが植物採取の箱として定着したのでしょうね?
不思議です。
「らんまん」はよほど、
shimaさんの思い出を刺激するドラマのようですね😊
これからも楽しみにしています。🌸
そうです、昔の駅の待合室で採った写真なんですが、弟は昆虫採集ができると思ってわくわく、ニコニコしていたのです。
ご祖父様が獣医さんでしたらお持ちになっていた可能性充分ですね。
木曽義仲や倶利伽羅峠の名前が咄嗟に浮かぶとは・・leelinさんは歴史にも詳しいのですね。
胴乱の幸助は私もどんな花以下調べてみるつもりなんですよ。
はい、記事にも書きましたが胴乱はいろんなことに使われていたようですから私の父も私たちにいろんな用途を教えたのだと思います。
私にも土器の採掘は楽しかった記憶があります。
お子さんたちも遺跡発掘調査をされたとはいい体験になったと思いますね。
そして学んだことも・・・
胴乱の素材や形や用途の変化は時代と共に変化したことは本当に不思議ですね。
やはり人の考える力なのでしょうか、改善する力も見事ですね。
らんまんからはまだまだ学べそうです。
おはようございます☀️
「らんまん」🎵
本当に楽しいですね~🎵
shimaさんの心の琴線に触れる色々な話題かいっぱいですね。
胴乱は知らなかったです。面白いものですね~🎵
そして実は、
私が夫とよく行く六甲山の森林植物園では、2.3年前から、「らんまん」の牧野博士が見つけた色々な植物が、至るところに看板が立てられ説明されてたので、本当に楽しみにしていたのです。
そんな植物を見るのも楽しいし、
人物像とか、姉弟の関係(実は私もひとり弟がいて、姉弟です。なんか同じような感じです笑)
とか、私にとっても面白さ満載です。
これからも楽しみに見ていきますよ🎵
「らんまん」が始まる前は『今度のドラマは果たしてどうなのだろう?』と思っていましたが日に日に面白くなってきましたね。
今日の蘭光先生の言葉も良かったですね。
ただ、今後ちょっと気になることが・・
(ちょっと大袈裟で、とるに足らないことなんです。)
今日の放送の終わりの部分で成長した万太郎(神木隆之介)と竹雄(志尊淳)が出てきましたね。
問題(?)はこれからなんです。
(と言ってもわざとらしくふざける私のスタイルで・・・)
今後万太郎の姉(綾)を演じるのは佐久間由依さんですね。
佐久間由依さんと言えば・・・
勿論、みっちっちさんが真っ先に思い浮かぶのは推しの綾野剛さん・・・
「綾」と「綾野」は偶然だとしても・・・???
でも心の広いみっちっちさんは既に佐久間由依さんのことも認め(?)応援するくらいおおらかな気持ちで鷹揚に構えているのですからね。
みっちっちさんをおちょくるつもりで書こうと思ったのですが、やはりだめです。
ふざけるわけにはいきませんでした。
身も心も爽やかに躍動しているみっちっちさんの姿に見事に跳ね返されました。
さあ、大爆発の心地良い爆風をいっぱい浴びて私も舞いあがりましょう。
麦わらで「蛍かご」も作り、蛍を捕集していましたが、それも秋の昆虫かごとして使っていました。蛍かごの編み方は完全に忘れてしまいました。
いまは何でもお金で買える時代ですが、私達の頃は「モノの無い時代」でしたから、Shima さんもご存じのように、遊び道具は何でも自分達で作りましたよね。
小学生の低学年でも「肥後ナイフ」を持つことは、男子生徒のステイタスだったような時代ですから。
工夫力・創造力の無い、いわゆる考える力の無い、鉛筆も削れない、指をケガした痛みを知らない子供が育ち、やがて命の尊さを知らない大人になるのは、社会構造や教育制度の問題ですね。
「胴乱」を検索してみると色々なものがありました。
昔の人の智恵と改善能力は凄いですね。
highdyさんも竹ひごの思い出をお持ちなんですね。
あの頃は私たち子供でも大きな竹を割る時の竹割り包丁や鉈などの使い方も覚えましたよね。
そしてひごなんかを作る時には「肥後の守」を使いましたね。
肥後の守は男の子の必需品でしたね。
そうでしたステイタスでした。
ノコギリで木を切って、ナイフで削って、船を作り、模型用のスクリューとゴムひもで走らせた懐かしい思いでも甦ってきます。
現在、竹ひご抜きを見せても解らない大人がかなりいると思いますね。
今は肥後ナイフや切り出しナイフを使って鉛筆を削れる人も高齢者を除くとほとんどいないのではないでしょうか。