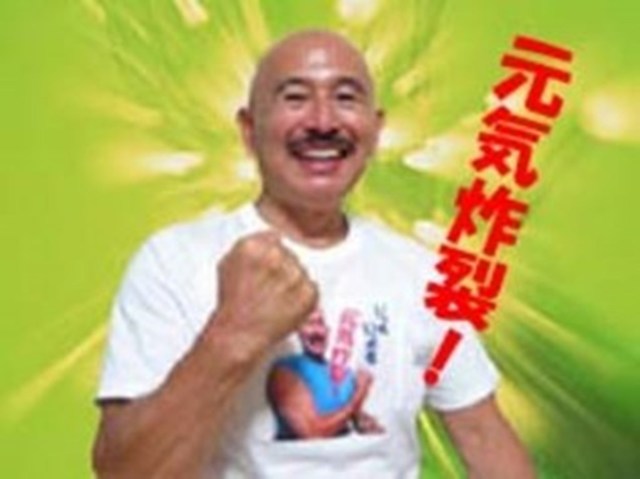若者たちの熟語や慣用句、故事、ことわざの誤用や間違った言い方、
本来の意味とは違う意味での使い方を私は残念に思うことがあるが、
現代ではその由来よりも『言葉は進化するもの・・・だから新解釈を
認めるべき』という説も広まっているようだ。
果たしてそれでいいのだろうか?
私たちは子供の頃から親や先生から漢字や言葉の読み方や意味などを
きちんと正しく教えられてきたと思う。
ところが最近はその成り立ちによる本来の意味や使い方が疎かに
されているような気がするし、熟語や慣用句、故事、ことわざなども
誤用によって一部ではそれも認められてしまうというような残念なことも
起きているようだ。
こんなことを分かったように言う私自身も恥ずかしながら40代の頃まで、
『姑息(こそく)』の本来の意味を知らず、『間、髪を容れず』の意味は
わかっていたが『かん、はつをいれず』という正しい読み方ではなく、
『かんぱつをいれず』と読んでいた。
『姑息』については私以外にも狡いとか、卑怯とかという意味で理解
している人が多いのかもしれないが、本来の意味である『一時しのぎ』という
意味で使われるケースがだんだん少なくなり、誤用が誤用ではないように
理解されているのだろうか。
『間髪を容れず』についても間と髪の間を区切った表示ではなく
間と髪を続けて書き、かんぱつと読んでも不思議ではないので
私もかんぱつと読んでいたが、指摘された時には自分でわかっていた
つもりの意味を初めて本当に理解できたようで、恥ずかしさと共に
知る喜びを大きく感じた。
最近では少なくなったのかもしれないが、有名人でも下記の使い方を
間違う人がかなりいた様な気がする。
『名誉挽回』と『汚名返上』を混同し、有名人でも『汚名挽回』と言ってる
様子を今も時々見ることがあるが、二度と着せられたくない汚名は
返上するものであり、決して挽回するものではないことは文字からも
理解できる筈・・・。「汚名」「名誉」という音声が混同を招くのだろうか。
やはり文字を書くことの大切さがわかるような一例ではないだろうか・・・。
また最近は若者に限らず大人でも『ヤバイ』という言葉をいい意味でも
悪い意味でも使うことが多いようだ。
『全然』もそうだと思う。
私たちは『全然』の後には打消しや否定的な言葉がつく・・・「まるっきり」、
「まるで」、「全く」、「少しも」・・・というような場合に使う言葉として習ってきたと
思うのだが最近は『全然いい』『全然大丈夫』などのように肯定的な表現
として使われることも多いようだ。
私は肯定的な表現に使うことには抵抗があるが歴史上では日本語に
関する言論誌の中でも肯定的な表現で使われているということもあり、
夏目漱石や石川啄木、芥川龍之介の作品にも「全然プラス肯定」の
表現が使われているという。
言葉は時代と共に進化したり使われ方が違ってもそれを受け入れると
言うのも一理あるとは思うが間違った使い方はやはりやめるべきでは
ないだろうか。
例えば・・・
『しおどき』はもともと物事をするのにちょうど良い時と言う意味が
「終わりの時」「引退や引き際」という意味で使われることが多く、
ちょうどいいタイミングという意味では使われることが少ないかも・・・。
『さわり』も話などの最初の部分ととらえる人が多いようだが本来は
話などの要点であり、これも誤用されることが多いのではないか。
『檄を飛ばす』は「檄」を激励の「激」と間違えているものと考えられるが
「檄」には激励やひとを励ますと言う意味はなく、元々は木札に書いた
文書のことで人々を呼び集めたり、同意を促すことで口頭で伝える
ものではなかったようだ。
しかし現在ではスポーツの世界でも監督やコーチなど指導者が
叱咤激励する場面で「檄をとばす」と間違った表現が当たり前のように
使われているようだ。
『鳥肌が立つ』も本来の意味の寒さや恐怖によるものとは違う使い方で
例えば、演奏や演技、奇跡的な逆転勝利の場面など物事に大きく感動
した場面でも使われているようだがこれも間違い。
『悲喜こもごも』も正しくは一人の人間の心情、心境や感情を表わすときに
使う言葉で、複数の人の喜びや悲しみを表現する言葉として使うのは
これも間違い・・・。
これらは以前に比べて本を読むことが少なくなってきたからだろうか?
それとも話し言葉が主となり読んだり書いたりということが少なくなって
きたからだろうか?
若い人たちでもきちんと正しく使い分けている人たちも少なくないとは
思うのだが…
現在はパソコン、スマホなどでも素早く意味や由来などを調べることが
できるのでも言葉についても、もっともっと上手く活用すればいいと思う。
したり顔する高齢者の自己満足と思われるかもしれないが、何事も
正しいことを知ることは決して無駄ではないし、自らを反省したり
鼓舞するためにもいいことだと私は思っている。